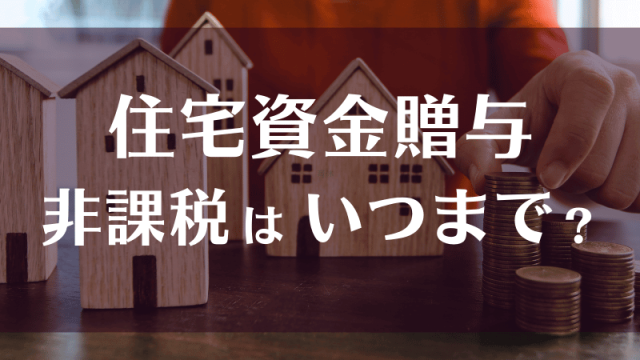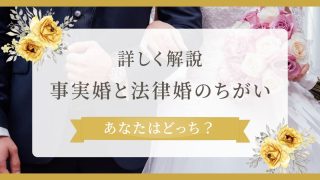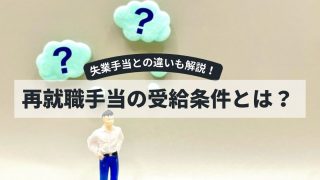「諸費用が高すぎて困った」「費用の内訳が分からず不安」と、気に入った住宅物件を見つけたのに、諸費用の金額を見て驚く人も少なくないでしょう。
住宅ローンを契約する際に支払う手数料や保証料、不動産の税金などは、諸費用だけで数百万円単位の費用が発生することもあります。
後々になって資金計画を見直さざるを得ない場合も出てくるため、念入りに事前の確認をしておくことが重要です。
本記事では、諸費用の全体像から主要な項目の内訳や相場、支払のタイミングまで網羅的に分かりやすく解説します。
諸費用に対する漠然とした不安が解消されるだけでなく、安心して資金計画を立てられるようになるでしょう。
住宅ローン契約時にかかる諸費用の全体像

住宅を購入する際、物件の価格以外にも、住宅ローンの契約などで必要となる「諸費用」を含めた資金計画を立てておく必要があります。
諸費用は、金融機関でローンを組む際の費用に加え、不動産に関する税金や手数料も多く、高額となる場合もあるからです。
事前に把握しておかないと想定以上の出費に慌てることもあり、中には予算の関係上から物件を変更せざるを得ないケースもあるでしょう。
まずは、住宅ローンの契約において物件価格以外にもさまざまな費用が必要になるという点を認識しておくことが重要です。
諸費用とは?必要となる主な項目
住宅ローンを契約する際に必要となる「諸費用」について説明していきましょう。
融資手数料 :事務手数料として支払う
保 証 料 :保証会社付の住宅ローンに対して保証会社へ支払う
印 紙 税 :契約書に貼る印紙代
登録免許税 :不動産を自分の名義として登記する際の税金
不動産取得税 :土地や建物を取得した際の税金
司法書士手数料:司法書士へ登記などを依頼する手数料
仲介手数料 :住宅の売買に対して仲介してくれる会社への手数料
火災保険料 :建物に掛ける保険料
地震保険料 :火災保険と同様
なお、直接不動産会社と売買ができる場合は仲介会社を通じて取引をしないため、仲介手数料は掛かりません。
引っ越しをする際の費用や、水道の加入金なども別途掛かるため、事前に全体の金額を把握しておきましょう。
諸費用の相場は物件価格の3〜10%
諸費用の内訳を理解したとしても、重要なのは「いくら必要になるか」を把握しておくことでしょう。
諸費用の金額は、購入する物件や住宅ローンの内容によって異なりますが、新築物件の場合3%〜7%程度、中古物件の場合6%〜10%程度が目安です。
例えば、
4,000万円の新築物件の場合は120~280万円
3,000万円の中古物件の場合は180~300万円
掛かります。
中古物件の場合、仲介手数料や登録免許税の税率が高くなる傾向もあるため、諸費用が割高になるケースが多いでしょう。
住宅ローンを組む際の金融機関や、ローンの期間によっても保証料が異なり、さらに火災保険のプランによっても変わります。
いずれにせよ、百万円単位のまとまった費用が必要となるため、物件の価格だけでなく諸費用も含めた資金計画を立てることが大切です。
主要諸費用の内訳と目安金額

住宅を購入する際の諸費用については、比較検討することで少しでも低く抑えられる可能性があります。
例えば、住宅ローンの手数料は金融機関によって異なりますし、仲介手数料も不動産業者によってはキャンペーンなどによって抑えられるでしょう。
それぞれの項目に対して具体的な相場を知っておくことで、より正確な資金計画を立てられるため必ず事前に確認しておくことが大切です。
ローン手数料・保証料の相場と違い
諸費用の中でも、金融機関や保証会社へ支払う「ローンの事務手数料」や「保証料」は高額となる場合があります。
ローン手数料は「事務手数料」や「融資手数料」などと呼ばれていますが、大きく分けると「定額型」と「定率型」の2種類です。
定額型は借入額に関わらず3〜5万円程度に設定されていますが、定率型は借入額の2.2%程度で計算されるため、借り入れが大きいほど高額となります。
保証料ですが、万が一返済が困難になった場合に、保証会社が金融機関に変わって返済するために支払うために必要です。
なお、保証料の場合、繰上返済を行うと一部保証料が返戻されるケースもあるため、確認しておきましょう。
印紙税
諸費用は様々な項目に分かれますが、代表的なものとして挙げられるのが「印紙税」です。
例えば、金融機関と「金銭消費貸借契約書」を結ぶ際に交わされる場合や、不動産会社と「売買契約書」を結ぶ際にも印紙を貼り付けます。
なお、印紙税の金額は、以下の通りです。
「不動産の場合」
| 不動産売却価格 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5千万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
「金融機関との場合」
| 金銭消費貸借契約 | 本則税率 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 |
参考:国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
住宅ローンの契約に対する金銭貸借消費契約書を結ぶ際、電子契約に対応する金融機関が増えているため、印紙が不要となるケースもあります。
登録免許税・登記費用、仲介手数料など
不動産を取得した場合の税金や手数料などの種類は多いため、それぞれ確認していきましょう。
| 費用項目 | 簡単な説明 | 目安金額(相場) |
| 登録免許税 | 登記にかかる国税(所有権移転、抵当権設定) | 不動産評価額や借入額 × 0.1~1.5%(軽減措置適用後) |
| 仲介手数料 | 不動産会社への報酬(仲介の場合) | 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税 (上限) |
| 不動産取得税 | 購入後に一度かかる都道府県税 | 不動産評価額 × 3%(軽減措置適用で減額・ゼロの場合あり) |
| 固定資産税等 精算金 | その年の税金の日割り負担分 | 物件による(年税額 ÷ 365 × 残日数) |
| 司法書士報酬 | 登記手続きの代行費用 | 5~15万円程度(登記内容による) |
登録免許税は、不動産の登記にかかる税金で、不動産の取得に関する「所有権移転」や住宅ローンの担保を設定する際の「抵当権設定」のタイミングで必要です。
抵当権設定の登録免許税は原則、住宅ローンの借入額の0.4%ですが、一定の要件を満たす場合は2027年3月31日取得分まで0.1%へ軽減されます。
なお、不動産の登記は専門的な知識が必要となるため、基本的に司法書士へ依頼することが一般的です。
司法書士へ依頼する際は報酬が必要となりますが、司法書士によって価格が大きく変わるため、比較検討しておくことをおすすめします。
火災保険・地震保険
住宅ローンを利用する場合、金融機関から「火災保険」への加入を融資の条件とされる場合が一般的でしょう。
万が一、火災や風災、水災、雪災など自然災害によって損害を受けた場合、修繕に掛かる費用の支払いなどでローンの返済が滞りかねないからです。
火災保険料は、建物の構造(木造か鉄筋コンクリートかなど)、所在地、補償内容、保険期間によって異なりますが、数十万円単位になることもあります。
なお、地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害は「火災保険」で補償されず、地震が多い日本では必ず地震保険の加入を検討しておきましょう。
保険料は建物構造と所在地で変動するため、複数社の見積もりを比較して必要な補償範囲を見極める必要があります。
団信(団体信用生命保険料)
住宅ローン契約者のほぼ大半が「団信」に加入します。
団信は生命保険の一種で、住宅ローンの返済期間中に契約者が死亡または所定の高度障害状態になると残りの住宅ローンが完済される仕組みです。
通常、保険料は住宅ローンの金利に含まれますが、がんや脳卒中、急性心筋梗塞などの3大疾病保障付きである場合、金利に0.1~0.3%程度上乗せされます。
その他の病気・ケガによる就業不能状態などを保障する団信もあり、既に加入している生命保険や医療保険などと照らし合わせた上で検討しましょう。
諸費用の支払いタイミングと方法

住宅ローンの諸費用には種類が多いものの、まとめて支払うわけではなく「住宅購入時」や「ローン契約」など、異なるタイミングで支払います。
基本的に自己資金で用意するのが望ましいですが、場合によっては住宅ローンに組み込んで借り入れるという選択肢も必要です。
諸費用の準備を計画的に進めておかないと、資金繰りに支障をきたす可能性もあるため、綿密に計画しておきましょう。
売買契約時~ローン実行時のフロー
住宅ローンの諸費用として、不動産の売買契約を結ぶ際の手付金や印紙税、仲介手数料などが必要です。
その後、住宅ローンの本審査申し込みを経て、ローン契約を結ぶ際に印紙税が掛かります。
さらに、金融機関への融資手数料や保証会社へのローン保証料、登記手続きのための登録免許税なども必要です。
その他、司法書士報酬、火災保険料・地震保険料の支払も発生します。
費用項目ごとに支払時期が分かれているため「いつまでに」「いくら必要」なのかをリストアップし、事前に金融機関や不動産会社に確認しておきましょう。
現金一括払い vs. ローン組み込みのメリット・デメリット
住宅ローンの諸費用の全てを自己資金で用意するのが理想ですが、手元資金に余裕がない場合もあるでしょう。
多くの金融機関では、諸費用の一部または全部を住宅ローンの借入額に含めて借りられるケースも増えています。
ローンに組み込むメリットとしては、現金の持ち出しを抑えられる点です。
手元資金を置いておけるため、引っ越し費用や家具・家電の購入費用に充てられます。
一方、デメリットとしては、ローンの金額が増えることによって利息負担が増えるため、総返済額が増加してしまう点です。
将来的に物件を売却する際にローン残高が売却価格を上回りやすく、追加の費用を自己資金で賄わなければならないリスクも考慮しなければなりません。
利息負担を避けるために諸費用は自己資金で支払うことが推奨されますが、手元資金とのバランスやメリット・デメリットを理解した上で判断しましょう。
諸費用を賢く節約するポイント

高額になりがちな住宅ローンの諸費用は、工夫次第では負担を軽減できる可能性があります。
印紙税や登録免許税のように法律で定められている税金は節約が難しいものの、手数料や保険料など、交渉によって下げられる費用もあるからです。
総支払額を少しでも抑えるためには、どの費用が節約できるかを比較検討することがポイントとなります。
住宅ローンの諸費用を賢く節約するための具体的なポイントを確認し、無理のない範囲で実践し、少しでも有利な条件でマイホームを実現していきましょう。
頭金を増やした手数料の圧縮方法
諸費用の中で大きな割合を占めるローン手数料やローン保証料は、基本的に住宅ローンの借入金額に応じて変動します。
つまり、借入金額が少なくなれば、手数料や保証料も安くなる可能性があるということです。
例えば、4,000万円の物件を購入する際に、頭金ゼロの場合と頭金800万円(物件価格の20%)を入れた場合を計算してみましょう。
ローン手数料が借入額の2.2%であった場合
⇒手数料だけで約17.6万円(800万円×2.2%)も節約できる計算になります
さらに、借入額が減ることで毎月の返済額や総利息負担も軽減されるという大きなメリットも期待できます。
とはいえ、諸費用や利息負担を減らしたいからといって、手元の預貯金を無理に頭金に充ててしまうことには注意が必要です。
病気やケガ、失業、子どもの教育費など、一般的には生活費の3ヶ月分から半年分程度の「生活防衛資金」も余力として残しておきましょう。
保険の内容を見直して無駄を省く
火災保険は、補償内容によって保険料を節約できる可能性が高い項目です。
例えば、自治体が公表しているハザードマップなどを参考に、洪水や土砂災害のリスクが低ければ「水災補償」を外す対応をしましょう。
また、建物だけでなく家財道具に対する補償も付帯できますが、所有している家財の評価額に見合った適切な補償額を設定することも大切です。
さらに、個人賠償責任特約や弁護士費用特約など、自動車保険や他の損害保険で既に加入している補償と重複していないかも確認しておきましょう。
万が一の際に十分な補償が受けられるよう、立地や建物の構造、家族構成などを考慮し、本当に必要な補償を見極める冷静な判断が求められます。
まとめ
住宅ローン契約時に必要となる諸費用は、複雑且つ高額になりがちです。
一般的に、諸費用は物件価格の3%〜10%程度が相場となると言われていますが、融資手数料、保証料、印紙税など多岐に渡るため分かりにくいでしょう。
基本的に現金で用意しておくべきですが、状況によってはローンに組み込むことも可能です。
ただし、そのメリット・デメリットをよく理解しておく必要があります。
また、ご自身の状況に合わせて具体的な諸費用額をシミュレーションし、自分にあったプランを見定めたうえで諸費用の支払を決めておくことが大切です。
最終は、検討中の金融機関や不動産会社へ相談し、詳細な見積もりを取得した上で、物件価格だけでなく諸費用も含めた総額で資金計画を立てておきましょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!