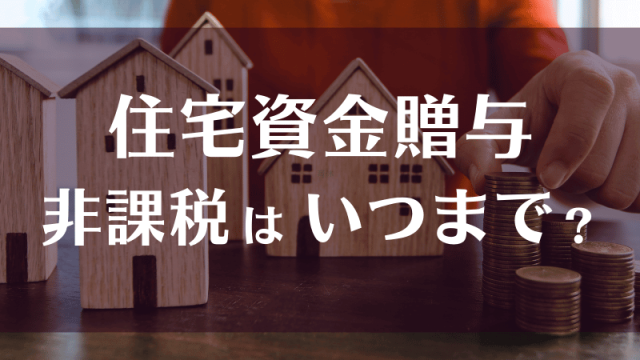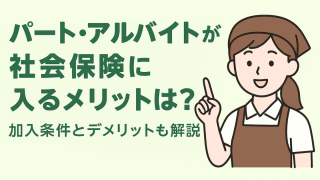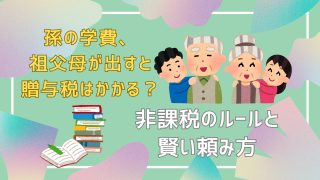「住宅ローンの返済を少なくしたい」「自分に合う返済方法を知りたい」そんなふうに考えていませんか?
住宅を購入するときに、住宅ローンを組むときの「頭金」をいくら用意すればよいか悩む人が多いのではないでしょうか。
頭金を用意するにしても、住宅を購入するころには出産や子どもの教育費などの支出がかさむため、頭金を貯めるのはそう簡単ではありません。
とはいえ、頭金があることで住宅ローンの審査や、ローンを組んだ後の返済負担が減るなどのメリットが多いのも事実です。
この記事では、頭金の基礎知識や金額の目安、住宅ローン審査のポイントまで幅広く解説します。
住宅ローンの頭金はいくらが相場?

住宅ローンの頭金は「いくら用意すればよいのか」と、相場が気になる方も多いでしょう。
中には「多ければ多いほどよい」と聞いたことがあるかもしれませんが、決してそうとも言い切れません。
新築物件や中古物件、さらには住まいのタイプや家族構成など、家計の状況によっても変わるため、相場を理解しつつ自分にあった金額の設定が大切です。
住宅ローンの頭金とは?役割と相場
住宅ローンの頭金とは、住宅を購入する時に現金で支払う金額を指します。
例えば、5,000万円の住宅物件に対し、住宅ローンを4,000万円で取り組む場合、頭金は1,000万円です。
なお、頭金には以下の役割があります。
- 住宅ローンの借入額を減らす
- 住宅ローンの審査を有利にする
借入額を減らすと、毎月の返済額や総返済額を抑えられるため、返済の負担が減ります。
また、頭金が多いと計画的に貯蓄ができる証明になり、金融機関からの信頼を得やすく、審査にプラスの影響を与えるでしょう。
なお、一般的には新築住宅で10〜20%を準備する人が多い一方、中古物件では幅広い結果が見られるなど、若干のばらつきがあります。
頭金の金額はどう決める?審査への影響と注意点

頭金は、返済額だけでなくローンの審査や金利が優遇されるかどうかも影響します。
借入金額が大きいと、審査で慎重に見られる傾向もあるため、頭金の割合など正しく理解することで、今後の審査を円滑に進められるでしょう。
ここでは、頭金の有無が審査にどのように影響するのか、また金利優遇と併せて注意すべき点を確認します。
頭金が多いほど審査は有利?金融機関の評価ポイント
頭金が多いと、住宅ローンの借入額が減らせるため、金融機関の審査が有利に働く可能性が高まります。
借入額が減ることによって、返済比率が抑えられるからです。
返済比率とは?
住宅ローンの年間返済額に対する、年収の割合です。以下の計算式で表せます。
(計算式)
「返済比率(%)=年間返済額÷年収×100」
金融機関では返済比率が低いことで安定して返してもらえると判断するため、極めて重要な項目です。
なお、返済比率を減らすには、収入を上げるか借り入れを減らすかの2択しかありません。
さらに、頭金が多いと、計画性があるとも判断されます。
ただし、闇雲に頭金を増やせば良いというわけでもなく、将来の支出や緊急時の対応もできるようにしておきましょう。
頭金の割合で金利は変わる?優遇金利の適用条件
頭金の比率が一定の水準を超えた場合、金融機関によっては、少しでも金利が下がる可能性もあります。
例えば、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する「フラット35」では、融資率が9割を超えた場合と下回った場合では金利が異なるからです。
他にも頭金が1〜2割以上で金利を優遇する場合もあるため、総返済額を減らせる可能性が高まります。
ただし、具体的な割合や優遇幅、住宅ローンの商品内容によって条件が異なるため、各ホームページや銀行の窓口で確認しておきましょう。
頭金が少ない場合の注意点とリスク対策
頭金を用意するメリットは多い一方、頭金が少ない、もしくは用意できない家計もあります。
その場合は審査が厳しくなる点に注意しておきましょう。
住宅ローンの審査では返済比率を見られますが、自身の収入だけで足りなければ収入を合算できるパートナーか、保証人を探さなければなりません。
また、返済比率以外にも担保評価に注意しておきましょう。
担保評価とは?
融資の際に銀行が不動産の価値を評価し、担保として適しているかどうかを判断することです。
なお、「担保」は融資を受ける際に、金融機関に対して返済不能などになった場合の返済を保証するために住宅ローンを借り入れる債務者が差し出すものを指します。
担保評価が低ければ、借入金額が減るか、他の担保物件を差し入れなければなりません。
最近では、頭金なしでローンを組めるという銀行も増えていますが、当然ながら審査があることを理解した上で検討していきましょう。
住宅ローン頭金の貯め方と無理のない資金計画

住宅ローンの頭金は、計画的に貯蓄することが大切です。
しかし、いくら計画しても十分に貯められない場合もあるため、家計の見直しや親族からの支援も含めると用意しやすいでしょう。
この項目では、具体的な方法や、ライフプランに応じた貯め方などを解説します。
家計見直しと具体的な貯蓄方法
計画的に貯蓄する場合、まずは毎月の支払を見直しましょう。
現状の収入と支出が把握できていないと「いつまでに」「いくら貯める」か、計画を立てられないからです。
例えば、以下の方法を見ていきましょう。
- 固定費の見直し
- 先取り貯金
- 積立預金
固定費は、通信費や光熱費、保険料など、割高なものから見直すことで、節約につながります。
次に、先取り貯金を取り入れましょう。
家計の多くが「収入-支出=貯蓄」であるのに対し「収入-貯蓄=支出」とすることで強制的に貯蓄に回す方法です。
また、先取りしたお金は、積立預金などすぐに使えないようにしておくことをおすすめします。
親からの贈与を受ける
住宅を購入する家計では、支出の見直しができていない家計も多く、資金が貯まりにくい場合もあります。
そこで、自力では限界がある場合、親族などからの援助を活用しましょう。
自身や配偶者の親から「住宅取得資金の贈与」による支援を受けることで、特例が適用できます。
「住宅取得資金の贈与に関する非課税の特例(令和6年~8年)概要」
| 項目 | 内容 |
| 適用期間 | 令和6年1月1日〜令和8年12月31日 |
| 非課税限度額 | ・省エネ等住宅:1,000万円まで ・その他住宅:500万円まで |
| 対象者の主な要件 | ・直系尊属(親・祖父母など)からの贈与 ・贈与年1月1日時点で18歳以上 ・合計所得金額が2,000万円以下 ・過去に本特例の適用を受けていない ・贈与の翌年3月15日までに居住、または居住見込みがあること ・日本国内に住所があること |
| 住宅の要件(新築・取得) | ・床面積が40㎡以上240㎡以下 ・床面積の2分の1以上が居住用 ・新築未使用、または耐震性等の基準を満たす中古住宅 |
| 住宅の要件(増改築) | ・床面積が40㎡以上240㎡以下で2分の1以上が居住用 ・工事費100万円以上 ・増改築等工事証明書などで証明が必要 |
ただし、上の図は概要であるため「住宅取得資金の贈与税非課税制度の詳細」は国税庁のWebサイトをご確認ください。
参考:国税庁|No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
ライフプランに合わせた頭金設定
住宅ローンを組むと、35年など長期間に渡ってローンの返済が続くことが多いでしょう。
そのため、住宅を購入した後に、子どもの教育費や車の購入、老後の資金も視野に入れておかなければなりません。
必要となる資金の洗い出しや、ライフプランに応じた収入の計画を立てることも大切です。
例えば、出費の大きい項目は以下の通りです。
- 出産
- 子どもの教育費
- 習い事
- マイカー購入
- 旅行
- 医療費
- 親の介護費用
- リフォーム
- 修繕費用など
老後までの資金計画を立てるには、自身だけでは限界もあるため、ファイナンシャルプランナーなどの専門家にも相談しながら、自分に合った頭金の額を決めましょう。
住宅ローン申請の流れと必要書類

頭金の基本が分かった上で、一番重要なのは「住宅ローンの審査が通るかどうか」です。
そのため、住宅ローンの審査の流れや、今後必要となる書類などを把握し、円滑に進められるようにしておきましょう。
住宅ローン事前審査(仮審査)の流れと注意点
住宅ローンの事前審査では、金融機関が申込者に「住宅ローンをいくらまで貸せるか」の目安を判断します。
基本的に事前審査から始まり、通過した後に本審査、契約の流れです。
それぞれ必要となる書類が異なるため、確認しておきましょう。
「事前審査の流れ」
1.申し込み
金融機関のWebサイトや窓口で行う
2.必要書類の提出
本人確認書類、収入証明書類、物件に関する書類を提出
3.審査
申込内容や提出された書類に基づいて金融機関にて審査
4.結果通知
通常、1日〜数日程度で審査結果が通知される
なお、事前審査に通ったからといって、必ず本審査が通るとは限りません。
最近では「Web申込」も増えており、審査にかかる期間が短いケースも増えています。
「すぐに結果が知りたい」「審査に不安な点がある」場合は、積極的に活用しましょう。
住宅ローン本審査の流れと注意点
事前審査が通ったら、次は本審査に進みます。
さらに多くの書類提出が求められるため、漏れなく準備しておくことが重要です。
「本審査の流れ」
1.申し込み
事前審査に通った金融機関へ申し込み
2.必要書類の提出
住民票、課税証明書、物件に関する詳細な書類、団体信用生命保険の申込書・告知書を提出
3.審査
金融機関が、提出された書類や信用情報、物件の担保評価などに基づいて、詳細な審査を行う
4.結果通知
1週間~数週間程度で審査結果が通知される
団体信用生命保険とは
住宅ローンの契約者が、死亡や高度障害になった場合、生命保険会社によって住宅ローンの残債が支払われる保険のことです
本審査では提出書類が増えるため、準備に時間がかかる可能性があります。
また、万が一書類に不備があると、審査が長引くことも考えられるでしょう。
なお、審査の途中に契約内容の変更や、健康状態に変化があった場合などは、融資が取り消される可能性もあります。
住宅ローン契約時の確認ポイント
本審査に通過したら、いよいよ住宅ローンの実行に向けて契約します。
その際は以下の点に注意しておきましょう。
「契約」
1.契約内容をしっかり確認する
不明な点や疑問点がある場合は、必ず金融機関の担当者に確認した上で契約する。
2.必要書類の提出
印鑑証明書、その他、金融機関が指定する書類を提出
3.実行
不動産の売買がある場合、銀行の応接室にて契約を結び、必要な資金が融資された上で必要な資金をそれぞれ振り込んで完了。
最近は、住宅ローンの契約をオンラインで行う「電子契約」が増えています。
電子契約にすると、書面の押印が不要なだけでなく、印紙税が不要になるなどメリットも多いため、積極的に活用しましょう。
まとめ
住宅の購入は、人生の中でも非常に大きな買い物であるため、住宅ローンも必然的に長期に渡る返済が続きます。
頭金を事前に用意しておくことで、住宅ローンが通りやすくなったり、場合によっては金利優遇を受けられたりするため、前もって計画しておくことが大切です。
とはいえ、住宅ローンを組む家計は、子どもの教育費や他のローンの取り組み、老後資金も見据えた資金計画を立てておかなければなりません。
今回、ご紹介した情報を参考に、頭金と住宅ローンについて理解を深め、自身に合った住宅購入プランを立ててください。
また、必要に応じて、FPなどの専門家にも相談しながら住宅購入を実現しましょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!