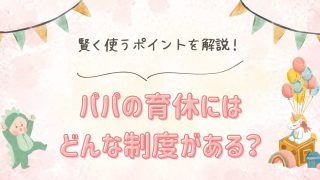長年連れ添った配偶者のために「自分の資産を遺しておきたい」と考える人は多いはずです。
中でも、自宅を生前贈与できる「おしどり贈与」は相続までに配偶者の住居を確保するための重要な選択肢の1つといえます。
とはいえ「本当に得なのか」「手続きは自分でできるのか」「費用はいくらかかるのか」といった不安がある方も多いのではないでしょうか。
ここでは、制度の基本的な概要からメリット・デメリット、さらには必要書類の詳細なども解説します。
この記事を最後まで読むことで、ご自身の状況で「おしどり贈与」を利用すべきかどうか判断ができるようになり、正しい選択ができるようになるでしょう。
おしどり贈与の基本を理解する

「おしどり贈与」とは「贈与税の配偶者控除」のことで、婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産などを贈与する際に、最大2,110万円までが非課税となる制度のことです。
この制度は配偶者の居住安定を目的としていますが、制度の趣旨や非課税枠の内訳を正しく理解しないまま手続きを進めると、対象外の贈与になりかねません。
控除が適用されないという事態を招く可能性もあるため、ここでは基本的な制度の趣旨や非課税額について解説していきます。
おしどり贈与の趣旨
おしどり贈与の正式名称は「贈与税の配偶者控除」です。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産またはその取得資金の贈与が行われた際に、基礎控除とは別に最大2,000万円の控除が適用される制度を指します。
配偶者の一方が亡くなった後、残された配偶者の生活基盤である住居を確保しやすくすることが趣旨です。
投資用不動産や事業用不動産、あるいは生活費としての現金の贈与は対象ではありません。
趣旨から外れた目的で制度を利用しようとすると、税務調査などで指摘を受け、控除が否認されてしまうリスクがあります。
制度の目的を正しく理解していないと適用を誤り、結果的に多額の税金を納めることになる可能性も否定できないため、趣旨を正しく理解しておきましょう。
おしどり贈与によって非課税になる金額
おしどり贈与では、贈与税の基礎控除110万円に加え、最大2,000万円の特別控除が適用されるため、合計で最大2,110万円までが非課税となります。
しかし、非課税を正しく理解していないと想定外の費用負担に繋がるため、以下の点に注意しましょう。
注意点①:非課税の対象は「贈与税」のみ
最も重要な点は、特例の対象となるのは「贈与税」だけです。
不動産の名義変更には、不動産取得税や登録免許税といった税金が別途発生します。
これらの費用は数十万円から百万円以上になることもあり、現金での準備が必要です。
「非課税」だからといって何も費用が掛からないというわけではないため、正しく理解しておかないと資金計画に大きく狂うリスクがあります。
注意点②:控除額は不動産の評価額が上限
2,110万円という非課税枠は、あくまで上限です。
例えば、贈与する不動産の評価額が1,800万円の場合、非課税となるのは1,800万円までとなります。
差額の310万円分を他の贈与に使えるわけではないため、その点は正しく理解しておきましょう。
おしどり贈与の適用要件

おしどり贈与の特例を受けるには、適用条件がいくつかあります。
「婚姻期間20年以上」「居住用不動産またはその取得資金であること」「贈与後に実際に居住すること」という3つの要件をすべて満たしておかなければなりません。
各条件を一つでも満たさなければ控除は適用されないため、仮に満たしていないと申告後に税務署から否認され、高額な納税義務が発生する可能性もあります。
要件①:婚姻期間が20年以上であること
おしどり贈与の要件の1つ目は、贈与が行われた時点で戸籍上の婚姻期間が20年以上であることが条件です。
そのため、入籍日から贈与日までの期間で計算され、1日でも足りなければ適用は認められません。
事実婚や内縁関係の期間は一切含まれず、たとえ25年間同居していても籍を入れてから19年しか経っていなければ、要件を満たさないため、注意しておきましょう。
一方で、過去に離婚し、同じ相手と再婚した場合は前後の婚姻期間を通算することも可能です。
とはいえ、期間計算を自己判断で誤ってしまうと、申告後に税務署から否認され、追徴課税が発生するリスクがあります。
正確な婚姻期間は戸籍謄本で確認する必要があり、思い込みで手続きを進めてしまうと、後で取り返しのつかない事態にならないようにしましょう。
要件②:居住用不動産またはその取得資金であること
贈与の対象となる財産は、受贈者(贈与を受ける配偶者)が自ら居住するための国内にある家屋やその敷地、またはそれらを取得するための金銭に限定されています。
居住用であることが絶対条件であるため、別荘や賃貸目的の投資用マンション、店舗兼住宅の店舗部分などは対象外です。
金銭を贈与する場合は、その資金が確実に居住用不動産の取得に充てられたことを証明する必要があります。
もし贈与された資金を別の用途に使ってしまった場合、控除の適用は認められません。
不動産の用途や資金使途に関する認識が相違していることで、制度の対象外であるにもかかわらず申告し、税務調査で指摘されるという場合もあります。
要件③:実際に居住し、住み続ける見込みがあること
贈与を受けた配偶者は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された不動産(または取得した不動産)に居住し、引き続き住み続ける見込みがあることが必要です。
住民票を移すだけでは不十分で、生活の実態が伴っていなければなりません。
例えば、贈与後すぐにその家を売却したり、賃貸に出したりする計画がある場合、要件を満たさないと判断される可能性が高いでしょう。
一時的な居住や形式的な手続きだけで済ませようとすると、控除の適用が取り消され、多額の贈与税と延滞税を課されるという厳しい結果を招く可能性もあります。
おしどり贈与のメリット

おしどり贈与には、贈与税の大幅な節税効果に加え、将来の相続財産を減らしたり、相続発生直前の贈与でも相続財産への持ち戻しが免除されたりするメリットがあります。
配偶者の居住を法的に確保できるだけでなく、将来の不動産売却時に税制上有利になる可能性も出てくるでしょう。
ただし、これらのメリットは全ての家庭が得られるわけではなく、財産状況によっては効果が限定的になりやすいため注意が必要です。
メリット①:贈与税を大幅に節税できる
おしどり贈与の最大のメリットは、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円、合計2,110万円までの贈与が非課税となる点です。
通常、2,110万円の財産を贈与した場合、多額の贈与税が発生しますが、この制度を使えばその負担をゼロにできます。
都心部などで高額な不動産を所有している場合、この節税効果は非常に大きいといえるでしょう。
しかし、あくまで贈与税に限定されており、不動産取得税や登録免許税といった他のコストが発生することを理解しておかなければなりません。
諸費用を考慮すると、全てがメリットとはいえないケースもあるため、贈与税の節税額だけで判断しないように気をつけておきましょう。
メリット②:相続税の課税対象財産を減らせる
生前に居住用不動産を配偶者に贈与しておくことで、贈与者の将来の相続財産を事前に減らせる点が大きなメリットです。
相続財産が減れば、相続税の基礎控除額を超えにくくなり、結果として相続税がかからなくなったり、税額が低くなったりする効果が期待できます。
(参考)
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
特に、相続財産が基礎控除を超えそうな場合には有効な手段となり得るでしょう。
メリット③:生前贈与加算の対象外になる
相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算する「生前贈与加算」の対象となります。
しかし、おしどり贈与の特別控除を適用した部分は対象外です。
令和5年度税制改正により、この期間は令和9年以降、段階的に7年まで延長されます。
万が一贈与後すぐに相続が発生してしまった場合でも、贈与した不動産が相続財産に加算されることはありません。
時間がない中での贈与となった場合でも、節税効果が維持されるという安心感があります。
ただし、控除額を超える部分や同一年に行った他の贈与については加算の対象となる可能性があるため、想定しない課税が生じるリスクに注意しておきましょう。
メリット④:配偶者の住居を確保できる
おしどり贈与を使って生前に自宅の名義を配偶者に移しておくことで、不動産を遺産分割の対象から外すことが可能です。
本来、相続が発生した場合、遺言書がなければ遺産は法定相続人全員による遺産分割協議で分け方を決めることになります。
自宅などの不動産が主な遺産であると、他の相続人から「家を売って現金で分けたい」という可能性もあり、配偶者が住み慣れた家を失いかねません。
そのため、おしどり贈与を活用することで、法的に配偶者の居住権が保護され、他の相続人の意向に左右されることなく安心して住み続けられます。
メリット⑤:3,000万円特別控除を2人分使える
将来的に自宅の売却を考えている場合、おしどり贈与を利用して自宅不動産の持ち分を配偶者に贈与しておくと「居住用財産の譲渡所得の特別控除」を最大6,000万円まで使えます。
「居住用財産の譲渡所得の特別控除」は、居住用財産を売却した際に譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという特例です。
そのため、1人当たり3,000万円、2人で最大6,000万円まで売却益を非課税にできます。
ただし、あくまで将来に売却する場合であり、適用には所有期間などの細かい要件を満たすことが重要です。
また、メリットだけを期待して共有名義にすることで手続きが煩雑になる場合もあるため、注意しておきましょう。
おしどり贈与のデメリットと注意点

おしどり贈与には、贈与税以外の不動産取得税や登録免許税といった高額な費用が発生する場合があります。
また、相続時に利用できる「配偶者の税額軽減」によって対応でき、おしどり贈与が不要となるケースも少なくありません。
ここでは、二次相続での税負担増など長期的なリスクも把握し、結果的に損をしないようにしておきましょう。
デメリット①:不動産取得税・登録免許税などの費用負担が大きい
おしどり贈与で贈与税が非課税になったとしても、不動産の名義変更に伴う税金は別途発生します。
例えば、不動産の固定資産税評価額に対して課される「登録免許税」「不動産取得税」です。
評価額2,000万円の不動産であれば、登録免許税だけで40万円、不動産取得税も数十万円の現金支出が必要になる可能性があります。
一方、相続で取得すると税率は大幅に軽減されるため、贈与は相続に比べて諸費用が高額になりがちです。
さらに、手続きを司法書士に依頼すればその報酬もかかります。
不動産ばかりではなく、他にかかる現金支出も考慮した上で取り組みを検討しましょう。
デメリット②:相続税の配偶者控除で十分な場合が多い
おしどり贈与を検討する際に、相続時に利用できる「配偶者の税額軽減」も選択肢として考えておかなければなりません。
相続が発生した際、配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額まで相続税がかからないからです。
日本の多くの家系では、相続財産の総額が1億6,000万円を超えることは少なく、おしどり贈与をしなくても相続時に非課税で自宅を引き継げるケースがほとんどです。
そのため、相続財産によっては、おしどり贈与を利用することで、支払わなくてもよかったはずの登録免許税などを負担する割りに節税効果がほぼないということもあるでしょう。
デメリット③:二次相続や先に亡くなるリスク
おしどり贈与は「二次相続」の問題を考慮しておかないと、将来的にリスクが高まる可能性があります。
例えば、贈与によって配偶者に財産が集中すると、その配偶者が亡くなった際に子供たちが負担する相続税が高額になりかねません。
一次相続だけでなく、二次相続まで考えておかないと、家族全体の税負担が結果的に増加するリスクもあるでしょう。
また、贈与を受けた配偶者が贈与者より先に亡くなってしまうと、結局その不動産は相続によって贈与者が負担します。
既に支払った登記費用などが全て無駄になってしまうというシナリオも想定しておく必要があります。
おしどり贈与の手続きと必要書類

おしどり贈与は、贈与税額がゼロであっても税務署への申告は法律で義務付けられており、これを怠ると特例が適用されません。
具体的には、以下の3ステップです。
ステップ①:贈与契約書を作成する
ステップ②:不動産の名義変更(贈与登記)をする
ステップ③:贈与税の申告をする(税額ゼロでも必須)
なお、各ステップで必要となる書類も多岐にわたるため、期限に間に合わなくならないよう事前に準備しておきましょう。
ステップ①:贈与契約書を作成する
おしどり贈与を行う上でまず進めるべきは、贈与者と受贈者の間で「贈与契約書」を作成することです。
「誰が」「誰に」「いつ」「どの不動産を贈与したか」という事実を証明するための法的な証拠書類となります。
口約束での贈与も法的には有効ですが、不動産登記や税務申告の際に客観的な証明書類として契約書は必須です。
なお、契約書には当事者の情報や不動産の詳細(所在、地番、家屋番号など)、贈与日を正確に記載しておかなければなりません。
記載内容に不備があると、登記手続きが滞ったり、税務署から贈与の事実を疑われたりする可能性があります。
契約書を自分で作成する場合、法的に有効な要件を満たしていないリスクがあるため、専門家へ相談することがおすすめです。
ステップ②:不動産の名義変更(贈与登記)をする
贈与契約を締結したら、該当する不動産を管轄する法務局で所有権移転登記の手続きを行います。
登記手続きを完了させて初めて、その不動産が法的に配偶者のものであることを第三者に対して主張できるようになるからです。
なお、申請するには、以下の書類を揃えておきましょう。
【不動産登記に必要な主な書類】
- 贈与契約書(登記原因証明情報)
- 登記済権利証または登記識別情報通知(贈与者)
- 印鑑証明書(贈与者・発行後3ヶ月以内)
- 住民票(受贈者)
- 固定資産評価証明書
書類収集や申請書の作成は非常に煩雑であり、不備があれば法務局で何度も修正を求められることになりかねません。
自力で行うにはハードルが高く、時間と労力がかかるだけでなく、手続きの遅延やミスが生じる可能性が高い内容といえます。
ステップ③:贈与税の申告をする
おしどり贈与の手続きで最も重要なのが、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署へ贈与税の申告を行うことです。
おしどり贈与は、申告をすることによって初めて適用が認められる「申告要件」があるからです。
なお、申告する際には以下の書類を準備しておきましょう。
【贈与税申告に必要な主な書類】
- 贈与税の申告書
- 受贈者の戸籍謄本または抄本(贈与日から10日経過後に作成されたもの)
- 受贈者の戸籍の附票の写し
- 贈与された不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書など、不動産の評価額がわかる書類
おしどり贈与では、計算上、贈与税額がゼロになる場合でも必ず申告手続きを行わなければなりません。
仮に、申告を忘れてしまうと、おしどり贈与の特例は適用されず、基礎控除110万円を超える部分に対して通常の高い税率で贈与税が課されます。
「税金が出ないから申告は不要だろう」という判断は最も陥りやすい致命的なミスであり、後から多額の追徴課税を受けないよう漏れなく申告しましょう。
よくある質問(Q&A)

おしどり贈与を検討する上で現金での贈与や離婚・別居といった特殊なケースでの適用可否など、様々な疑問が生じるでしょう。
万が一、誤った解釈のまま進めてしまうと、否認リスクや税金の問題が生じるため、陥りやすい点を回避できるよう最後まで見ていきましょう。
Q1. 現金での贈与は可能ですか?
- A.可能です。
ただし、その目的が「居住用不動産を取得するための資金」である場合に限られます。
単なる生活費の援助や、不動産購入以外の目的で現金を贈与しても、おしどり贈与の対象にはなりません。
なお、現金で贈与した場合、その資金が実際に不動産の購入代金として使われたことを証明するために、売買契約書や領収書などを申告時に添付する必要があります。
資金の使途が不明確な場合や、贈与された資金の一部が別の目的に流用された場合、控除が否認される可能性があるため、現金の場合は特に注意しておきましょう。
Q2. 離婚・再婚した場合は使えますか?
A.使えます。
婚姻期間20年の要件は、同一の配偶者との法律上の婚姻期間を通算して計算します。
例えば、15年間結婚した後に一度離婚し、数年後に同じ相手と再婚して5年以上が経過した場合、婚姻期間は合計で20年以上となるため要件を満たすことが可能です。
ただし、あくまで同一の配偶者との間の話であり、別の相手との婚姻期間は合算できません。
また、贈与の時点で法律上の婚姻関係にあることが前提であり、離婚が成立した後では制度を利用できないという点に注意が必要です。
Q3. 別居中でも適用できますか?
- A.法律上の婚姻関係が継続していれば、別居中であってもおしどり贈与の適用は可能です。
ただし、受贈者である配偶者が、贈与された不動産に「実際に居住し、その後も住み続ける見込みがある」という要件を満たす必要があります。
別居中の妻に自宅を贈与し、妻がその家に移り住むのであれば問題ありません。
しかし、贈与後も夫婦が別々の家で暮らし続けるような場合は、居住要件を満たさないと判断され、控除が認められない可能性が高くなるでしょう。
Q4. この制度はいつまで使えますか?
- A. おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の制度に期限は設けられていません。
ただし、日本の税制は毎年のように改正が行われており、控除額の縮小や要件の厳格化、制度自体が廃止される可能性はゼロではありません。
「いつか使おう」と考えていると、いざという時に制度がなくなってしまうというリスクも想定しておく必要があります。
Q5. 自分で手続きできますか?
- A. 贈与税の申告手続き自体を自分で行うことは不可能ではありません。
ただし、おしどり贈与の申告には多数の添付書類が必要であり、不動産の評価額の計算も伴います。
不動産登記の手続きは極めて専門性が高く、一般の方が自力で完璧に行うのは非常に困難です。
コストを抑えたいというニーズは理解できますが、手続きの不備で特例が受けられなくなれば、節約した費用の何十倍もの税金を支払うことになりかねません。
確実性を考慮すると税務申告は税理士、不動産登記は司法書士に依頼するのが賢明といえるでしょう。
まとめ
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、長年連れ添った配偶者の居住を安定させるための非常に有効な手段となり得ます。
特に、相続財産から自宅を外し、遺産分割トラブルを回避できる点は大きなメリットです。
しかし、この制度は最大2,110万円まで非課税という大きなメリットがある一方で、全ての家系にとって最適な選択肢とは限りません。
安易な判断は、かえって家族全体の資産を減らす結果を招く懸念があるため、メリットだけでなく、贈与税以外の費用負担や長期的なリスクを総合的に比較検討する必要があります。
なお、コストを考慮して自分で進めてしまうと、労力と時間が大幅に掛かってしまうため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!