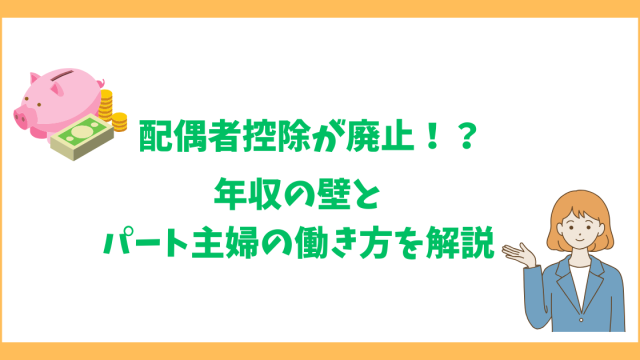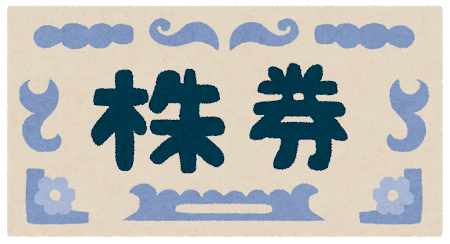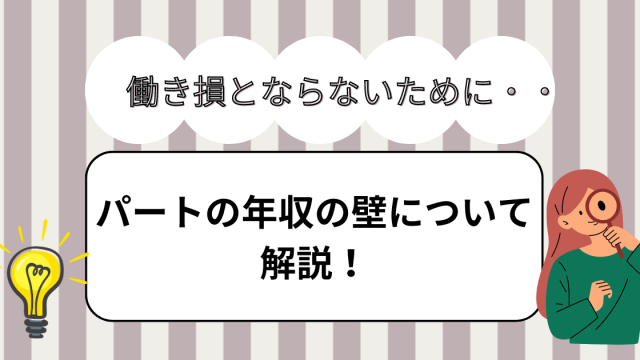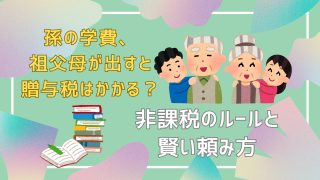「個人年金を受け取ったら税金は掛かる?」「確定申告って必要?」「何か対策はあるの?」このように考える人も多いのではないでしょうか?
将来の備えとして貯めてきた個人年金をいざ受け取ったとしても、税金に関する疑問や不安が浮かんでくる方が多いのが実情です。
この記事では、個人年金の受け取りを控えた方やすでに受け取りが始まっている方に向けて、税金の基本的な仕組みから具体的な計算方法、確定申告の要否までを解説します。
最後まで読めば、ご自身のケースで税金がいくらかかるのかを正確に把握でき、安心して適切な手続きを進められるようになるため、ぜひ確認しておきましょう。
個人年金保険にかかる税金の基本知識

最も基本的な知識として知っておきたいのは「個人年金に税金はかかるのか」という点ですが、結論として「個人年金は課税対象」となります。
支払った保険料の一部は「個人年金保険料控除」として所得から控除され、税負担が軽減されていたことで「税金の支払いを繰り延べていた」という考え方に基づくからです。
ただし、どのような税金がどのようにかかるかは、条件によって変わってきます。
ここでは、その基本となる3つのポイントをしっかり押さえましょう。
契約者と受取人の関係による税金の種類
個人年金にかかる税金の種類は「誰が保険料を払い(契約者)」「誰が年金を受け取るか(受取人)」という関係性によって、次の税金に区別されています。
- 所得税
- 贈与税
- 相続税
以下の早見表を確認し、掛かる税金の種類を把握しておきましょう。
| 契約者(保険料負担者) | 年金受取人 | かかる税金の種類 |
| 本人 | 本人 | 所得税 |
| 本人 | 配偶者や子など | 贈与税(初年度)+ 所得税(2年目以降) |
| 本人(死亡) | 配偶者や子など | 相続税 |
「自分で保険料を払い、自分で受け取る」ケースでは、所得税の対象です。
一方で、夫が保険料を払った保険を、妻が受け取るようなケースでは、夫から妻への「贈与」とみなされ、初年度に贈与税がかかります。
贈与税は所得税に比べて税率が高くなる場合があり、税負担が大きくなりがちです。
特別な理由がない限り、契約者と受取人は同一にしておくことが税負担を抑える最も重要なポイントと言えます。
一括受取と年金受取の税金の違い
所得税の対象となる場合、その課税方法は「受け取り方」によってさらに2種類に分かれます。
所得の種類が違うと、税額の計算方法や控除の仕組みが大きく異なるため、どちらが有利になるかは慎重な検討が必要です。
「年金形式」で毎年受け取る場合 :雑所得
公的年金などと同じ所得区分です。
毎年、他の所得と合算して税額を計算するため、所得が多い年は税負担が重くなる可能性があります。
「一括」でまとめて受け取る場合 :一時所得
生命保険の満期保険金などと同じ所得区分です。
税金の計算上、最大50万円の特別控除が適用され、さらに課税対象額が半分になるという大きなメリットがあります。
源泉徴収される場合とされない場合
会社員の方が給与から所得税を天引きされるように、個人年金も受け取る際に税金が天引き(源泉徴収)されるケースがあります。
年間の年金額から必要経費を差し引いた「雑所得」の金額が25万円以上となる場合、年金額の10.21%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されるのが一般的です。
ただし、源泉徴収はあくまで「仮払い」であり、医療費控除などの適用は考慮されていません。
そのため、確定申告をすることで払い過ぎた税金が還付される可能性があります。
源泉徴収されている場合でも、確定申告は自分にとって有利になるか検討しましょう。
【参考】保険料支払時の「個人年金保険料控除」とは?
年金受け取り時の税金を考える上で「個人年金保険料控除」も理解しておきましょう。
個人年金保険料控除とは、年間に支払った保険料のうち一定額を所得から差し引ける制度で、所得税や住民税の負担を軽減する効果があります。
控除を受けるためには「年金受取人が契約者またはその配偶者であること」「保険料の払込期間が10年以上であること」などの条件を満たさなければなりません。
個人年金の税金計算シミュレーション
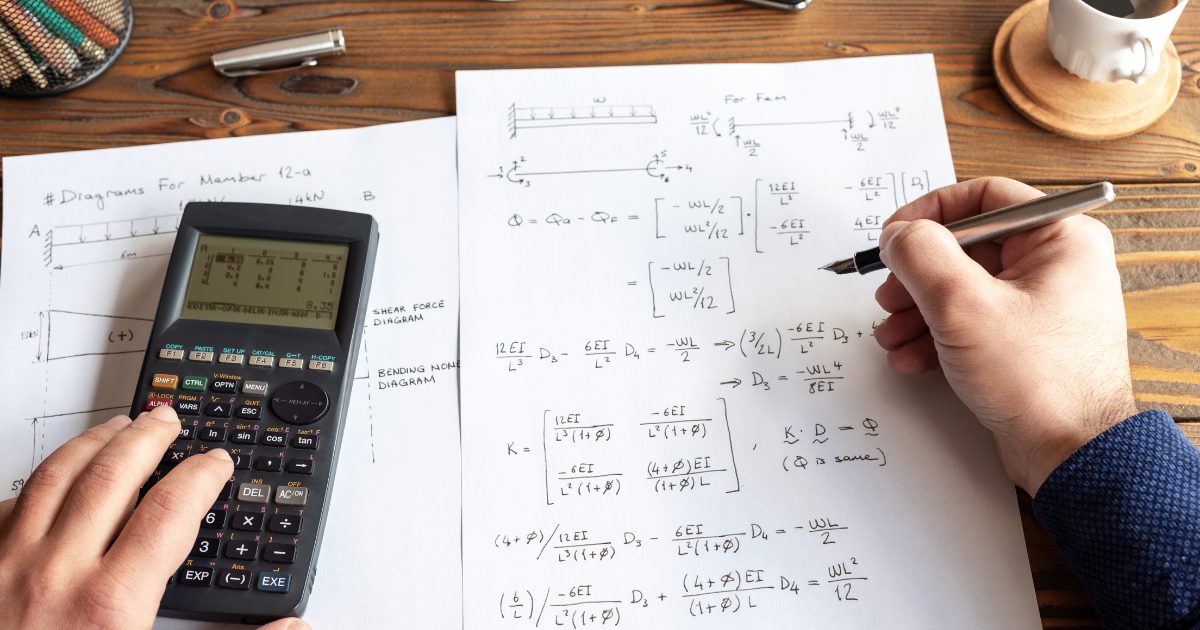
税金の仕組みが分かったとしても、実際にどれくらいの税金がかかるのかは気になるところです。
そこで、具体的な計算方法を見ていきましょう。
雑所得(年金受取)の計算方法
年金形式で毎年受け取る場合、以下の計算式で「雑所得」の金額を算出します。
計算のポイントは、支払った保険料のうち、その年の年金額に対応する部分を「必要経費」として差し引ける点です。
「計算式」
雑所得の金額 = 1年間の総収入金額 – 必要経費
総収入金額とは、その年に受け取る「基本年金」や「増額年金」の合計額です。
一方、必要経費とは、受け取る年金額に対応する支払った保険料のことで、以下の式で計算します。
「計算式」
必要経費 = その年の年金額 × (払込保険料の総額 ÷ 年金の総支給見込額)
「受け取る年金のうち、元本(自分が払った保険料)に当たる部分は経費として認めます」という意味です。
雑所得の金額が、他の所得(公的年金や給与など)と合算され、最終的な所得税額が決定されます。
一時所得(一括受取)の計算方法
年金を一括で受け取る場合、税制上有利な仕組みが取り入れられています。
特に「特別控除50万円」と「課税対象が1/2になる」という2点は非常に大きなメリットです。
「計算式」
一時所得の金額 = (一括受取額 – 払込保険料の総額 – 特別控除額最大50万円) × 1/2
受け取った金額から支払った保険料総額を差し引いて利益を計算します。
そこから最大50万円を無条件で差し引ける「特別控除」が適用されます。
さらに、残った金額を半分にしてから他の所得と合算するため、税負担が大幅に軽減される仕組みです。
利益が50万円以下であれば、この時点で一時所得は0円となり、税金はかかりません。
年金額別の具体的な税金シミュレーション
ここでは、具体的な税金シミュレーションを見ていきましょう。
シミュレーションを見ることで、ご自身のケースを当てはめて計算すると、掛かる税金が分かります。
- 払込保険料の総額:600万円
- 受取期間:10年確定年金
- 年間の受取額:70万円
- 年金の総支給見込額:700万円 (70万円 × 10年)
パターン別に見ていきましょう。
【パターンA:年金受取(雑所得)の場合】
- 必要経費を計算
70万円 × (600万円 ÷ 700万円) = 60万円 - 雑所得を計算
70万円 (総収入) – 60万円 (必要経費) = 10万円
このケースでは、雑所得は10万円です。
他の所得(給与所得や公的年金など)と合算して、最終的な所得税率を掛けて税額が決まります。
【パターンB:一括受取(一時所得)の場合】
一括受取額を700万円として計算します。
- 利益を計算
700万円 (一括受取額) – 600万円 (払込保険料) = 100万円 - 特別控除を適用
100万円 – 50万円 (特別控除) = 50万円 - 課税対象額を計算
50万円 × 1/2 = 25万円
このケースでは、課税対象となる一時所得は25万円です。
一見するとAの方が所得金額が少なく、税金が抑えられているように見えます。
しかし、Aは受け取る期間全てに税金が掛かるのに対し、Bは受け取った年だけに掛かる税金であるため、トータルとしてはAの税金の方が高くなります。
贈与税が発生する場合の計算
契約者(夫)と受取人(妻)が異なる場合、初年度に「贈与税」がかかります。
贈与税は、財産を無償で譲り受けた場合に発生する税金で、暦年課税という方式が一般的です。
贈与税の課税価格 = 年金受給権の評価額 – 基礎控除110万円
「年金受給権の評価額」とは、その年金を受け取る権利の金銭的な価値のことで、通常は解約返戻金の額などを基に算出されます。
評価額から年間110万円の基礎控除を差し引いた金額に対して、贈与税率を掛けて税額を計算します。
評価額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、個人年金の場合は超えるケースが多いため注意が必要です。
確定申告の必要性と手続き

税金の計算ができたら、次に必ず確認しておきたいのが「確定申告」です。
個人年金を受け取った場合、条件によっては確定申告が義務となりますが、自分は申告が必要なのか不要なのかを確認してみましょう。
確定申告が必要な人・不要な人
確定申告が必要になるかどうかの判断基準は、主に「所得の種類」と「金額」で決まります。
- 個人年金の雑所得が年間20万円を超える人
- 個人年金の一時所得が発生した人(利益が50万円を超えた場合など)
- 源泉徴収された税金の還付を受けたい人(医療費控除や生命保険料控除などを適用したい場合)
- 贈与税や相続税の申告が必要な人(所得税とは申告時期が異なる場合があります)
- 公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得(個人年金の雑所得など)が年間20万円以下の人
- 給与所得者で、給与以外の所得(個人年金の雑所得など)が年間20万円以下の人
- 個人年金の一時所得が0円またはマイナスになる人(利益が50万円以下の場合など)
ただし、上記は所得税の確定申告が不要なケースであり、住民税の申告は別途必要になる場合があります。
住まいの市区町村役場に必ず確認しておきましょう。
仮に、失念したり怠ったりすると、翌年の住民税や国民健康保険料の算定に影響が出ることがあるため注意が必要です。
申告を忘れた場合のリスクとペナルティ
確定申告が必要であるにもかかわらず手続きを忘れてしまうと「申告漏れ」となります。
本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとして以下の追徴課税が発生する可能性があるため、気を付けておかなければなりません。
- 無申告加算税:原則15%(50万円を超える部分は20%)、調査前に自主申告すれば5%に軽減
- 延滞税:税金の納付が遅れた期間に応じて発生。年率は2025年現在最大8.7%
- 重加算税:仮装・隠蔽等の悪質な場合は35~40%(場合によって50%や加重も)、刑事罰や財産差押もあり得る
意図的でなくても、申告漏れはペナルティの対象です。
保険会社から税務署へは支払情報が共有されているため「申告しなくてもバレない」ということはありません。
必ず期限内に手続きを済ませておきましょう。
確定申告の手続きと必要書類
確定申告は、原則として所得が発生した翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。
手続きには以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 個人年金の支払調書: 毎年1月頃に保険会社から郵送される「年間の支払額」「源泉徴収税額」が記載された書類
- 各種控除証明書: 医療費の領収書、生命保険料控除証明書、社会保険料控除証明書など
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
現在は国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、自宅のパソコンやスマートフォンからでも申告が可能です。
画面の案内に従って入力するだけで税額が自動計算されるため、税務署に行く時間がない方でも安心して利用できます。
よくある質問

最後に、個人年金の税金に関するよくある質問とその回答をまとめました。
多くの方が疑問に思うポイントですので、ぜひ参考にしてください。
Q. 個人年金はいくらまで非課税?
個人年金そのものに「いくらまで非課税」という明確な非課税枠はありません。
ただし、所得税の確定申告においては「公的年金や給与以外の所得(個人年金の雑所得など)が合計で年間20万円以下」であれば確定申告が不要になる制度があります。
「年間20万円」という金額が、実質的な非課税ラインのひとつの目安として広く認識されていますが、あくまでも所得税の話であり、住民税の申告は必要です。
Q. 一括と年金どちらが税金的に有利?
税金の計算方法だけを見ると、一時所得として扱われる「一括受取」の方が有利になるケースが多いでしょう。
最大50万円の特別控除があり、さらに課税対象額が半分になるという税制上のメリットが大きいからです。
ただし、一般的に受け取れる保険金の総額は「年金受取」の方が多く設定されているため、税金の有利不利だけで決める人は少ないと言えるでしょう。
手元に残る総額や、ご自身のライフプラン(まとまった資金が必要か、継続的な収入が欲しいか)を考慮して総合的に判断することが大切です。
Q. 確定申告しないとバレる?
はい、税務署に把握される可能性は極めて高いと言えます。
生命保険会社は、誰にいくら個人年金を支払ったかを記載した「支払調書」を税務署に提出することが法律で義務付けられているからです。
税務署はこの支払調書と全国民の申告内容をデータで照合できるため、無申告や申告内容の誤りは高い確率で発覚します。
ペナルティを避けるためにも、正しく申告することが賢明です。
Q. 個人年金の税金を抑える方法は?
最も基本的で効果的な方法は「契約者と年金受取人を同一にする」ことです。
税率の高い贈与税の発生を確実に避けられます。
年金を受け取る際には、医療費控除、配偶者控除、生命保険料控除など、適用できる所得控除を漏れなく申告することで節税が可能です。
なお、他の所得が少ない年に受け取りを開始するなど、受け取り時期を調整することも有効な場合があります。
Q. 年金受取中に死亡したら税金は?
年金の残りの期間を受け取る権利(年金受給権)が、相続財産とみなされます。
注意すべきは生命保険の死亡保険金に適用される「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が、この年金受給権には適用されないという点です。
他の相続財産と合算して相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要になります。
契約形態によって課税関係が複雑に変わるため、専門家への相談もご検討ください。
まとめ
今回は、個人年金にかかる税金について、仕組みから計算方法、確定申告までを網羅的に解説しました。
「税金」と聞くと複雑で難しく感じられたかもしれませんが、ポイントを押さえておくことが大切です。
- 契約者と受取人は「自分自身」にすることが、税負担を抑えるためには重要
- 「一時所得」を選択することで一括受取は税制上のメリットが受けられる
- 「年間20万円」の壁により、 個人年金の利益(雑所得)がこの金額を超えるかどうかで、確定申告の必要性が出てくる
- 申告漏れのリスクを理解し、正しく手続きすることでペナルティが避けられる
個人年金は、将来に自分の資産を受け取るための重要な選択肢の一つです。
仕組みを正しく知ると、使える控除も変わってくるため、少しでも税金を抑えて受け取ることが可能です。
万が一、自分では難しいと感じたら、早めにFPや税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!