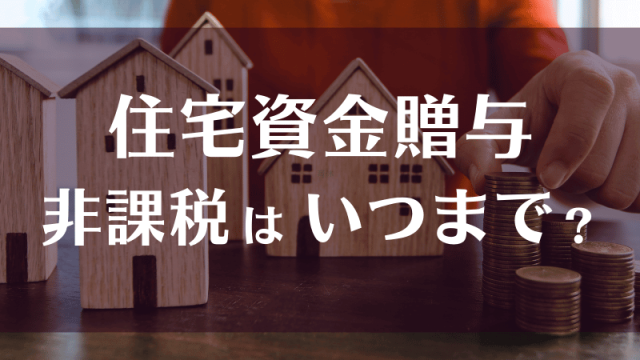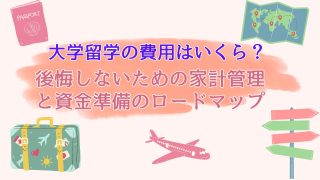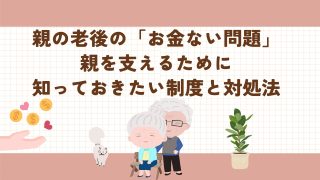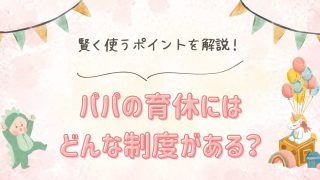実家を相続したけど「空きやってこんなに税金がかかるの?」「そもそも管理って何をすればいいの?」「このまま持ち続けようか迷う」こうした不安をかかえていませんか?
ただでさえ税金がかかる空き家ですが、管理を怠った空き家の固定資産税は最大で現在の6倍まで跳ね上がる可能性も否定できません。
ただし、2023年12月の法改正により新設された「管理不全空き家」制度によって、適切な対応を取れば税金が上がらずに済みます。
この記事では、空き家の固定資産税が「6倍になる」仕組みから実践的な対策まで、わかりやすく網羅的に解説します。
最後まで読めば、今すぐ取るべき行動が明確になるとともに、大切な資産を守る具体的な方法も見つかるでしょう。
【2023年法改正】空き家の固定資産税がなぜ6倍になるのか
 「空き家の固定資産税が6倍になる」と言われていますが、実は税金が加算されるわけではありません。
「空き家の固定資産税が6倍になる」と言われていますが、実は税金が加算されるわけではありません。
住宅が建つ土地の固定資産税は本来「住宅用地特例」という軽減措置があり、最大6分の1まで軽減されています。
2023年12月の法改正で、新たに「管理不全空き家」という区分が設けられましたが、管理状態の悪い空き家はこの特例の対象外となりました。
その結果、軽減されていた土地の税額が「約6倍」に戻る仕組みです。
たとえば、土地の評価額が1,200万円の場合、特例適用時の税額は年間約4万円になります。
しかし、特例が解除されると約24万円に上がり、計算すると「6倍」の差ということです。
重要なのは、この増額は建物ではなく土地の税金のみが対象であり、適切に管理していれば特例は維持できます。
空き家の固定資産税が6倍になる「管理不全空き家」とは?
 「管理不全空き家」とは、適切に管理されておらず、このまま放置すれば「特定空き家」に指定されるおそれのある空き家のことです。
「管理不全空き家」とは、適切に管理されておらず、このまま放置すれば「特定空き家」に指定されるおそれのある空き家のことです。
2023年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」で新設された空き家の区分のことを指します。
指定される基準は主に3つで「倒壊のおそれ」「衛生上の問題」「景観の悪化」のいずれかに該当すると指導の対象です。
1.倒壊のおそれがある
建物が倒壊するかどうかのリスクは、構造部分の深刻な損傷によって判断されます。
倒壊リスクは、第三者へ危害を及ぼすかどうかという公共の安全に直結する重大な問題です。
具体的な危険の兆候としては以下の内容が挙げられます。
- 基礎に深い亀裂が入っている
- 家全体が明らかに傾いている
- 柱の腐食やシロアリ被害が進行している
- 屋根の大規模な破損や継続的な雨漏りが発生している
これらの症状は、建築の専門知識がなくても目視で確認できる重要なチェックポイントです。
2.不衛生で周辺住民に悪影響を及ぼす
衛生状態が悪化すると、所有者の敷地内だけの問題ではなく、周辺地域全体の生活環境に深刻な影響を与える問題です。
衛生状態に問題が発生した場合、近隣住民からの苦情だけでなく行政への通報など、指導の直接的なきっかけとなりかねません。
たとえば、ゴミが散乱してカラスやネズミが集まっている、庭の雑草が原因で害虫が増えた、庭木が隣家の敷地や公道に大きくはみ出して通行を妨げているなどです。
これらは空き家の管理放棄を示す明確なサインと見なされます。
3.景観を著しく損ねる
景観の悪化は主観的な観点ではなく、地域全体の資産価値や住環境の質に影響を与えるかどうかで評価されます。
行政にとって、美しい街並みの維持が地域コミュニティ全体の価値につながるからです。
具体的には以下の状況が考えられます。
- 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている
- 外壁が広範囲にわたって剥がれ落ち下地がむき出しになっている
- 不適切な落書きや看板が多数設置されている
- 建物全体がツタなどの植物に覆われた廃墟のような外観
これらは地域の印象を大きく損ねる要因として問題視されます。
空き家の固定資産税が6倍になるまでの流れ
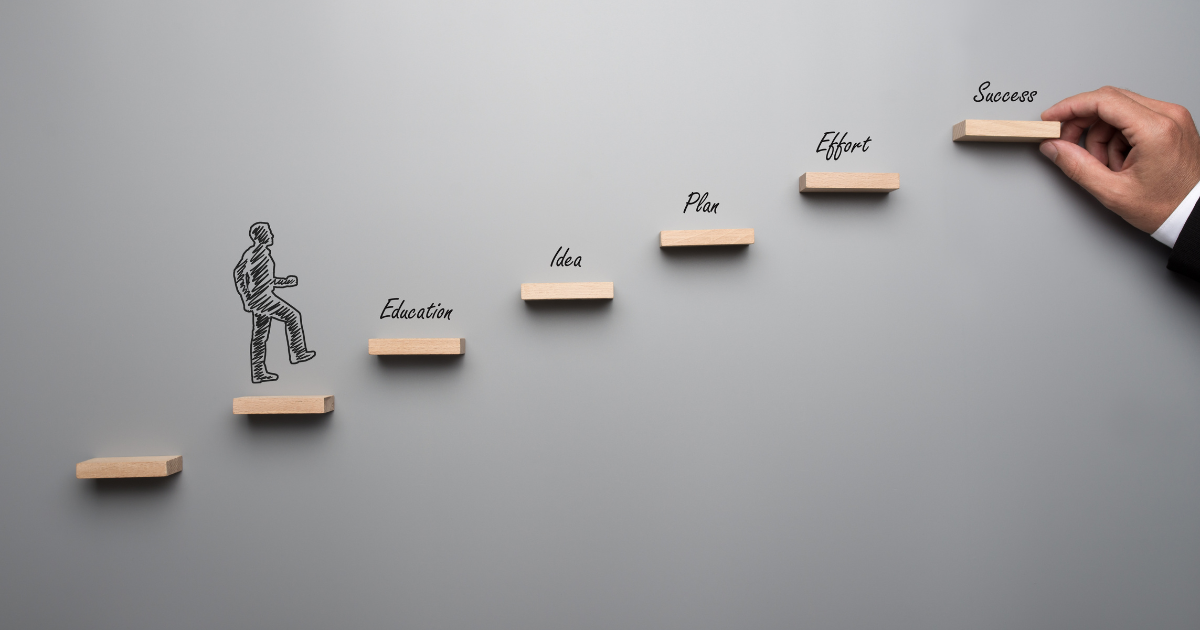 空き家の固定資産税が増額されるプロセスは、法律に基づき段階的に進められます。
空き家の固定資産税が増額されるプロセスは、法律に基づき段階的に進められます。
突如として税額が変わるわけではなく、所有者には4つの段階で改善の機会が与えられる仕組みです。
この章では「調査・判断」「助言・指導」「勧告」「課税」の各段階で、税額の増加を回避できる方法を解説していきましょう。
1.調査・判断
空き家の調査は、主に近隣住民からの情報提供や自治体職員による定期巡回によって開始されます。
この段階では、所有者が気づかないうちに手続きが進んでいる可能性があるため、注意が必要です。
調査のきっかけは「屋根瓦が落ちそうで危険」「庭の草木が道路にはみ出している」「異臭がする」など近隣住民からの通報がきっかけとなるでしょう。
自治体は空き家等対策特別措置法に基づき、空き家を危険な状態で放置しない責務を負っているため、通報には迅速に対応します。
2.助言・指導
調査の結果、管理状態に問題があると判断された場合、自治体は所有者に対して書面による助言・指導を行います。
所有者に自主的な改善の機会を提供する最初の公式なアプローチです。
通知書には「屋根の破損について修繕してください」「敷地内の雑草を除去してください」といった具体的な指摘内容と、期限が明記されています。
通知を受け取った場合は決して無視することなく、真摯に対処していきましょう。
3.勧告
勧告は、助言・指導に従わない所有者に対して行われる法的な手続きで、改善を促す指導とは性質が異なり、住宅用地特例解除の最終通告です。
所有者が改善の意思を示さないと自治体が判断した場合、空き家は「管理不全空き家」として認定されます。
勧告が出されると、その敷地は住宅用地特例の適用対象から除外され、翌年度から土地部分の固定資産税が最大で約6倍まで増額されるという仕組みです。
勧告は極めて重い行政措置ですが、通知に記載された期限内に指摘事項を改善し、自治体に報告すれば、勧告の解除を求められます。
増税を回避する最後の機会となるため、迅速かつ確実な対応が求められるでしょう。
4.課税
勧告を受けてもなお状況を改善しなかった場合、翌年度から実際に増額された固定資産税が課税されます。
翌年度から増額される理由としては、固定資産税が毎年1月1日時点の不動産状況で税額を決定するためです。
春頃に届く納税通知書には、住宅用地特例が適用されない土地として計算された税額、つまり6倍相当の金額が記載されます。
とはいえ、この段階でも状況を改善して自治体の確認を受けることで、翌年度以降に特例の適用を復活させることも可能です。
空き家の固定資産税を6倍にしないための対策
 空き家の固定資産税増額リスクは、適切な対策を講じることで確実に回避できます。
空き家の固定資産税増額リスクは、適切な対策を講じることで確実に回避できます。
基本的な対策としては、管理不全空き家に指定されないよう定期的な建物管理を継続する方法です。
たとえば、建物の老朽化が著しい場合は、解体して更地にするという選択肢も考えられます。
また、自治体独自の減免・特例措置を活用して税負担を軽減する方法も検討すべきでしょう。
どの対策が最適かは、建物の状態、立地条件、所有者の経済状況、将来の活用予定などによって変わってきます。
特定空き家に指定されないよう適切に管理する
固定資産税の増額を避けるためには、管理不全空き家に指定されないよう適切な管理を継続していくことが求められます。
適切に管理することで、近隣住民から苦情が出ない状態を維持するためです。
具体的な管理として、定期的に清掃・草刈りを行い、周辺環境を保つことが挙げられます。
また、建物の修繕(屋根・外壁・窓ガラスの補修)を行い倒壊リスクを防ぐことも必要です。
自身で管理が困難な場合、地域のシルバー人材センターの活用や空き家管理サービスの利用、親族や知人への管理委託なども検討しましょう。
いずれにせよ、近隣から通報されないよう「見た目の管理状態」を維持することが重要です。
解体して滅失届を提出する
建物の老朽化によって継続的な管理が困難な場合、解体による更地化も選択肢の一つです。
解体を実行すると住宅用地特例が適用されず、翌年度から固定資産税は更地価格で計算されるため税額が増えます。
倒壊寸前の建物を放置して特定空き家に指定されるリスクや継続的な管理費用を考慮すれば、解体の方が長期的には経済的負担を軽減できる場合もあるでしょう。
解体を実行する場合の重要な手続きとしては、建物解体後1ヶ月以内に法務局への建物滅失登記申請を出すことです。
手続きを失念すると、登記上は建物が存在し続けるため、存在しない建物に対する固定資産税が課税され続けるという問題が発生します。
解体費用や解体後の税額、管理継続費用、売却可能性などを総合的にシミュレーションし、最適な判断を行うことが重要です。
減免・特例措置を活用する
自治体によっては「解体後一定期間は固定資産税を軽減」する制度があります。
たとえば、老朽化した空き家の解体後に土地の固定資産税を一定期間軽減する特例や災害により家屋が使用不能になった場合の減免措置などです。
これらの措置は自治体HPや窓口で最新の減免制度を確認することが重要です。
まずは空き家が所在する市区町村の公式ホームページで関連情報を確認し、不明な点があれば固定資産税の担当窓口に直接問い合わせてみましょう。
また、空き家対策を検討する際は、管理継続・解体・減免措置だけでなく、売却や賃貸という選択肢も含めて総合的に判断することが重要です。
売却や賃貸を選択する際には、状態の良さや立地条件なども考慮した上で検討しましょう。
空き家の固定資産税が6倍になってしまったらどうする?
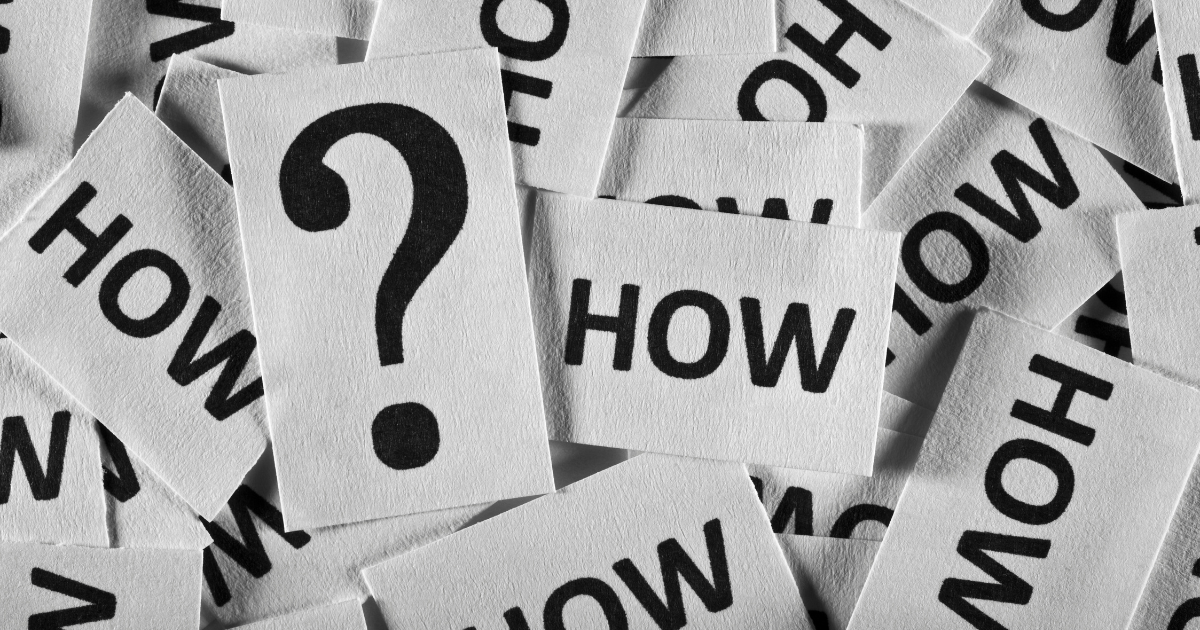 管理不全空き家に指定され固定資産税が増額してしまった場合でも、指定解除を申請し、税負担を元の水準に戻すことが可能です。
管理不全空き家に指定され固定資産税が増額してしまった場合でも、指定解除を申請し、税負担を元の水準に戻すことが可能です。
元の水準に戻すためには、3つのステップを進めていく必要があります。
まずは自治体からの勧告内容を具体的に把握し、次に指摘箇所の修繕・清掃・解体などの実施、最後は完了後に自治体に報告して指定解除を申請することです。
各ステップを適切に実行すれば、翌年度から住宅用地特例の適用を復活させられます。
STEP1:勧告内容を確認し、改善点を把握する
まずは、自治体からの「勧告書」に具体的な指示事項が記載されているため、正確に把握しましょう。
勧告書は行政と所有者の間で改善すべき点を明確にするための公式な文書であり、その内容に沿って対応することが指定解除への最も確実な方法です。
「建物南側外壁の剥離箇所を補修すること」「敷地内雑草を除去し、越境している庭木を剪定すること」といった具体的な指示が記載されています。
内容に目を通したら、放置せずに期限内に対応計画を立てることが重要です。
仮に、内容が理解できない場合や技術的な判断が必要な場合は、記載されている自治体の担当部署に問い合わせて詳細を確認しましょう。
STEP2:修繕・清掃・解体などで改善を実施する
改善点が明確になったら、勧告書の内容に基づいて具体的な改善作業に着手します。
ポイントとしては、建物の修繕、敷地内の除草・清掃、害虫対策などですが、倒壊リスクが高い場合は解体も選択肢となるため、建物の状態によって判断しましょう。
なお、作業を行う前に必ず「指摘された箇所については過程を詳細に記録として残すこと」がポイントです。
作業の記録は、後の報告段階で改善履行を客観的に証明する重要な証拠となるため、必ず記録しておきましょう。
基本的には、勧告書の指摘事項に従い、一つひとつの項目を丁寧に完了させますが、自力での作業が困難な場合は、専門業者に依頼することも可能です。
STEP3:自治体に報告・確認し、指定解除を申請する
改善作業が完了したら、その後は役所に報告し、現地確認を受けましょう。
改善が認められれば「特定空き家」指定が解除されます。
自治体が自発的に状況を確認するわけではないため、指定を解除したい場合は必ず所有者からの申請が必要です。
申請後は、職員による現地確認が実施され、指摘事項を適切に改善していることが認められれば正式に指定は解除されます。
指定が解除されると住宅用地特例が復活し、翌年度の固定資産税から軽減が反映されます。
最終的な報告・申請手続きを確実に実行しなければ住宅用地特例が復活しないため、確実に実行していくことが重要です。
空き家の固定資産税に関するよくある質問
 空き家の固定資産税については、覚えておくべきポイントがいくつもあるため、ここでは特に疑問が多い点について解説します。
空き家の固定資産税については、覚えておくべきポイントがいくつもあるため、ここでは特に疑問が多い点について解説します。
- 制度の全国統一性と自治体による運用の違い
- 税額増加の対象範囲
- 指定解除の可能性
- 解体による税額への影響
疑問を正しく理解することで、自身の状況に最も適した対策を選択できるでしょう。
空き家の固定資産税が6倍は全国共通?自治体差はある?
住宅用地特例が解除されて税額が最大「6倍相当になる仕組み」は全国共通です。
ただし「勧告」までの運用や減免措置は自治体ごとに異なるため、必ず確認しておきましょう。
たとえば、空き家の調査頻度や判定基準の厳格さ、指導から勧告への移行期間、所有者への支援制度の充実度などです。
そのため、ある市では空き家解体費用に対する補助金制度を設けている一方で、別の市では特段の支援策がないといったケースもあります。
基本的には税制の仕組みが同じでも、実際の対応や利用できる支援制度が異なるため、最新情報は市区町村の窓口や公式HPで確認が必要です。
6倍になるのは土地だけ?建物はどうなる?
固定資産税が6倍相当になるのは「土地部分」の固定資産税のみです。
建物の固定資産税は、建物の構造や築年数、劣化状況など毎年算出されるため、管理不全空き家だからといって評価や税率が変わることはありません。
勘違いして「家屋が6倍」と思う人が多いため注意が必要ですが、納税通知書を確認すると土地と家屋(建物)の税額が明確に分けて記載されていることが分かります。
特定空き家指定は解除できる?
特定空き家に指定された場合でも、自治体からの指導・勧告後に修繕・清掃・解体など是正することによって解除は可能です。
指定が解除されれば、翌年度から住宅用地特例が再び適用され、固定資産税の負担も元の水準に戻ります。
重要なのは、改善への取り組みを所有者自身が主体的に行い、その結果を適切に自治体に報告することです。
何から始めるべきか判断に迷う場合は、自治体の担当者と相談することをおすすめします。
解体すると本当に安くなる?逆に高くなるケースは?
「空き家を解体すれば固定資産税が安くなる」と考えがちですが、一般的には解体によって税額が上昇します。
建物を解体して更地にすると、土地に適用されていた住宅用地特例(税額を最大6分の1に軽減)が解除されるためです。
ただし「特定空き家」に指定された場合であれば、土地のみの方が税負担も小さいケースはあります。
そのため、解体+税額増を含めてシミュレーションし、売却・活用と比較すべきでしょう。
単独での判断が困難な場合は、税理士や不動産の専門家に相談しながら、最も合理的な選択肢を検討することが大切です。
まとめ丨空き家の固定資産税を6倍にしない対策を今日から始めよう
空き家の固定資産税が6倍になるのは、住宅用地特例の解除によるものであり、適切な知識と対策によって確実に回避できます。
空き家の状態にもよりますが、定期的な管理継続、老朽化が進んだ場合の計画的な解体、売却や活用による方法などは多岐に渡るため、状況に応じた対策が必要です。
とはいえ、何から手を付けて良いか分からない方も多く、その場合は自治体の担当窓口への相談、専門家への依頼、家族との話し合いを進めていきましょう。
相続した大切な資産を守り、将来の不安を解消するためにも、ぜひすぐにでも行動してください。
適切な対策により、空き家は価値ある資産として維持・活用することが可能となるでしょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!