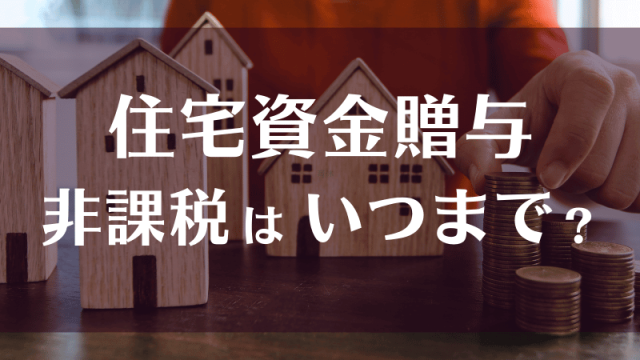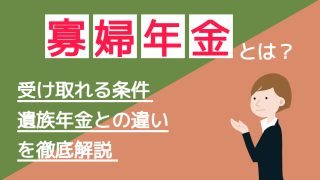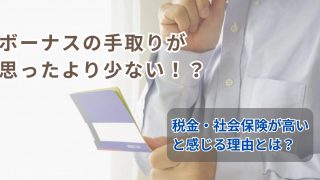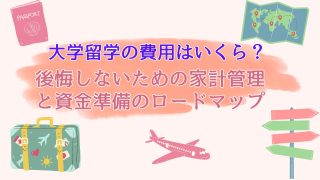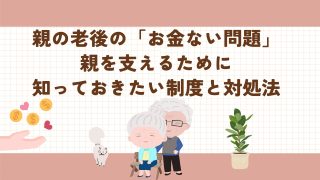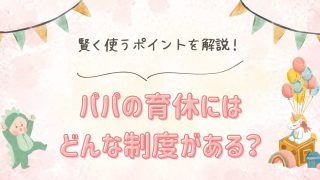「父が亡くなり、遺言書で兄が全財産を相続することになったけど、自分は何ももらえないの?」
「兄弟姉妹にも遺産を受け取る権利があるのかよく分からない」など、相続が発生すると疑問や不安を抱える方は少なくありません。
遺言書の内容に従わなければならないと考え何も行動しなければ、本来受け取れるはずの財産を失ってしまう可能性もあります。
しかし、多くの人が「遺言書があれば従うしかない」と諦めてしまっているのが現状です。
実は、遺言書がある場合でも、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。
ただし「法定相続分」と「遺留分」は全く異なる概念であり、正しく理解しなければ請求できません。
また、兄弟姉妹には遺留分が認められない、遺留分の請求には1年という期限があり、知らずに放置すると権利を失うなどの注意点もあります。
この記事では、法定相続分と遺留分の違いを明確にし、具体的な計算方法や遺留分侵害額請求の手続きまで、わかりやすく解説します。
自分のケースではどうなるのか、最後までこの記事を読めば理解できるでしょう。
法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分の「目安」となる割合のことです。
故人が遺言書を残さずに亡くなった場合に「誰が」「どのくらい」財産を引き継ぐのかという基準を示すためにあります。
ただし、この割合は絶対的なものではなく、強制力はありません。
例えば、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていれば、法定相続分の規定にかかわらず、遺言書の内容が優先されます。
また、遺言書がない場合でも、相続人全員が話し合って合意する「遺産分割協議」を行うことで、法定相続分とは異なる割合で自由に財産を分けられます。
「母の老後の生活資金として、配偶者の取り分を多くしよう」といった柔軟な分割も可能です。
法定相続分が適用される相続人は、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹と定められていますが、誰が相続人になるかには優先順位があります。
法定相続分はあくまで「遺言書がなく、相続人間の話し合いもまとまらない場合の最終的な拠り所となる基準」と理解しておくとよいでしょう。
遺留分とは

遺留分とは、遺言書の内容よりも強制力のある、法律で保障された「最低限の権利」です。
この制度の目的は、故人の財産形成に貢献してきたと考えられる家族の生活を保障し、相続における著しい不公平を防ぐことにあります。
例えば、遺言書に「全財産を愛人に譲る」「お世話になった隣人にすべて寄付する」といった極端な内容が書かれていたとしても、遺留分を持つ相続人は最低限の財産を取り戻すことが可能です。
ただし、権利が認められるのは配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)のみで、兄弟姉妹にはこの遺留分が一切認められていません。
遺留分は、遺言書を上回る強い権利ですが、自動的にもらえるわけではなく、自ら「請求」して初めて効力を発揮します。
また、遺留分を請求するルールが、2019年7月1日の民法改正で大きく変わっています。
旧制度(遺留分減殺請求)では、不動産など「財産そのもの」を取り戻すのが原則であったため、一つの不動産を複数人で共有する状態が生まれ、かえって新たなトラブルの原因となることがありました。
新制度(遺留分侵害額請求)では、請求方法が「お金(金銭)」での支払いに一本化され、金銭で解決できるようになりました。
法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分は、どちらも相続における取り分に関する概念です。
ただし、いくつか異なる点があるため、それぞれのポイントを見ていきましょう。
権利者と範囲の違い
法定相続分と遺留分では、権利を持つ相続人の範囲が異なります。
法定相続分は、すべての相続人に認められ、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹のすべてが対象です。
一方、遺留分は、配偶者、子、直系尊属にのみで、兄弟姉妹には認められていません。
兄弟姉妹に遺留分が認められない理由は、主に2つあります。
理由① 兄弟姉妹は被相続人との関係が遠い
配偶者や子に比べて、兄弟姉妹は被相続人との関係が遠いと考えられています。
配偶者は生活を共にし、子は被相続人の直系卑属として強い関係がありますが、兄弟姉妹は既に独立して別の家庭を築いていることが一般的です。
そのため、兄弟姉妹は関係性から認められていないということになります。
理由② 兄弟姉妹は被相続人の財産形成への貢献が少ない
被相続人の財産は、配偶者との共同生活や子の養育の中で形成されることが多く、兄弟姉妹が直接的に財産形成に貢献することは少ないと考えられています。
(参考)比較表
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分の権利者 | 遺留分の権利者 |
| 配偶者のみ | 〇 | 〇 |
| 配偶者と子 | 〇(両方) | 〇(両方) |
| 配偶者と直系尊属 | 〇(両方) | 〇(両方) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 〇(両方) | 〇(配偶者のみ) |
| 兄弟姉妹のみ | 〇 | ✖ |
この表でも分かるように、異なるのは兄弟姉妹の箇所のみです。
用いられる場面の違い
法定相続分と遺留分は、用いられる場面が異なります。
法定相続分は遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議を行う際の基準となる割合です。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。
遺留分は、遺言書がある場合に使われます。
遺言書によって自分の取り分が遺留分より少ない場合、または全く相続できない場合に、遺留分侵害額請求を行うことで、最低限の取り分を確保できます。
割合の違い
法定相続分と遺留分では、相続人が受け取れる割合も異なります。
法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって以下のように定められています。
- 配偶者のみ:配偶者が100%
- 配偶者と子:配偶者が1/2、子が1/2(子が複数いる場合は均等に分ける)
- 配偶者と直系尊属:配偶者が2/3、直系尊属が1/3(複数いる場合は均等に分ける)
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(複数いる場合は均等に分ける)
遺留分の割合は、原則として法定相続分の1/2です(直系尊属のみの場合は1/3)。
具体的には以下のようになります。
- 配偶者のみ:1/2
- 配偶者と子:配偶者が1/4、子が1/4(子が複数いる場合は均等に分ける)
- 配偶者と直系尊属:配偶者が1/3、直系尊属が1/6(複数いる場合は均等に分ける)
- 兄弟姉妹:なし
詳しくは、下図を見ると分かりやすいため、参考にしてください。
(参考)
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者のみ | 配偶者:100% | 配偶者:1/2 |
| 配偶者と子 | 配偶者:1/2 子:1/2 | 配偶者:1/4 子:1/4 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 | 配偶者:1/3 直系尊属:1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
時効と権利行使の方法の違い
法定相続分と遺留分では、時効の有無と権利行使の方法も異なります。
法定相続分には時効がありません。
一方で、遺留分には時効があります。
遺留分侵害額請求は、以下の2つの期限のうち、いずれか早い方までに行う必要があります。
- 相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年
- 相続の開始から10年
権利行使の方法は、遺留分を侵害している相手方(多く財産を受け取った人)に対して、遺留分侵害額請求を行います。
| 項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 時効 | なし | あり(知ってから1年、または相続開始から10年) |
| 権利行使の方法 | 遺産分割協議で相続人全員が合意 | 遺留分侵害額請求(内容証明郵便で通知) |
通常は内容証明郵便で通知します。
なお、郵便局によっては内容証明郵便を取り扱っていない小規模な郵便局もあるため、注意が必要です。
法定相続分と遺留分の計算方法

ここでは、具体的なケースを使って、法定相続分と遺留分の計算方法を解説します。
計算の基本ステップ
法定相続分と遺留分を計算する際は、以下の3つのステップで進めます。
ステップ1:相続人の確定
まず、誰が相続人になるのかを確定します。
配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外の相続人は、①子、②直系尊属(父母や祖父母)、③兄弟姉妹の順です。
ステップ2:法定相続分の計算
相続人が確定したら、相続人の組み合わせに応じて、法定相続分を計算します。
遺産総額に各相続人の法定相続分の割合を掛けることで、各相続人の法定相続分の金額が算出できます。
ステップ3:遺留分の計算
遺留分は、原則として法定相続分の1/2です(直系尊属のみの場合は1/3)。
法定相続分 = 遺産総額 × 法定相続分の割合
遺留分 = 法定相続分 × 1/2(原則
ステップ2で計算した法定相続分に1/2を掛けることで、各相続人の遺留分の金額を算出できます。
配偶者と子2人のケース
具体的な例で計算してみましょう。
- 遺産総額:6,000万円
- 相続人:配偶者、子2人(長男・次男)
- 遺言書:配偶者に全額(6,000万円)を相続させる
法定相続分の計算について
配偶者と子がいる場合、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2です。子が2人いる場合は、子の法定相続分1/2を2人で均等に分けます。
- 配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 長男:6,000万円 × 1/2 ÷ 2 = 1,500万円
- 次男:6,000万円 × 1/2 ÷ 2 = 1,500万円
遺留分の計算
遺留分は、法定相続分の1/2です。
- 配偶者:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 長男:1,500万円 × 1/2 = 750万円
- 次男:1,500万円 × 1/2 = 750万円
遺言書では配偶者が全額(6,000万円)を相続することになっていますが、長男と次男の遺留分はそれぞれ750万円です。
長男と次男が遺留分侵害額請求を行った場合、配偶者は長男に750万円、次男に750万円、合計1,500万円を支払う必要があります。
結果として、配偶者は4,500万円(6,000万円 – 1,500万円)、長男は750万円、次男は750万円が相続の対象額です。
配偶者と兄弟姉妹2人のケース
次に、兄弟姉妹がいるケースを見てみましょう。
- 遺産総額:4,000万円
- 相続人:配偶者、兄弟姉妹2人(兄・妹)
- 遺言書:配偶者に全額(4,000万円)を相続させる
法定相続分の計算方法
配偶者と兄弟姉妹がいる場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹が2人いる場合は、兄弟姉妹の法定相続分1/4を2人で均等に分けます。
- 配偶者:4,000万円 × 3/4 = 3,000万円
- 兄:4,000万円 × 1/4 ÷ 2 = 500万円
- 妹:4,000万円 × 1/4 ÷ 2 = 500万円
兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者が遺言書の通りに4,000万円を全額相続します。
兄と妹は、法定相続分では500万円ずつの取り分がありますが、遺留分がないため遺言書に従って何も相続できません。
このケースから、法定相続分はあっても遺留分がないということが明確にわかります。
兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分という最低限の保障がないため、遺言書によっては全く相続できなくなる可能性も出てくるでしょう。
遺留分侵害額請求の手続きと期限

遺留分を実際に請求する方法と注意点について解説します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺言書や生前贈与によって自分の遺留分が侵害された場合に、侵害された分の金銭を請求する権利です。
2019年の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変更されました。
改正前は、不動産などの現物で返還を求めることも可能でしたが、そうなると不動産の持分を共有するなど、後々のトラブルに繋がりかねない問題を抱えていました。
改正後は金銭での請求に統一されたことで、不動産の共有状態が生じにくくなり、手続きがシンプルになっています。
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害している相手方(多くの財産を受け取った人)に対して行いますが、請求することで、自分の遺留分に相当する金額を取り戻すことも可能です。
請求の流れ(3ステップ)
遺留分侵害額請求は、以下の3つのステップで進めます。
ステップ1:内容証明郵便で通知
まず、遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分侵害額請求を行う意思を通知します。
通知は、内容証明郵便を使用します。
内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便を送ることで、請求の意思を明確に示し、時効を止められます。
通知文には、請求する遺留分の金額、支払期限、支払方法などを記載することが必要です。
ステップ2:話し合い(示談交渉)
内容証明郵便を送った後、相手方と話し合いを行います。
お互いが合意できれば、示談が成立します。
示談が成立したら、合意内容を示談書にまとめ、相手方から遺留分侵害額を支払ってもらいましょう。
話し合いの段階で、弁護士に交渉を依頼することも可能です。
弁護士が間に入ることで、適正な金額での示談が期待できるでしょう。
ステップ3:調停・訴訟(合意できない場合)
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では、調停委員が間に入って話し合いを進めますが、調停でも合意できない場合は、訴訟を起こして裁判所に判断してもらいましょう。
訴訟では、遺留分の計算や侵害額について、証拠を提出して主張し、裁判所が判決を下した上で遺留分侵害額の支払いが命じられます。
請求期限と費用
遺留分侵害額請求には、厳格な期限があります。
また、請求には費用がかかることも理解しておきましょう。
請求期限(2つの時効)
遺留分侵害額請求には、以下の2つの時効があります。
いずれか早い方の期限までに請求しましょう。
- 相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年:自分が相続人であることを知り、かつ、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求する必要があります。
- 相続の開始から10年:相続の開始(被相続人の死亡)から10年が経過すると、遺留分侵害の事実を知らなかった場合でも、請求できなくなります。
時効を止めるためには、期限内に内容証明郵便で請求の意思を通知しなければなりません。
遺留分侵害額請求には、以下のような費用がかかります。
- 内容証明郵便の費用:1,000円~2,000円程度(郵便料金、内容証明料、配達証明料の合計)
- 弁護士費用:30万円~50万円程度(着手金と報酬金の合計。事案の複雑さや請求額によって変動します)
- 調停・訴訟費用:請求額の1%~2%程度(裁判所に納める印紙代や、鑑定費用など)
費用の相場が分かると、今後の進め方もスムーズです。
弁護士に相談するメリット
遺留分侵害額請求は、法律の知識が必要で、計算も複雑です。
また、相手方との交渉や、調停・訴訟の手続きも専門的であるため、弁護士に相談することで得られるメリットがあります。
- 遺留分の正確な計算ができる
- 相手方との交渉を有利に進められる
- 調停や訴訟の手続きを任せられる
- 時効の管理を確実に行える
費用はかかりますが、確実に遺留分を取り戻すためには、弁護士へ相談することが必要です。
まとめ
この記事では「法定相続分」と「遺留分」の違いについて詳しく解説してきました。
最も重要なのは、法定相続分は遺言書がない場合の「目安」に過ぎず強制力がないのに対し、遺留分は遺言書の内容よりも優先される最低限保障された「権利」であるという点です。
この権利が認められる範囲も大きく異なり、法定相続分は兄弟姉妹を含むすべての相続人に関係しますが、強力な権利である遺留分が認められるのは配偶者・子・親のみで兄弟姉妹には一切ありません。
違いを理解した上で、ご自身の状況に合わせて次に取るべき行動を判断することが大切です。
相続は、家族間の感情的な対立を生みやすい非常にデリケートな問題です。
特に、遺留分の計算や請求手続きは複雑で、期限も厳格であるため、少しでも不安な点があれば、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!