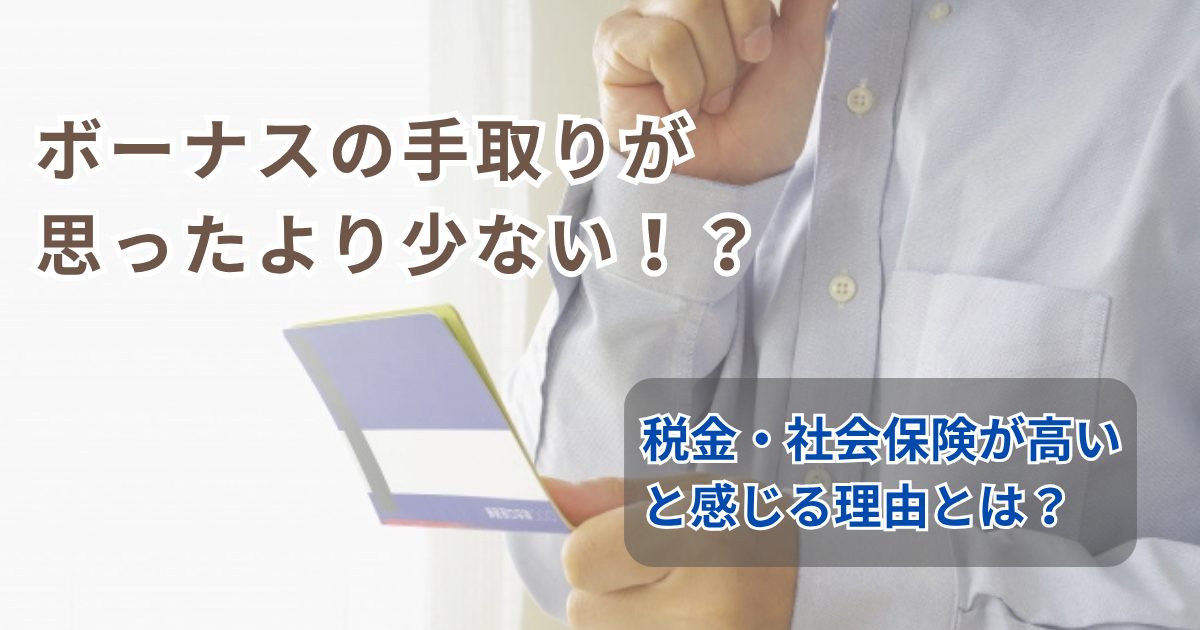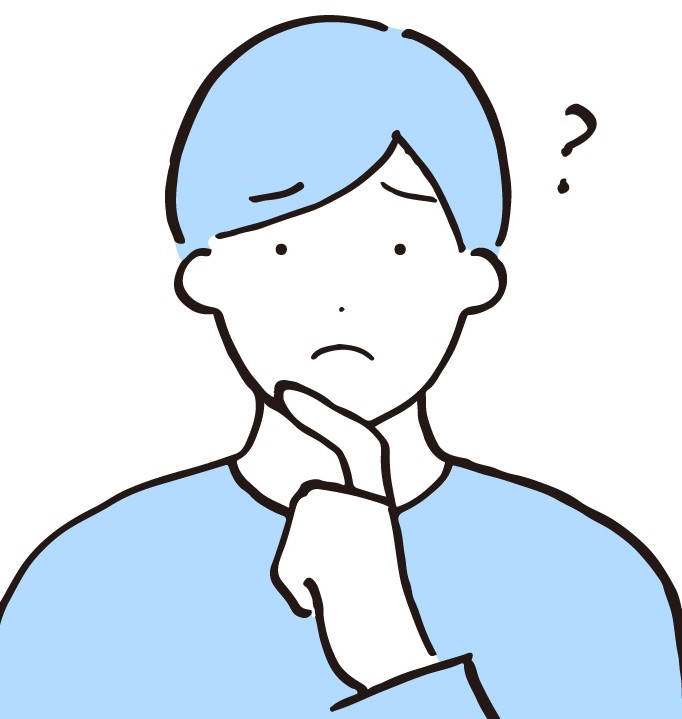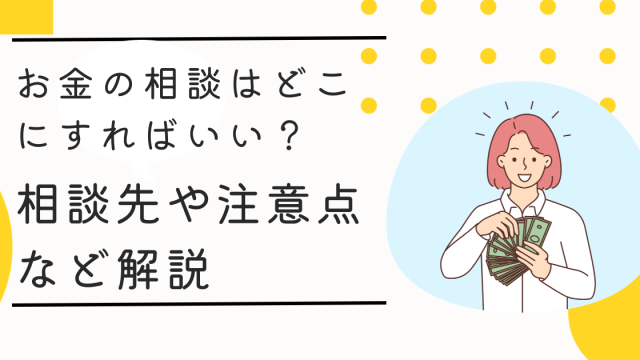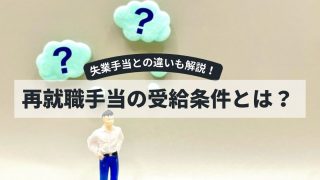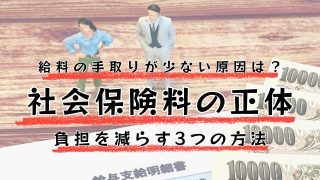ボーナスの支給額を見たときに、このように感じたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、なぜボーナスの税金や社会保険が高いと感じるのかについて、くわしく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
ボーナスの手取りが少なく感じるのはなぜ?

ボーナスにも税金と社会保険料がかかる
ボーナスは「臨時のごほうび」というイメージが強いですが、実際には給与と同じ「所得」として扱われます。
そのため、給与とは別でボーナスそのものから所得税・社会保険料が控除され、額面よりも手取りが減るしくみになっているのです。
【所得とは】
所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。
会社員の場合、収入(総支給額)から給与所得控除を差し引いた金額をさします。
税金や社会保険料が控除される金額は、加入する健康保険組合や扶養親族の人数によって異なりますが、一般的にはボーナス総支給額の2~3割が目安です。
ボーナス支給月の給与明細をチェック
ボーナスが支給されたら、明細書をよく確認してみましょう。
明細を見ると「所得税」「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」などがそれぞれ記載されています。控除の内訳を知るだけでも、なぜ手取りが減っているのかを理解できるでしょう。
ここからは税金と社会保険料それぞれの算出方法について解説します。
ボーナスにかかる税金のしくみ

所得税は「前月の給与額」で税率が決まる
ボーナスにかかる所得税は、源泉徴収税額表に基づいて計算されます。
手順としては以下の通りです。
- 前月の社会保険料控除後の給与を確認
- その金額に対応する税率を国税庁の「源泉徴収税額表」から確認
- その税率をボーナスの支給額に掛けて所得税を計算
たとえば、前月の給与(社会保険料控除後)が40万円の人(扶養親族2人)の場合、税率は約10%前後。
仮に100万円のボーナスなら、およそ10万円が所得税として引かれる計算です。
このように、ボーナスの税率は「前月の給与水準」や「扶養人数」で決まるため、とくに前月残業が多かった場合や、扶養人数に変更があったときには、税金が高く感じる傾向にあります。
ボーナスの所得税も年末調整で清算
ボーナス支給時の所得税も、給与と同様に年末調整で精算されます。つまり、一時的に多めに引かれていて、あとから戻ってくる可能性もあります。
とはいえ、手取りとして受け取る段階では、給与とは別枠で控除されるため、金額のインパクトが大きく「損した気分」になりやすいのですね。
住民税は前年の所得をもとに年間の税額が決まり、12回に分けて毎月の給与から天引きされています。そのため、ボーナス支給時に追加で引かれることはありません。
ボーナスにかかる社会保険料のしくみ

健康保険・厚生年金・雇用保険の3つが対象
社会保険料は、ボーナスからも引かれます。対象となるのは主に以下の3つです。
それぞれの保険料の役割についても確認しておきましょう。
- 健康保険料
医療費の一部を国が負担してくれる公的保険制度のための費用。
医療機関での診察や入院時に自己負担が一定の割合で済むのはこの制度のおかげ。保険料率は加入している健康保険組合や地域によって異なる。 - 厚生年金保険料
将来の年金を支えるための保険料。現役時代に支払う保険料が、老後の年金額に反映されるしくみ。
厚生年金に加入していれば、老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金も受け取ることが可能。 - 雇用保険料
失業時や育児休業時などに給付を受けるための保険料。ボーナスにも課されるが、保険料率は他の社会保険に比べて低め。なお、保険料率は業種によって異なる。
たとえば、健康保険料率が10%、厚生年金保険料率が18.3%、雇用保険料率が0.55%だとすると、合計約29%。
健康保険料と厚生年金保険料は会社と折半するため、実際に本人が負担するのはおよそ14〜15%前後ということです。
つまり、100万円のボーナスなら、社会保険料だけで14~15万円前後が差し引かれる計算になります。
とくに以前より支給額が増えて社会保険料の金額に変更があった場合などは、引かれている金額が多いと感じるでしょう。
ボーナスに社会保険がかからないケースもある?
一般的に、ボーナスには健康保険・厚生年金・雇用保険の社会保険料がかかりますが、以下のようなケースでは例外的に保険料が課されないことがあります。
福利厚生として扱われる支給の場合
結婚祝い金や永年勤続表彰など、労働の対価ではない支給は賞与に該当せず、社会保険料の対象外となります。支給回数が年4回以上の場合
社会保険では、年間支給回数が4回以上のボーナスは「給与」とみなされます。そのため、賞与としての社会保険料はかかりません。
(※給与として扱われるため、給与ベースで保険料が計算されます)育児休業・産前産後休業中に支給された場合
これらの休業期間中は、社会保険料が免除される特例があります。
その期間に支給されたボーナスも同様に免除されるため、社会保険料がかかりません。- 支給月が資格喪失月に該当する場合(退職月のボーナス)
社会保険では「退職日の翌日」に資格を喪失します。
そのため、ボーナス支給月の末日より前に退職する場合は、退職月の社会保険料はかかりません。

ボーナスの活用方法

まとまった金額が支給されるボーナス。せっかくなら価値のある使い方をしたいですよね。
ここではボーナスの活用方法についてご紹介します。
ふるさと納税
ボーナスの活用方法で見逃せないのがふるさと納税です。
ふるさと納税は、自己負担額の2,000円を除いた金額が、所得税と翌年の住民税から控除され、寄付額に応じた返礼品を受け取れるというお得な制度です。
その年の寄付は年末まで申し込めるので、まだ利用したことのない方はぜひ始めてみてはいかがでしょうか?
ふるさと納税には、年収や家族構成による控除上限額があります。
総務省の「控除上限額目安表」や各仲介サイトのシミュレーションなどで確認しておきましょう。
iDeCoやNISAで資産形成する
将来的に資産を増やしていくにはiDeCoやNISAを活用するのもおすすめです。
iDeCoでは掛金が全額所得控除の対象となるため、所得税・住民税の節税につながります。
また、NISAでの運用益は非課税になるため、長期的な資産形成を考えるうえでも有利です。少額から始められていつでも引き出せるのもNISAのメリットです。
ボーナスの一部をこれらにまわすことで、「使って終わり」ではなく、将来の資産を育てるお金として活用できるでしょう。
「iDeCoやNISAを活用した資産形成を始めてみたい!」という方はぜひFPオフィスあしたばへ。
一見難しそうなこれらの制度についても、弊社FPがわかりやすくご説明いたしますので、投資初心者の方もお気軽にご相談くださいね。
まとめ

ボーナスの手取りが少なく感じるのは、税金や社会保険料が控除されるしくみが原因です。ボーナスの支給額が上がると、その分控除額も増えるため手取りが少ないように感じてしまいます。
出来るだけボーナスを有効的に使うために、明細をしっかりチェックし、ふるさと納税やiDeCo・NISAなどで賢く活用することをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
あしたばライター:藤元 綾子
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!
↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓