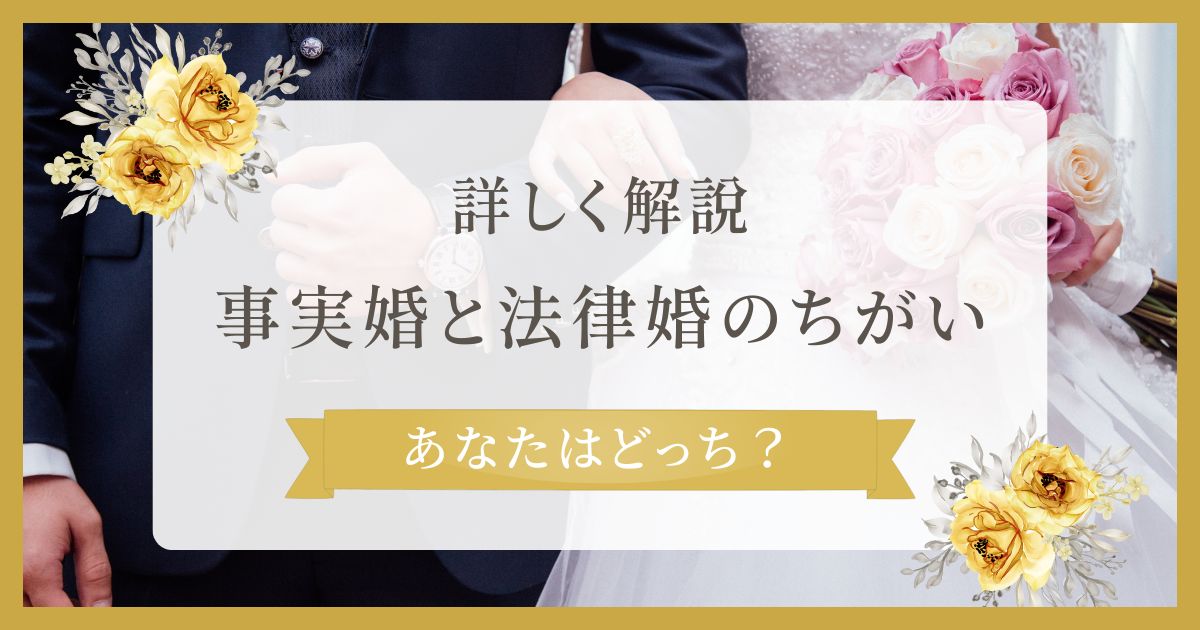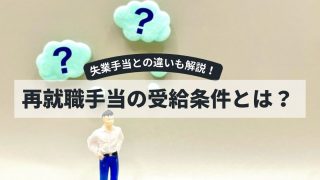最近よく耳にする事実婚。
聞いたことはあるけど、実際どんなものなのか詳しく知らないという方は多いのではないでしょうか?
この記事を読むと、そもそも事実婚とはなんなのか、事実婚を選ぶ理由、法律婚と事実婚の違いが分かります。
法律婚と事実婚の定義

法律婚とは
夫婦で婚姻届に記入し役所で受理してもらうことで、同じ戸籍となり法律上の夫婦となります。これが法律婚です。
事実婚とは
法律婚のように役所で手続きは行いません。しかし、法律婚の夫婦と同じような関係性である状態のことを事実婚といいます。
なぜ事実婚を選択するのか?

などの意見があり、特に「名字を変える必要がない」という理由で、事実婚を選ぶ方は多いようです。選択的夫婦別姓制度が導入されたら法律婚を選ぶ方は増えるのではないでしょうか。
事実婚のメリット

①面倒な改姓の手続きをしなくて済む
すぐに思いついたものだけでも以下の手続きが必要になります。この手間がないのは大きなメリットといえます。
改姓の手続きが必要なもの
・運転免許証、各種免許
・パスポート
・マイナンバーカード
・銀行や証券会社などの金融機関
・キャッシュカードやクレジットカードなど
②たとえ関係を解消したとしても戸籍に残ることはないのでリスクが低い
事実婚は戸籍に記載されないので、関係を解消しても戸籍に残ることはありません。
③保守的な価値観や環境に囚われず、自由に夫婦の在り方を決めることが出来る
年長の男性が一家で一番の権力を持っているとされていたり、女性の方が地位が低いとされている家制度や戸籍制度に違和感を持つ夫婦もいると思います。事実婚であれば夫婦平等に自分たちだけの家族の形を決めることが出来ます。
事実婚でも法律婚と同等になること

法律婚と同じ権利や国の制度を説明したいと思います。
今から挙げるものが全てではありません。
私たちの生活になじみが深いものをピックアップしてご紹介します。
分かりやすいように、ここから被保険者を夫、被扶養者を妻としてご説明します。
①健康保険の扶養に入ることができる
被保険者である夫の健康保険の扶養に妻は入ることができます。収入基準や親族関係などの条件がありますが、妻は自分で公的医療保険に入る必要がありません。
②国民年金の扶養に入ることができる
妻が会社員や公務員として働いている国民年金第2号の夫の扶養に入ることで、妻は保険料を自分で支払う必要はなく、納付済み期間としてカウントされます。
③夫が亡くなった時に妻が受け取る年金制度が適用される
被保険者である夫が亡くなった時に、遺族である妻が受け取る年金制度も法律婚と同等の扱いになります。
法律婚と同等の年金制度
・遺族基礎年金
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金
・自営業の方などが加入する国民年金第1号の夫が亡くなった時に妻が受け取ることができる寡婦年金や死亡一時金
・厚生年金に上乗せして受給される加給年金
④育児休業や介護休業などの各種制度が適用される
事実婚のデメリット

ここまで読んでいただいた方の中には、普通に生活を送ることに関しては、それほど違いを感じないかもしれません。むしろ法律婚より事実婚の方がいいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、事実婚にもデメリットがあります。
それは子供の親権や、パートナーに万が一のことが起こった時の相続や税金に関して事実婚では認められていない権利があるということです。いくつかご紹介したいと思います。
①事実婚では相続権が認められていない
遺産を相続する権利があるのは、法律上の配偶者と子供・親や祖父母・兄弟姉妹とされています。事実婚のパートナーは相続については、他人とされているため相続の権利がありません。
事実婚の場合、子供は父母どちらかの戸籍に入ることになるので、亡くなったのが親権者であった場合、子供には相続の権利があります。パートナーに財産を相続したいと思った場合、生前に対策が必要となります。
②事実婚では相続税の「配偶者の税額軽減の特例」を受けることができない
生前に対策をして遺産を受け取った場合、相続税を納付しなければなりません。
事実婚では相続税の「配偶者の税額軽減の特例」を受けることが出来ないことに加え、支払う相続税が2割増しになるため法律婚に比べると相続税が高くなります。
「配偶者の税額軽減の特例」
法律婚では配偶者が遺産を受け取る時、1億6000万円か相続する金額から控除額を差し引いた2分の1の額のどちらか多い方まで相続税がかかりません。
事実婚のパートナーは法律上の配偶者ではないため、特例を受けることは出来ません。
③所得税の配偶者控除の適用にならない
一定の所得以下の配偶者を養っている納税者は総所得金額から定められた金額を差し引くことが出来るため所得税を減らすことが出来ます。
④子供が生まれた場合、共同親権を持つことができない
事実婚で出産した子供の親権は、母親が単独で持つことになります。父親が親権を持つためには、子供を認知することと、父母双方の同意を得る必要があります。
⑤子供の親権者である父母のどちらかが亡くなった時、残されたパートナーが親権者になるためには親権者の遺言や家庭裁判所の審判が必要。
⑥医療同意の権利が認められない場合がある
医療同意とは患者が意識不明や昏睡状態に陥り自らで意思を伝えることができない時に、治療方針や緊急手術の承諾を代わりに行う権利のことです。
通常、法律上の配偶者や親や子供が医療同意を行うとされていますが、病院によって判断は異なります。場合によって事実婚では認められない可能性もあります。
事実婚の生前にしておきたい相続対策

①生前贈与
生きている間に財産を贈与する方法で、誰にでも贈与することが可能です。しかし贈与を受けた場合は、贈与税がかかります。
②遺言書による贈与
遺言書に事実婚のパートナーに遺産を相続することを記載しておくことで、事実婚でもパートナーに遺産を残すことが出来ます。
③特別縁故者になる
特別縁故者とは、亡くなったパートナーに、法で決められている相続人となる人がいない場合に、家庭裁判所に親しい関係にあったことを申し立てることで遺産を受け取ることが出来る人のことです。
④生命保険の受取人をパートナーにする
生命保険の受取人をパートナーにしておくことで、死亡時にパートナーは保険金を受け取ることが出来ます。
上記のように事実婚では、いざという時の大切な権利を行使することが出来ません。
あの時こうしておけばよかったと後悔しないためにも、事実婚と法律婚の違いを知り、夫婦でしっかり話し合い準備をしておくことがいかに大切かお分かりいただけたのではないでしょうか。少しでも読んでいただいた方の参考になれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!
↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓