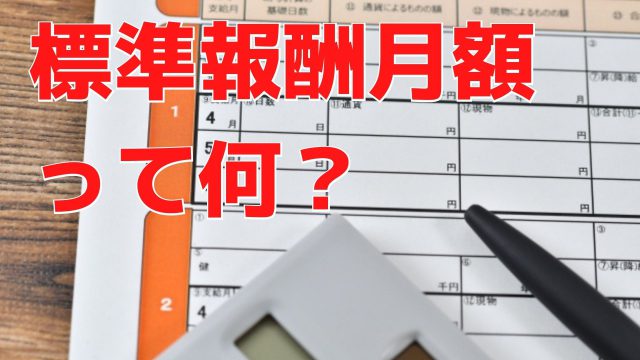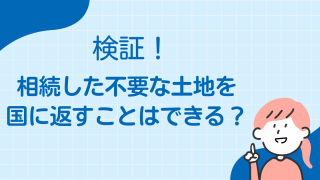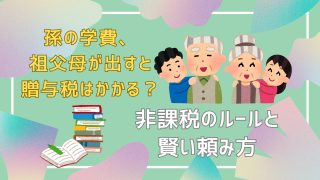近年、NISAやiDeCoなどの制度が広く普及し、一般生活者の方の投資への関心も高まってきました。
その流れの中で「子どもにも投資を学ばせたい」「早いうちからお金の教育を始めたい」と考える保護者が増えています。
しかし実際には「子どもでも投資はできるの?」「未成年者が証券口座を開けるの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、子ども名義での投資についてや未成年口座の仕組み、年齢別の投資教育のポイント、さらに注意点やメリットまで、FPがわかりやすく解説していきます。
そもそも子どもでも投資はできるの?

子ども名義で投資は可能?
かつて存在した「ジュニアNISA」が2023年末で終了したため、現在では、課税口座での取引が基本となります。
未成年者であっても、証券会社を通じて「未成年口座」を開設することで、株式や投資信託などの金融商品を購入することが可能です。
ただし、未成年本人が自由に売買を行うことはできず、必ず親権者が代理で手続きを行わなければいけません。
非課税制度はありませんが、子どもの将来資金や金融教育の一環として未成年口座を活用することも可能です。
未成年口座については後ほど詳しく解説します。
投資と投機の違いについて教える重要性
子どもに投資を教える際には、「投資」と「投機」の違いを正しく理解させることが非常に重要です。この2つは似ているようで、意味がまったく異なるからです。
| 【投資】 | 【投機】 | |
|---|---|---|
| 目的 | 長期的に資産を増やす | 短期的に利益を得る |
| 時間軸 | 数年〜数十年 | 数日〜数ヶ月 ※場合によっては数分〜数時間 |
| リスク | 比較的コントロールしやすい(分散投資や長期保有でリスクを抑えられる) | 高リスク(短期的な値動きに大きく左右される) |
| 手法の例 | 株式の長期保有、投資信託、債券、不動産投資 | FXの短期売買、仮想通貨のデイトレード、信用取引 |
| リターンの特徴 | 緩やかだが安定的な利益を期待 | 大きな利益も可能だが損失も大きくなりやすい |
| 判断基準 | 国・企業の成長性や経済の動向など | 値動きの予測やチャート分析など |
| イメージ | 畑を耕すようにコツコツ資産を育てる | 値動きに賭けるギャンブルに近い |
SNSや動画サイトでは「一発で儲かる方法」といった投機的な情報が多く出回っています。子どもに「お金はコツコツと増やすもの」という視点を持たせることが重要です。
年齢別の投資(金融)教育のポイント

小学生向け:おこづかいでお金の価値や貯金の大切さを学ぶ
小学生の段階では、難しい投資の話よりも「お金の価値を知ること」が大切です。
おこづかい帳をつけたり、欲しいものを買うためにお金を計画的に貯める体験をさせると、自然と「貯金の大切さ」が身につきます。
例えば子どもがゲームソフトを欲しいと言った場合に、「毎月500円ずつ貯めれば〇か月で買えるよ」と具体的に目標を立ててみるのもおすすめです。
中学生向け:お金の循環について理解する
中学生になると、学校での学習やニュースなどを通じて、経済や社会の仕組みに触れる機会が増えてきます。
ご家庭でも、ニュースを見ながらさまざまな話題について、親子で話し合ってみてはいかがでしょうか?社会や将来に目を向ける良い機会になりますよ。
また、中学生くらいになると、お金の循環についても説明すれば理解できるようになります。家計の収入と支出、生活費の内訳について一緒に考えてみるのもおすすめです。
電気代・食費・通信費などを具体的に数字で示すことで、「毎月の食費や自分が使っているスマホにはこのくらいの費用がかかっているんだ」と実感でき、お金の大切さだけでなく収入と支出のバランスを取ることの理解につなげることができます。
高校生向け:授業で「金融教育」について学ぶように
高校生になると、将来の進学や就職が現実的なテーマとなり、金融教育の必要性が一層高まります。
2022年度からは高等学校で「金融教育」が正式にカリキュラムに組み込まれ、授業で資産形成や投資の基礎などについて学ぶようになりました。これは社会に出る前に「金融リテラシー」を高めるための重要な機会です。
この時期には「投資と投機の違い」「リスクとリターンの関係」を体系的に理解できるように。実際のニュースで株価や為替の動きをチェックしてみることで、「企業の業績と株価がどう関係するか」など投資について学ぶことができます。
また、進学を考える高校生にとって「奨学金」や「教育ローン」について理解することも大切です。
「借りたお金は、のちに返済する義務がある」という感覚を早めに持つことは、将来、無計画な借金を避けるために役立ちます。
加えて、アルバイトで実際に収入を得る経験を通じて「働いて得るお金の価値」と「運用して増やすお金の仕組み」を学ぶことができれば、金融教育の効果がさらに高まるでしょう。
年齢・理解力に応じた段階的な学びの進め方
お金や投資の教育は、年齢や理解度に合わせて段階的に進めることが大切です。小学生では「お金の基礎」、中学生では「身近なお金の流れ」、高校生では「より具体的な金融教育」というようにステップアップさせることで、自然に金融リテラシーが育ちます。
未成年口座とは?

ここで、冒頭でお伝えした「未成年口座」について解説します。
未成年口座は、満18歳未満で未婚の人を対象とした証券総合口座です。
ここからは、未成年口座の口座開設などついて説明していきます。
未成年でも証券口座は開設できる?
未成年でも証券口座を開設することは可能です。
ただし、未成年口座を開設し、投資をおこなうには、親権者の同意と手続きが必要です。
証券会社によっては『親権者が証券会社に口座を有していることが条件』となっているケースもあります。
以下は口座開設時に必要となる書類の一例です。
- 子供の本人確認書類(マイナンバーカードや健康保険証など)
- 親権者の本人確認書類
- 親子関係を確認できる書類(住民票など)
多くの証券会社ではオンラインでの申し込みに対応しており、比較的簡単に手続きが進められるようになっています。
原則として親権者が代理で取引を行いますが、一定年齢以上(多くの場合15歳以上)の子供が取引主体者となることを認めている証券会社もあります。
未成年口座でできる投資と制限
未成年口座では、株式・投資信託・ETFなどの取引が可能です。
一方で、金融機関によりますが、信用取引やFX、先物取引といった高リスク商品は利用できません。基本的には「長期投資・現物取引」に限定されます。
贈与や税務上の注意点について
子どもの投資資金は多くの場合、親からの資金援助となるケースが多いと思いますが、未成年口座の運用資金は、子どもへの「贈与」と見なされます。
贈与税の非課税枠である年間110万円を超えると、課税対象となるため注意が必要です。
今後の展望:2026年以降の「こども支援NISA」構想について
政府は新たに「こども支援NISA(仮称)」の導入を検討しています。
これは、2023年末に終了した「ジュニアNISA」に代わる制度として期待されています。
詳細は未定ですが、2026年以降、未成年でも非課税で投資ができる仕組みとなる予定です。
教育資金や子どもの資産形成を支援する制度となることが期待されており、今後の動向に注目が集まっています。
未成年者向けの投資について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。


子どもに投資を学ばせるメリット

お金を管理するスキルが身につく
子どもが投資を学ぶメリットのひとつは、「お金を管理するスキル」が自然と育まれることです。
おこづかいをただ「もらって使う」だけではなく、「いくら入ってきて、いくら出ていき、残高がいくらなのか」を意識する習慣を持つことは非常に重要です。
このスキルは将来的に一人暮らしを始めるときや社会人として給与を得るときに役立ちます。
例えば、毎月の家賃・食費・光熱費・通信費を管理しながら貯金や投資に回すという実生活の家計管理にも直結します。つまり、子どものころから投資を学ぶことは、「経済的な自立」への基礎づくりになるのです。
資産形成の重要性を早くから知ることができる
もうひとつの大きなメリットは、資産形成の重要性を早い段階から理解できる点です。
社会に出てから「投資は必要」と頭では分かっていても、すでに生活費やローンに追われてしまい、実際に行動に移すのは難しいケースが少なくありません。
一方、子どものうちから「お金を働かせる」「お金を育てる」という考え方に触れておけば、社会人になったときに自然と投資や積立を生活習慣の一部として取り入れることができます。
投資を学ぶうえで、とくに理解させておきたいのが「複利の効果」です。
たとえば、毎月1万円を年利3%で20年間運用すれば、単純に貯めた240万円が約330万円に増える計算になります。
こうした具体的な数字を学ぶことで、「早く始めれば長期的に大きな差が生まれる」という事実を実感でき、子どもが将来、大きな買い物やライフイベントに備える際にも非常に役立つでしょう。
将来子どもに必要な資金を貯められる
さらに、未成年口座を活用した投資は、子ども自身の学びだけではなく、将来の資金準備にも直結します。
教育資金、留学費用、結婚資金、さらには独立後の生活資金など、大きな出費は人生の節目ごとに必ず訪れるもの。
子どもの名義でコツコツ投資信託を積み立てていけば、10年後、20年後にはまとまった資金になります。
その過程を子どもに見せ「このお金はあなたの大学進学のために積み立てているんだよ」と説明すれば、投資の教育と将来の資金準備を同時に実現することができます。
子ども自身に数字が少しずつ大きくなっていく様子を見せて「自分のお金が増えていく」経験をさせれば、努力や時間をかけることの価値を実感し、将来の人生設計にも前向きな影響を与えるでしょう。
子どもの投資の注意点・リスク

損失が出る可能性を伝える
当然ながら、投資は必ず利益が出るものではありません。
投資には必ずリスクが伴い、利益だけでなく損失が出る可能性もあるという現実を子どもに理解させることは非常に重要です。
「お金を預ければ必ず増える」という誤解を持ってしまうと、将来の大きな失敗につながりかねません。
例えば、株価は企業の業績や社会情勢によって上下します。短期的にはマイナスになることも多く、時には元本割れする可能性もあります。
こうした事例を親子で一緒に確認することで、「投資は一時的にお金が減ることもあるが、長期的に育てることで利益につながる」という考え方を学ばせることができます。
失敗体験から学ぶことも教育の一環です。
少額であっても「思った通りに値上がりしなかった」という経験を通じて、投資のリスクと向き合い、冷静に判断する力を養うことができます。これは将来、大きな資産を動かすときに欠かせない素養になるはずです。
保護者の管理下でおこなうこと
未成年者が投資を行う場合、必ず保護者の管理と責任が伴います。
未成年者は自分で証券口座を開設して自由に運用することはできず、必ず親権者の同意や管理が必要になります。
大切なのは、単に「親が代理で投資する」のではなく、子どもと一緒に投資の内容を確認しながら教育につなげることです。
たとえば、毎月の積立額や購入する銘柄を親子で話し合い、「どうしてこの投資信託を選んだのか」「なぜ長期で積み立てるのか」といった理由を丁寧に伝えるとよいでしょう。
あくまでも「親が管理し、子どもと一緒に学ぶ」というスタンスを忘れずに、教育の一環として投資を学ぶことが大切です。
SNSやネット情報に影響されやすいリスク
特に中高生になると、SNSや動画サイトなどを通じて、投資に関する情報を目にする機会が増えます。その中には「誰でも簡単に儲かる」「短期間で資産が何倍にもなる」といった誤解を招く情報が多く存在します。
若い世代は好奇心旺盛で、新しい情報に影響されやすいため、「一発逆転」や「楽して稼ぐ」といったキャッチコピーに惹かれてしまうことも。こうした情報を鵜呑みにすると、リスクの高い投機的な取引や詐欺まがいの投資話に巻き込まれる危険性があります。
そのためにも、保護者が正しい知識を伝え、情報の見極め方を教えることが大切です。
「投資に必ず儲かる方法は存在しない」「リスクとリターンは表裏一体である」といった基本的な考え方を繰り返し説明することで、子どもが安易な情報に流されにくくなります。
また、親子で一緒に信頼できる情報源(金融庁や証券会社の公式サイト、新聞など)を確認する習慣をつければ、自然と情報リテラシーも育まれます。これは投資だけでなく、将来社会に出てからの情報活用スキルにもつながる重要な力です。
まとめ

親の同意や管理のもとにはなりますが、未成年口座を使って子どもでも投資をおこなうことは可能です。
現在は未成年口座を利用した投資が中心ですが、2026年以降は「こども支援NISA」によって、子どもの資産形成環境は大きく変わる可能性があります。今後の動向にも注目しておきましょう。
子供に投資教育を始める場合は、親の正しい知識と適切なサポートが欠かせません。
資産形成などのご相談は、ぜひFPオフィスあしたばへお気軽にどうぞ!
最後までお読みいただきありがとうございました。
【あしたばライター:藤元綾子】
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!
↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓