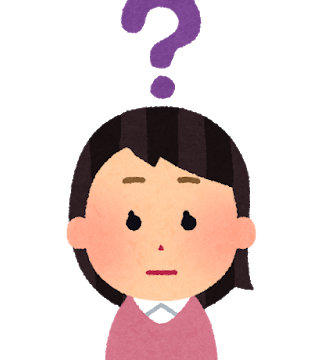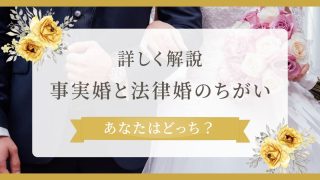「住宅ローンは年収の何倍まで借りられる?」「いくらなら安心して返済できる?」と、正しい情報が分からずに不安が頭をよぎるのではないでしょうか?
一般的に住宅の購入は人生で最も大きな買い物になるため、住宅ローンを組む際は大きな借入の負担が生まれます。
借入の際は、年収を参考にして金額を決める人も多いですが、将来の返済負担も考慮した上で進めることが大切です。
この記事では、年収を参考にした住宅ローンの計画を立てるために必要な年収別のシミュレーションや、返済負担の正しい考え方について解説します。
年収だけで判断できない「借りられる額」と「借りるべき額」の違い
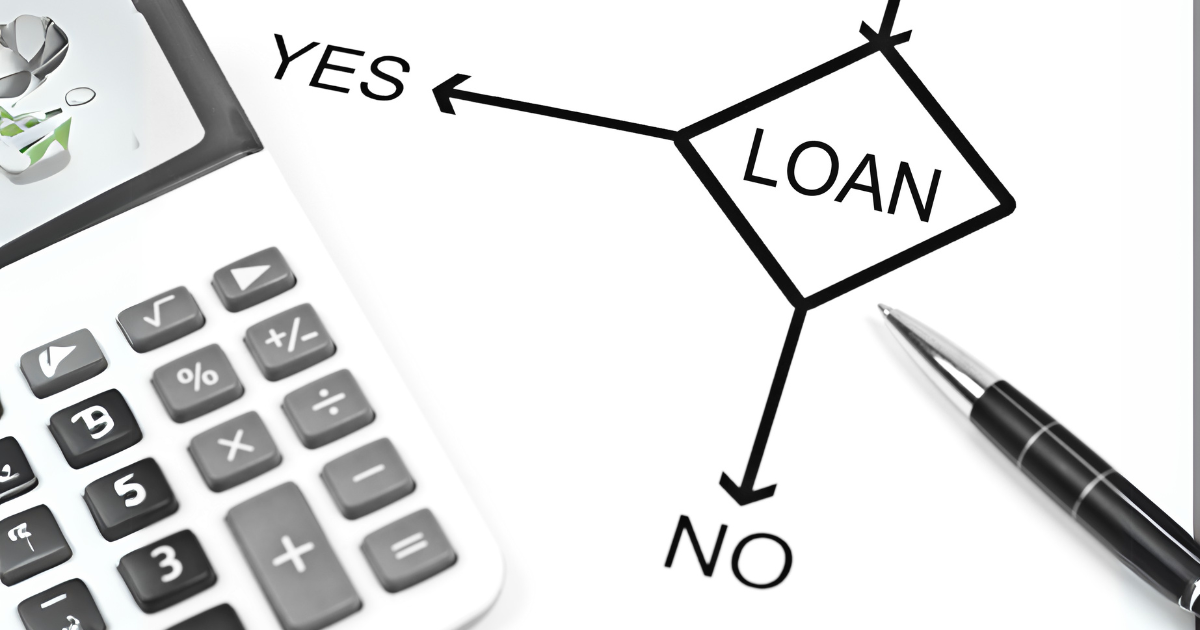
住宅ローンを借り入れる際に「借りられる額」と「借りるべき額」には違いがあるということを把握しておかなければなりません。
金融機関の審査によっては申込人の勤務先や勤務年数、資産背景などの属性面によっては多額の借入を行うことは可能です。
しかしながら、借りられるからといって借りすぎてしまうと、将来的に返済が困難になるリスクも生じます。
年収に応じた「借りられる額」を理解した上で、適正な水準を見極めていきましょう。
年収に対する借入額の目安「年収倍率」とは?
住宅ローンの借入額を考える上で参考になる指標の1つが「年収倍率」です。
年収倍率とは、住宅ローンを組む際に「自分の年収の何倍まで借りられるか」を示す数値で、金融機関が融資の限度額を判断するために用いられます。
参考となる年収倍率の目安は、以下の通りです。
| 種類 | 年収倍率 |
| 土地付注文住宅 | 7.6倍 |
| マンション | 7.2倍 |
| 注文住宅 | 7.0倍 |
| 建売住宅 | 6.6倍 |
| 中古マンション | 5.6倍 |
| 中古戸建 | 5.3倍 |
参考:住宅金融支援機構|2023年度 フラット35利用者調査
例えば、年収500万円の場合、上図の倍率を参考にすると5〜7倍程度、金額にすると2,500〜3,500万円の借り入れが可能です。
ただし、あくまで理論上の数値であり、長期の返済となる場合は「退職後の収入」でも十分に返済ができるかを検討しておかなければなりません。
安易に倍率だけで考えると、家計への負担や不測の事態に対応できないため、シミュレーションによって実際の支出を把握しておきましょう。
「返済比率(返済負担率)」で見る安全な借入ライン
住宅ローンの金額を決める際、借入倍率以上に重要な「返済比率(返済負担率)」を理解しておかなければなりません。
返済比率とは、年収に占める年間のローン返済額の割合を示す指標です。
数値が高ければ高いほど家計の負担が大きくなります。
一般的に、金融機関の審査では30〜35%程度の借り入れは可能なものの、理想的な返済比率は20〜25%です。
(計算式)
年間のローン返済額 ÷ 年収 × 100
年収500万円、年間のローン返済総額が100万円の場合、返済比率は20%です。
年間のローン返済額には住宅ローンだけでなく、教育ローンや車のローン、カードローンなどの返済額も含まれます。
なお、カードローンなど期間が決まっていないローンは、返済期間を3年と試算して返済比率を割り出すなど、金融機関独自のルールがあることを把握しておきましょう。
年収別の返済シミュレーション

年収別のシミュレーションを行うことは、自身の返済能力を客観的に把握し、適切な借入額を見極める上で非常に重要といえるでしょう。
借入の金額が同じでも、返済期間や金利による返済負担、各家計のライフプランによっても異なるからです。
仮に、シミュレーションによって返済負担が大きければ、頭金の準備や物件の価格を見直すことも選択肢として考えられます。
シミュレーションツールを活用し、異なる条件を比較検討することで、より現実的な資金計画を組んでいきましょう。
年収300万円の場合
●金額ベース
| 借入額 | 期間 | 金利 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 借入倍率 | 返済比率 |
| 1,500万円 | 35年 | 2% | 49,689円 | 596,268円 | 5倍 | 19.8% |
| 1,800万円 | 35年 | 2% | 59,627円 | 715,524円 | 6倍 | 23.8% |
| 2,100万円 | 35年 | 2% | 69,565円 | 834,780円 | 7倍 | 27.8% |
●期間ベース
| 借入額 | 期間 | 金利 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 返済比率 |
| 1,800万円 | 25年 | 2% | 49,689円 | 915,516円 | 30.5% |
| 1,800万円 | 30年 | 2% | 59,627円 | 798,372円 | 26.6% |
| 1,800万円 | 35年 | 2% | 69,565円 | 715,524円 | 23.8% |
※返済方法は毎月の返済額が一定の「元利均等返済」で計算しています。
年収300万円の月々の手取り額は約20万円の計算となるため、月々6万円を返済に充てると生活費は14万円です。
仮に、この水準が節約や家計管理の工夫が前提であれば、これ以上の借り入れは得策とは言えません。
また、金額を抑えたとしても、完済時年齢の関係によって35年間借り入れができない場合、返済比率は上がります。
月々の支出を正確に把握し、無理のない返済計画を立てることが、年収300万円台で住宅ローンを上手く借りるためのポイントとなるでしょう。
年収500万円の場合
●金額ベース
| 借入額 | 期間 | 金利 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 借入倍率 | 返済比率 |
| 2,500万円 | 35年 | 2% | 82,815円 | 993,780円 | 5倍 | 19.8% |
| 3,000万円 | 35年 | 2% | 99,378円 | 1,192,536円 | 6倍 | 23.8% |
| 3,500万円 | 35年 | 2% | 115,941円 | 1,391,292円 | 7倍 | 27.8% |
●期間ベース
| 借入額 | 期間 | 金利 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 返済比率 |
| 3,000万円 | 25年 | 2% | 127,156円 | 1,525,872円 | 30.5% |
| 3,000万円 | 30年 | 2% | 110,885円 | 1,330,620円 | 26.6% |
| 3,000万円 | 35年 | 2% | 99,378円 | 1,192,536円 | 23.8% |
年収500万円の方であれば、多くの金融機関で3,000万円を超える住宅ローンの借入が可能となる水準です。
ただし、日本経済の先行き不透明感が増す中で、現在の年収が将来も維持される保証はありません。
毎月の返済が家計を過度に圧迫しないか、将来の収入が変動するリスクがないかも考慮しておく必要があります。
3,000万円以上の住宅を購入する場合、住宅の設計や設備の自由度は高まる一方、オプションの追加などで費用が膨らみやすい点には注意が必要です。
予算と希望のバランスをしっかりと見極め、長期的な視点で返済計画を立てておきましょう。
年収700万円以上の場合
●金額ベース
| 借入額 | 期間 | 金利 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 借入倍率 | 返済比率 |
| 3,500万円 | 35年 | 2% | 115,941円 | 1,391,292円 | 5倍 | 19.8% |
| 4,200万円 | 35年 | 2% | 139,130円 | 1,669,560円 | 6倍 | 23.8% |
| 4,900万円 | 35年 | 2% | 162,318円 | 1,947,816円 | 7倍 | 27.8% |
●期間ベース
| 借入額 | 期間 | 金利 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 返済比率 |
| 4,200万円 | 25年 | 2% | 178,018円 | 2,136,216円 | 30.5% |
| 4,200万円 | 30年 | 2% | 155,240円 | 1,862,880円 | 26.6% |
| 4,200万円 | 35年 | 2% | 139,130円 | 1,669,560円 | 23.8% |
年収700万円以上の収入があれば、4,000万円から5,000万円といった高額な物件の購入も十分に可能な水準といえるでしょう。
しかし、年収が高いからといって安心はできません。
例えば、子どもの教育費の増加や親の介護、自身のキャリアチェンジによる収入減などのリスク管理が求められます。
また、年収が高い世帯では、低い世帯よりも支出が多いケースも見られるため、特にライフプランの計画を立てておくことが重要です。
年収不足を感じたら試す3つの対策

住宅ローンの審査によっては、減額回答によって希望する借入額に満たないケースもあります。
しかし、他の対応策を検討することで、借入の可能額を増やしたり、必要な借入額そのものを減らしたりすることも可能です。
ここでは、年収不足を感じた際に知っておくべき3つの対応策について、詳しく解説していきます。
収入合算(ペアローン・連帯保証人)で借入可能額を増やす
希望する住宅の価格に対して、単独の年収では審査が通らない場合、収入を合算して住宅ローンを申し込めます。
主な方法としては「収入合算(連帯保証型)」と「ペアローン」の2つです
例えば、収入合算は夫婦の一方が主たる債務者となり、もう一方が連帯保証人となることで、2人の収入を合算して審査を受けられます。
一方、ペアローンは夫婦それぞれが個別の住宅ローンを契約する方法です。
ペアローンは、夫婦がそれぞれ別のローンを組むため、団体信用生命保険(団信)に加入でき、住宅ローン控除もそれぞれ受けられるなどのメリットもあります。
一方、諸費用が二重にかかることを考慮しておかなければならず、それぞれのメリットとデメリットを把握しておきましょう。
諸費用・頭金の見直しで必要借入額を削減する
住宅購入時には、物件価格以外にも登記費用やローン手数料といった諸費用が発生します。
諸費用を自己資金で賄ったり、あるいは住宅購入の際に支払う「頭金」の額を見直したりすることで、住宅ローンの必要借入額を減らせるでしょう。
頭金は一般的に住宅価格の1割から2割程度が目安であるものの、金額が多いほど借入額は減るため、月々の返済負担や総支払利息を軽減できます。
また、金融機関によっては頭金の割合に応じて金利優遇を受けられるでしょう。
頭金を多く支払うために貯蓄の大部分を充ててしまうと、急な出費や不測の事態に対応できなくなるリスクも考慮しなければなりません
手元の資金と将来のライフプランを総合的に考慮し、バランスの取れた頭金の額を設定することが重要です。
通りやすい金融機関を選ぶ
住宅ローンの審査基準は金融機関や提携する保証会社によって異なるため、審査が通らない金融機関があったとしても、他の金融機関で承認されるケースもあります。
なお、保証会社は大きく分けると、次の3つです。
- 金融機関のグループ会社
- 外部と共同で設立
- 外部の保証会社
一般的に、金融機関のグループ会社が運営する保証会社は、あまりリスクを取らないため、審査が厳しくなりやすいでしょう。
一方、外部の保証会社である「全国保証」のように、金融機関と関係性のないケースでは比較的審査に通りやすい傾向にあります。
借りた住宅ローンを無理なく返済するためには

住宅ローンは、数十年にわたる長期の返済となるため、計画通りに無理なく返済し続けることが大切です。
契約時の返済計画だけでなく、将来のライフプランの変化や、予期せぬ事態にも対応できるようにしておかなければなりません。
そこで、住宅ローンを無理なく返済していくための具体的なポイントについて詳しく見ていきましょう。
返済期間を無理のない設定にする
住宅ローンの返済期間は、月々の返済額や総返済額に大きく影響します。
同じ金額でも期間が異なると、返済負担は大きく変動するからです。
借入期間が50年のローンを選択できる金融機関もありますが、期間が長ければ総返済額は増えやすくなるため、長ければ良いわけでもありません。
途中で繰り上げ返済も可能なため、最長期間で借り入れし、余裕が出た際に期間短縮や一部返済を検討するのも1つの方法です。
住宅ローン以外の支出入を考えておく
住宅ローンの返済計画を立てる際、収入や支出の変動を考慮しておく必要があります。
例えば、ローンを組んだ後の転職によって収入が減少することで、返済負担が重くなるからです。
また、子どもの誕生や進学に伴う教育費、親の介護費用、車の買い替えなど、支出が想定以上に膨らむことも考えておかなければなりません。
収入減や支出増のリスクに対応するためには、借入可能額の上限ぎりぎりまで借りるのではなく、余裕を持たせた資金計画を立てることが賢明です。
10年後、20年後などの長期的な視点で家族構成や生活状況の変化を予測し、住宅ローン以外の支出入を「見える化」することで、無理のない返済を続けられるでしょう。
まとめ
住宅ローンは、生活の基盤となるマイホームを手に入れるための重要な借入です。
計画を立てる際には、年収倍率や返済比率などに目が行きがちですが、それだけでは十分とはいえません。
ご自身に見合ったシミュレーションを通じて、無理のない返済計画を把握しておくことが大切です。
万が一、年収不足を感じる場合は、収入合算や頭金の見直し、適切な金融機関の選定も必要です。
本記事で解説したポイントを参考に、専門家にも相談しながら、最適な住宅ローン計画を立てるとともに、夢のマイホームでの生活を実現していきましょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!