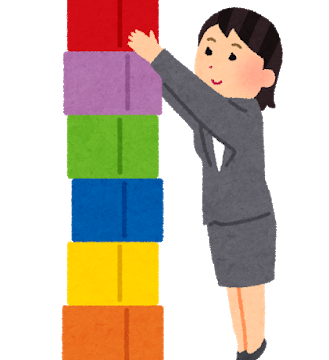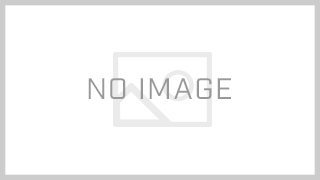長年働いたご褒美とも言える「退職金」。まとまった金額が手元に入ることで、ほっとする反面、「どう使えばいいの?」「無駄にしたくない」といった不安も出てきます。実際、退職金を何となく使ってしまい、後になって後悔する人も少なくありません。
この記事では、FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から、退職金の使い道や注意点、後悔しないための活用法まで、分かりやすく解説します。これから退職を迎える方や、すでに退職金を受け取った方も、ぜひ参考にしてください。
・退職金|みんなどれくらいもらってる?
・退職金を受け取ったらやるべきこと
・退職金の主な使い道|みんなは何に使っている?
・退職金受け取り|税金面の違いについて
・退職金の使い道|注意点は?
・まとめ
退職金|みんなどれくらいもらってる?

退職金の平均支給額
退職金の金額は、勤続年数や企業の規模などによって大きく異なります。以下は、大企業と中小企業別にみた大学卒、高校卒それぞれの退職金の平均金額です。
| 大企業 | 中小企業 | |
|---|---|---|
| 大学卒(定年退職) | 約2,230万円 | 約1,092万円 |
| 高校卒(定年退職) | 約2,017万円 | 約994万円 |
参照:中央労働委員会「令和3年賃金事情総合調査(確報)」
参照:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」
いずれにしても退職金は退職後の生活を支えるための大切なお金です。
後悔のないよう、有効的に使いたいですよね。

ここからは、退職金をもらったらまずやっておくべきことをご紹介します。
退職金を受け取ったらやるべきこと

退職金を受け取った後は、以下の点をおさえておきましょう。
ライフプランの見直し
定年後は「支出が減る」と思われがちですが、レジャー費や子供、孫への援助など、意外と出費がかさむケースも考えられます。
定年後は収入が年金中心となる場合が多いため、支出を見直し、将来にわたって資金が不足しないよう計画を立てましょう。
生活防衛資金の確保
定年退職後は入院や介護、家の修繕費など予期せぬ支出が発生する可能性もあります。万一に備え、生活費の半年~1年分程度は生活防衛資金として確保しておくと安心です。
退職金の主な使い道|みんなは何に使っている?

退職金の使い道は人それぞれですが、他の人が何に使っているのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
以下は投資信託協会が60歳以上を対象におこなった退職金の使い道についてのアンケート調査結果です。(複数回答)
| 退職金の使い道 | |
| 預貯金 | 59.3% |
| 日常生活費への充当 | 25.6% |
| 旅行などの趣味 | 21.7% |
| 住宅ローンの返済 | 20.8% |
| 資産運用のため金融商品の購入 | 20.3% |
| 住宅のリフォーム | 19.0% |
| 家電など耐久消費財の購入 | 11.0% |
| 子供や孫の教育費、結婚費用など | 8.3% |
| 開業・起業資金 | 1.8% |
| その他 | 3.5% |
| 特にない | 9.7% |
出典:投資信託協会「2022年度 投資信託に関するアンケート調査報告書」
この中からいくつかの使い道について詳しくみてみましょう。
①預貯金
調査の結果、最も多いのが「預貯金」でした。老後の生活資金や緊急時に備えて、ある程度現金で持っておくことは必要です。
ただし、インフレ対策としては預貯金だけでは「お金の価値」が減少してしまう可能性も考えられます。余剰資金がある場合は一部を資産運用することを検討してもよいでしょう。
②旅行などの趣味
「第二の人生を楽しみたい」という思いから、海外旅行や趣味に使う人も多くいるでしょう。退職後は時間があるからこそ、今までできなかったことを楽しむチャンスです。
③住宅ローンの返済
退職までに完済していない場合、ローン返済に充てるという方も多いです。住宅ローンの残債を大きく減らすことは精神的な安心感にもつながります。ただし、繰り上げ返済のタイミングや手数料には注意しましょう。
④資産運用
生活防衛資金をしっかり確保したうえでなお余裕資金がある場合は、資産運用することをおすすめします。
資産運用(投資)には当然リスクもありますが、預貯金で資金を眠らせておくことでお金の価値が低下してしまうことの方がリスクといえます。
国が推奨するNISAなどを活用し、長期分散投資でコツコツ資産を増やしていきましょう。
⑤住宅のリフォーム
老後の快適な生活のために、バリアフリーや断熱性向上のリフォームなど、家の修繕をおこなう方も多くいます。自治体によってはリフォームの際に支援制度を活用できる場合があるので、お住まいの市区町村窓口でご確認下さい。
⑥子供や孫への資金援助
子や孫の教育資金や結婚資金の援助も退職金の有効な使い道です。「贈与税の非課税枠」を活用すれば、税負担を軽減しながら支援できます。

⑦開業・起業資金
「退職後に自分の店を持ちたい」「フリーランスとして働きたい」と考える人もいます。夢の実現として魅力的な使い道ではありますが、資金計画や事業リスクの見極めは慎重におこないましょう。
退職金受け取り|税金面の違いについて

退職金の受け取り方は、一括、分割(年金形式)、またはその両方の3つから選択できます。
一括受け取り
退職金を一括で受取るときは「退職所得」となり、他の所得とは区別して課税されます。
この場合「退職所得控除」が適用されるため、税金が大きく軽減されます。
退職所得=(退職一時金-退職所得控除)×1/2
※ただし、以下の場合は「×1/2」の適用はないので留意してください。
・勤続5年以下の役員等の退職手当等
・勤続5年以下の役員等以外の人で、退職金額から退職控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分
退職所得控除額は勤続年数によって異なり、以下のように計算されます。
- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
- 勤続年数20年以上:800万円+70万円 ×(勤続年数-20年)
分割受け取り(年金形式)
退職金を年金として分割で受取る場合は「雑所得」になります。一括で受け取る場合の「退職所得」と異なり、他の所得(公的年金収入など)と合わせた総合課税です。
この場合公的年金などと合わせて一定額までは公的年金等控除が受けられます。
公的年金等控除額の計算式は、以下をご参照ください。
参照:国税庁「公的年金等の課税関係」
一括受け取り+分割受け取り(年金形式)
一時金と分割の両方で受け取ることも可能です。
この場合、一括で受取った分は「退職所得」、分割で受け取る分は「雑所得」として扱われます。
退職金の使い道|注意点は?

無計画に大きな買い物をする
退職金はまとまった金額が一度に手元に入るため、気が緩んでしまい「長年頑張ったご褒美に」と高額な買い物に手を出してしまう人も少なくありません。
もちろん以前から計画を立てて無理のない範囲で購入するのは退職後の楽しみとして良いと思いますが、無計画に高額なものを購入するのは、一時的な満足感を得られる反面、老後の生活費や医療費として確保すべき資金が不足する恐れもあるため慎重に見極めましょう。
退職金詐欺や投資トラブル
退職金を狙った詐欺は、年々巧妙化しています。高齢者をターゲットにした実態のない投資話を持ちかけてくる話は後を絶ちません。
不審な勧誘や提案を受けた場合はすぐに契約せず、家族や専門機関(消費生活センターなど)に相談しましょう。大切な資金を守るためには、「一人で判断しない」ことが最も重要です。
まとめ

退職金は、第二の人生を支える大切な資金です。しかし、無計画に使ってしまうと、後で「足りない」と後悔することにもなりかねません。
退職金の適切な使い道や運用方法などでお悩みの際は、ぜひ「FPオフィスあしたば」にご相談ください。
退職後の資金計画について経験豊富なFP(ファイナンシャルプランナー)がアドバイスさせていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【あしたばライター:藤元綾子】
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!
↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓