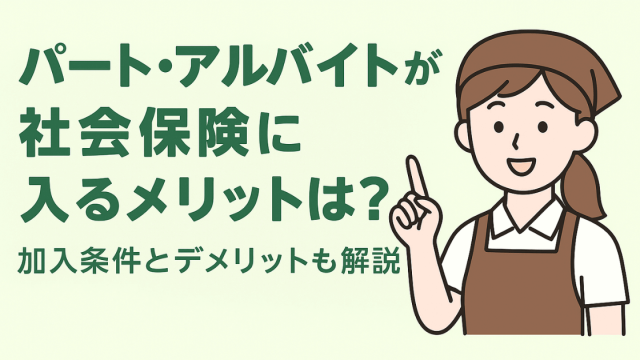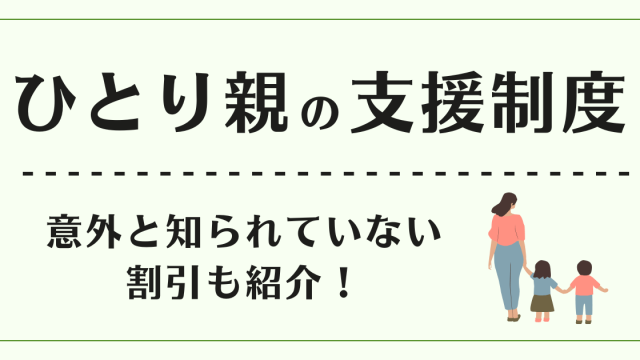「父親の認知症が心配だけど対策方法は?」「民事信託と家族信託のうち自分に適しているのは?」このようなお悩みを抱えていませんか?
最近、取り扱いが増えつつある「民事信託」と「家族信託」ですが、実は法的には同じ制度です。
しかし、金融機関で扱う「家族信託」との区別が付きにくい、成年後見制度との使い分けが難しいなど、正しく認知されていない点もあります。
この記事では、両者の違いによるメリット・デメリットや他制度との比較、手続きの流れと費用相場まで、知っておくべき内容を網羅的に解説しました。
最後まで読めば、あなたの家族に最適な認知症対策を自信を持って選択できるようになるでしょう。
民事信託と家族信託の基本知識

認知症対策や相続対策として注目される「民事信託」と「家族信託」は、呼び方が違うだけで法律上は同じ制度です。
とはいえ、呼び方が違うのには理由があるため、本質的な仕組みを理解した上で「なぜ分かれているのか」を理解しておく必要があります。
また、金融機関で扱う「家族信託」と呼ばれる商品は全く別の仕組みであり、違いを明確にしておきましょう。
民事信託と家族信託は同じ制度
信託法などでは「民事信託」「家族信託」という用語はなく、便宜上は実務的な呼び方に分けています。
専門家によっては定義が異なる場合もありますが、共通するのは「非営利を目的とした」信託契約という点です。
民事信託とは信頼できる相手に財産の管理を託す仕組み全般を指しますが、財産管理を任せる相手が家族の場合は家族信託と呼ばれています。
金融機関の家族信託商品との違いに注意
一般的な家族信託と、金融機関が提供する「家族信託」は仕組みが異なります。
金融機関が提供するサービスは、営利目的の「商事信託」に該当し、非営利の民事信託とは分けて考えなければなりません。
商事信託では相続発生後すぐに資金を引き出せたり、契約通りの財産管理が期待できたりと、メリットが多い点も徴です。
ただし、最低利用金額が100万円以上に設定されているなど、少額利用には向かないデメリットもあります。
また、不動産の取り扱いができないなど、制約事項もあるため注意しておきましょう。
民事信託のメリット・デメリット

民事信託は、認知症による資産凍結を防ぐ手段として有効です。
しかし、民事信託がもたらすのはメリットだけではなく、デメリットもあるため、しっかりと内容を理解しておかなければなりません。
「自分の家族にとって本当に必要な制度なのか」を判断しておくことが大切です。
5つの主要メリット
民事信託は、将来の不安を解消するメリットが多い制度です。
他の制度にはない柔軟性と将来の計画が立てやすいだけでなく、成年後見制度や遺言では対応しきれない部分もカバーできます。
ここでは、5つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.親の認知症対策
親の判断能力が正常なうちに契約を結べば、認知症などで判断能力を失った後も財産が凍結されるリスクはありません。
受託者が不動産の管理や預金の引き出しを行えるため、実家の売却や介護費用の支払いなどもスムーズに進められます。
2.柔軟な財産管理
成年後見制度では財産の積極的な運用や投資が制限されますが、民事信託は受託者の判断で投資や不動産の売却ができます。
収益性の低い不動産の売却や資産を組み換えるなど、収益性を高めるための投資も可能です。
3.遺言以上の機能
遺言では自分の代の相続しか指定できませんが、民事信託なら「自分が亡くなった後は妻、妻が亡くなった後は長男」という選択ができます。
後世に渡って資産を承継させられるため、自身の想いを将来に反映させた相続対策も可能です。
4.不動産の共有リスクを回避
不動産を相続した場合は、兄弟などの共有名義になることも多く、売却や大規模修繕の際には全員の同意が必要になるなどの手間が掛かります。
一方、民事信託は当事者間の契約のため、成年後見制度のような裁判所への申立てや継続的な報告義務がなく、手間や費用も大幅に抑制することが可能です。
5.倒産隔離機能で財産を守れる
信託された財産は「倒産隔離機能」により、委託者や受託者の固有財産とは法的に分離されます。
信託法などの法律により、信託財産が受託者の固有財産とは別途管理されるため、委託者や受託者が破産しても信託財産がその債権者に差し押さえられることはありません。
また、信託された不動産が共有状態であっても、受託者は単独でその管理や処分できます。
3つの注意すべきデメリット
民事信託は遺言よりも多くのメリットがある一方で、利用にあたっては注意すべきデメリットがあることを理解しておかなければなりません。
制度の特性や運用上の負担を理解せずに利用すると「想定外のトラブル」につながるおそれがあるからです。
ここでは、民事信託の主なデメリットについて整理します。
1.身上監護はできない
民事信託は財産を管理する制度であり、介護施設への入所契約や入院手続き、要介護認定の申請といった「身上監護」を代行することができません。
仮に、身上監護を任せたい場合は、任意後見制度など別の制度との併用を検討する必要があります。
2.節税効果は基本的にない
信託財産と他の財産は損益通算できないため、不動産投資をしている場合は税負担が増えることがあります。
損益通算とは、複数の不動産の赤字と黒字を相殺して税金を計算する仕組みですが、信託財産と個人の財産は別々に扱われるため相殺できません。
また、委託者と受益者が異なる「他益信託」では、贈与税がかかる場合もあります。
3.受託者の負担が大きい
財産管理を任される受託者には、信託された財産を適切に管理・報告する責任と義務が課せられます。
帳簿を作成したり、年に一度は財産目録を受益者に報告したりと、事務的な負担は決して小さくありません。
しかも、信託契約は一方的に破棄できないため、受託者になる際は注意しておきましょう。
他制度との違いと使い分け
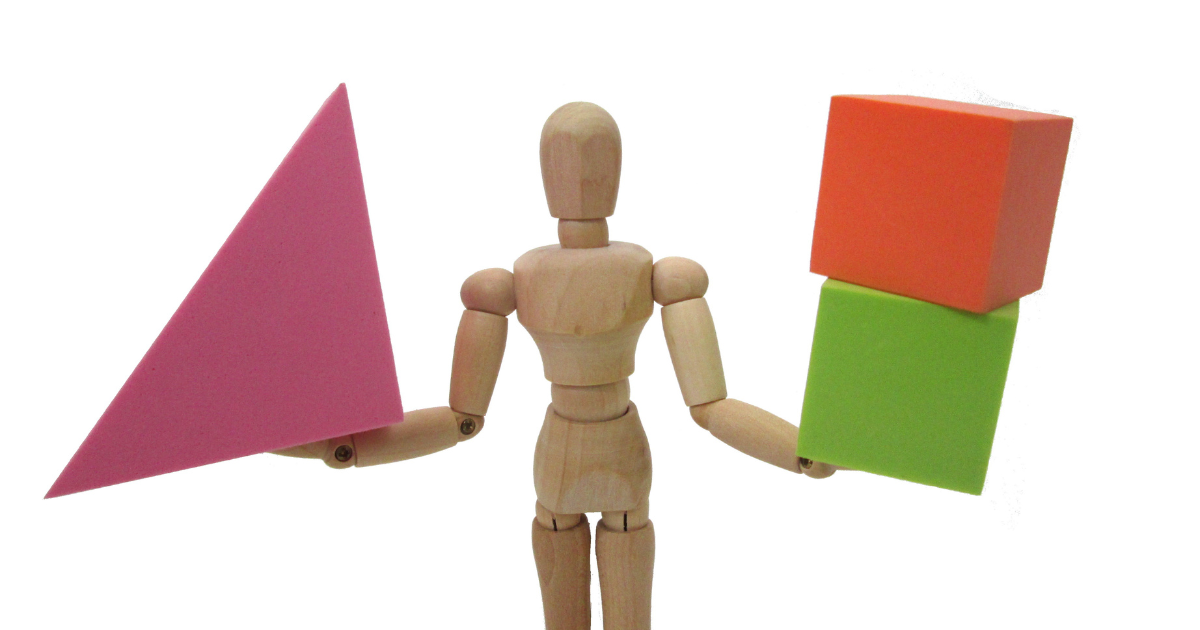
認知症対策や相続対策には、民事信託以外にも成年後見制度や遺言書などの選択肢があります。
それぞれに特徴があり、目的や状況によって最適な制度を選択することが大切です。
単独で完璧な制度は存在しないため、他の制度と組み合わせて使うことでご自身の家族に最適な対策を選択しましょう。
成年後見制度との違い
民事信託と成年後見制度の最も大きな違いは「財産管理の目的」と「柔軟性」です。
成年後見制度では、財産を「守る」ことを最優先としていますが、民事信託は財産を「活用」することを目的とした契約です。
たとえば、成年後見人は裁判所の許可なく不動産の売却や生前贈与、投資を行うことは原則できません。
一方、民事信託は契約内容に基づき、受託者の判断で資産の組み換えなど、裁判所の関与なしに財産運用ができるため、受託者への報酬支払いも任意です。
遺言書との違い
遺言書と民事信託はでは「効力が発生するタイミング」と「承継先の指定範囲」が異なります。
遺言書では、自分の財産を一代限りしか承継できませんが、民事信託は生前の財産管理から死後の資産承継までを一つの契約でカバーすることが可能です。
また「自分が亡くなったら妻、妻が亡くなったら長男」というように、二次相続以降の承継先まで指定する「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」も選択できます。
手続きの流れと費用

民事信託を始めるにあたって、自分で手続きを行うことも可能ですが、一般的には専門家の力を借りることが多いでしょう。
ただし、自分で進める場合と専門家に依頼する場合では、費用に大きな差が出てくるため、相場を知っておくことも重要です。
まずは全体の把握と手続きの流れを理解した上で、最適な進め方が選択できるようにしておかなければなりません。
民事信託の手続きの流れ
民事信託(家族信託)の契約は、以下の5つのステップで進めるのが一般的です。
手続きの流れを理解しておくことで、家族での話し合いから実際の運用開始まで、計画的に進められるため正しく把握しておきましょう。
1.家族で信託の目的・内容を話し合う
まずは「何のための信託か」「誰に何を託し、誰のために使うのか」を家族全員で話し合うことから始めることが大切です。
認識の共有がずれていると、後々のトラブルの原因になりかねません。
2.信託契約書を作成する
話し合った内容を元に、法的に有効な信託契約書を作成しましょう。
契約書が信託すべてのルールの基礎となるため、将来起こりうる事態を想定し、曖昧な表現を避けて具体的に記載しておくことが重要です。
3.契約書を公正証書にする
作成した契約書は、公証役場で公正証書にすることをおすすめします。
公正証書にすることで契約の証明力が高まり、後日の紛争を予防にもつながるからです。
必須ではないものの、トラブル回避には役立ちます。
4.財産の名義変更手続きを行う
契約締結後、信託する財産の名義を委託者から受託者への変更手続きが重要です。
不動産は法務局で「所有権移転登記」と「信託登記」の申請、預貯金は金融機関で「信託口口座」を開設し、信託財産と受託者個人の財産とを分けて管理しましょう。
5.信託財産の管理・運用を開始する
すべての手続きが完了したら、受託者は契約内容に従って財産の管理・運用を開始します。
受託者は帳簿を作成し、財産の状況を定期的に受益者へ報告する義務を負うため、漏れなく管理することが大切です。
自分でやる場合と専門家依頼時の費用比較
民事信託では、自身での手続きか専門家に依頼するかで費用が大きく変わります。
専門家に依頼する場合は、実費に加えて専門家への報酬が必要になるため、それぞれの相場を確認していきましょう。
1.自分で手続きする場合の費用
自分で手続きする場合は実費のみです。
- 公正証書作成手数料:3万円~10万円程度
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.3~0.4%
- 書類取得費用:数千円
2.専門家に依頼する場合の費用
自分で手続きする場合の「実費」に加えて、専門家への報酬が発生します。
- 信託契約のコンサルティング・設計費用:信託財産の0.5%~1%(最低30万円程度)
- 不動産の信託登記報酬:10万円前後
専門家に依頼するとことで、家族の状況に合わせた最適な契約書の作成や煩雑な手続きをすべて任せられるため、積極的に活用しましょう。
まとめ
民事信託や家族信託は、認知症による資産凍結を防ぐ有効な手段として注目されていますが、結論は同じ制度です。
民事信託を選択するポイントは、認知症対策として有効である一方、身上監護はできず、仮に身上監護を任せたい場合は成年後見制度などと組み合わせて管理しましょう。
手続きを進める上での費用は自身で行う場合が約20万円、専門家への依頼で50万円以上が相場となります。
一見すると、専門家へ依頼する費用は高く見えますが、複雑な契約書作成や将来のトラブルを回避できることを考慮すれば魅力のある制度です。
万が一、家族に認知症進行が懸念されるのであれば、早めに民事信託の専門家に相談し、ご家族の状況に適した対策を検討しておきましょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!