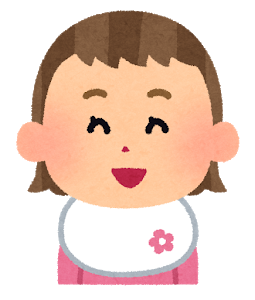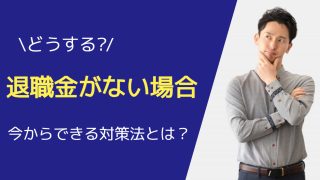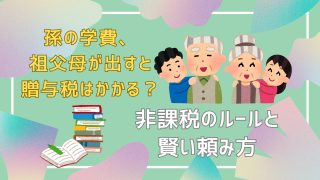「家族の認知症が心配」「このままだと将来相続で揉めるかもしれない」という不安を抱えていませんか?
対策として、遺言書の必要性は分かっていても法的な知識がなく、手続きが複雑で何から始めればいいか分からない方も多いでしょう。
特に認知症の進行が心配な状況では、時間的な制約もあるため、より深刻になる前の選択肢となり得るのが「遺言信託」です。
遺言書の作成から保管、相続発生後の手続きまでを銀行などの専門機関が一括でサポートしてくれるため、法的な知識がなくても安心して利用できます。
親の認知症進行や家族に負担をかけたくない場合の「遺言信託」が有効な選択肢となるかどうかを判断できるため、是非確認しておきましょう。
遺言信託とは|基本的な仕組みと自筆遺言書との違い

遺言信託とは、将来の相続手続きに備えて、遺言書の作成から保管、相続発生後の手続きまで、銀行などの専門機関に一括で任せられるサービスです。
財産の分け方を明確にした上で実行してもらえるため、遺された家族が相続で揉めたり、手続きを巡って困ったりするリスクを大幅に減らせます。
法律に詳しくなくても、専門家のサポートを受けながら進められる点が大きな特徴です。
遺言信託の定義と基本的な仕組み
「信託」とは、自分の財産を信頼できる第三者に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用してもらう法的な仕組みです。
財産の持ち主である「委託者」が、託される機関「受託者」に対して明確な指示を出し、その内容に基づいて財産を扱ってもらう方法で進められます。
委託者とは
自分の財産を信託する人のこと。
財産の使い道や目的、誰のために使うかを決める人のことです。
受託者とは
委託者から財産を預かって管理・運用する専門機関のこと。
信託銀行や信託会社が委託者の指示に従って財産を運用し、利益を受益者に交付します。
公正証書遺言の作成や保管、相続が発生した後の執行まで、専門家が全てをサポートするため、複雑な法律知識や煩雑な書類準備が不要です。
信託は「信じて託す」行為そのものであり、専門家の力を借りることで、家族の不安やトラブルを未然に防ぐ手段となります。
遺言信託のサービス内容
遺言信託のサービスは、大きく分けて「作成」「保管」「執行」の3つのフェーズに分かれています。
まず、遺言書の作成では、専門家が希望をヒアリングし、公正証書遺言の形で内容を文書化するフェーズです。
自分の意思が正確に反映されるよう、法的な観点からも細かくチェックしてもらえます。
次に、保管のフェーズでは、作成した遺言書を信託銀行や専門機関で安全に保管しますが、必要に応じて内容の見直しや更新も可能です。
そして、最も重要な執行では、相続発生後、遺言に従って財産分配や名義変更などの手続きを一括で代行してもらえます。
家族が困らないよう、法律と実務のプロが円滑に対応してくれるのが大きな特徴です。
自筆遺言書と遺言信託の違い
遺言には様々な形式がありますが、もっとも身近なのは自筆証書遺言です。
紙とペンさえあれば作成でき、費用もかからないため、一見すると手軽で魅力的に感じるかもしれません。
しかし、法律的な要件を満たさなかった場合は無効になる恐れがあり、また保管状況によっては改ざんや紛失のリスクもあります。
一方、遺言信託では、信託銀行や法律の専門家が関わることで、作成内容の妥当性や法的な有効性を担保することが可能です。
さらに、遺言内容を安全に保管し、相続発生後には第三者の立場で公平に執行されるため、家族間のトラブル防止にもつながるでしょう。
費用負担はありますが、安心感や確実性が高く「本当に大切な人に財産をきちんと届けたい」という想いを実現できる方法です。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 遺言信託(公正証書+執行付き) |
| 作成方法 | 自分で記載 | 専門家が作成サポート |
| 保管 | 自宅または法務局 | 銀行等が厳重保管 |
| 費用 | 低コスト(ほぼ無料) | 数十万円(内容により変動) |
| 執行 | 相続人が行う | 専門機関が代行 |
| トラブルリスク | 記載ミス等で高リスク | 法的安定性が高く安心 |
遺言信託を選ぶ理由

遺言信託は、遺言書の作成から死後の財産分配、名義変更などの手続きまでを一括で専門家に任せられるなどメリットの多い制度です。
便利である一方、相応の費用がかかる点や、契約時の内容変更に手間がかかる場合もあります。
ここでは、メリットとデメリット、注意点を整理し、自分に合った判断ができるよう解説していきましょう。
遺言信託の5つのメリット
遺言信託には「作成・保管・執行」までを一貫して任せられますが、特に初心者が押さえておくべきメリットを紹介します。
無効になる心配が少ない
自筆の遺言書は簡単に作成できる一方、書式の不備や法的要件を満たさないことで無効になる可能性もあります。
一方、遺言信託では、公証人や弁護士といった法律の専門家が作成段階から関わるため、形式・内容ともに確実な文書を完成させることが可能です。
紛失や改ざんのリスクが限りなく低い
遺言書を自宅で保管する場合、火災や盗難、家族による改ざんリスクを完全に排除するのは困難といえるでしょう。
しかし、遺言信託では信託銀行などの専門機関が文書を、複数のセキュリティレベルが施された場所で管理するのが一般的です。
相続発生後の負担が軽減
遺言信託では、被相続人が亡くなった後の手続きを信託機関が一括で対応します。
相続人が金融機関の解約、名義変更、登記手続きなどを行う必要がないため、高齢の遺族や手続きに不慣れな家族でもサポートがあるため安心です。
遺族同士のトラブルを防ぎやすい
相続を巡るトラブルは、財産の大小にかかわらず発生することが多いでしょう。
とくに遺言執行を家族が担当すると、感情的な対立が起こりやすく、関係が悪化するケースも見られます。
遺言信託では、第三者である信託機関が客観的に遺言の内容を執行するため、「家族の関係性を損なわない」仕組みとしても有効です。
内容の見直しが容易
遺言信託では、契約後も内容の変更や追加が可能で、現実に即した形にいつでも調整できます。
柔軟に対応できることで、将来への不安が和らぎ、長期的に安心して利用できるのが特長です。
「一度作ったら終わり」ではなく、何度でも見直せるという点が、多くの利用者に支持されています。
知っておくべき3つのデメリット
遺言信託は多くの利点がある一方で、事前に知っておくべき注意点もあります。
契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、サービス内容や費用体系、契約条件をしっかり理解しておくことが大切です。
ここでは、特に見落とされがちな3つのポイントを具体的に解説します。
サービスによっては数十万円かかることもある
遺言信託は無料ではなく、初回の相談・契約時にかかる費用は、遺言内容の複雑さや資産規模によって大きく変動します。
一般的には10万円〜30万円程度、中には50万円を超える例もあるため、事前に「何にいくらかかるのか」を明確に確認しておかなければなりません。
また、相談だけでも有料となる場合があるため、無料相談の有無も確認しておきましょう。
契約後の内容変更には制約がある場合も
一度契約した後でも、家族構成や資産状況の変化に応じて遺言の内容を見直したくなることは珍しくありません。
しかし、契約先や信託内容によっては、変更手続きに手間がかかったり、追加費用が発生したりする場合があります。
契約時には「後から変更は可能か」「その方法と費用はどうなるか」を具体的に確認しておきましょう。
信託機関ごとに対応範囲が異なるため、内容をよく比較する必要がある
「遺言信託」という名称は共通でも、提供されるサービス内容は機関によって大きく異なります。
ある銀行では保管と執行のみを行う一方、別の機関では相続人との連絡や遺産分割協議書の作成まで対応が可能であるなど、事前の確認が必要です。
契約前に「どこまで任せられるのか」を詳細に確認し、複数社を比較検討しておきましょう。
遺言信託にかかる費用の全体像

遺言信託には「契約時」「保管中」「相続発生後」の3つのタイミングで費用が発生します。
タイミングごとに料金体系が異なり、見落とされやすい継続的な費用も存在するため、各段階でかかる費用の目安を見ていきましょう。
契約時にかかる初期費用
遺言信託を検討し始めたとき、まず気になるのが「相談料や初期費用はいくらかかるのか」という点です。
一般的には信託銀行や金融機関では、初回の相談は無料であるものの、本契約に進む段階で「遺言信託契約料」として10万円〜30万円ほどの費用が発生します。
なお、遺言内容のヒアリング、公正証書作成の支援、財産目録の整理などが含まれており、対応範囲によっては50万円を超えるため注意が必要です。
また、信託機関によっては、契約後に内容を変更するたびに追加費用がかかることもあります。
さらに、公証役場での手数料も1万〜数万円が別途必要となるため、トータルコストを把握してから契約を検討しましょう。
毎年支払う保管手数料
遺言信託を契約した後は、作成した遺言書を安全に保管してもらうための「保管手数料」が継続的に発生します。
一般的な信託銀行では年間2,000円〜5,000円程度が相場とされており、金額自体は大きくないものの、長期間にわたる場合はコストがかさむ点に注意が必要です。
保管料には、書類の管理だけでなく、セキュリティ対策や損失補償、内容確認のための通知サービスなどが含まれていることもあります。
また、変更や内容更新を希望する場合は、別途手数料がかかるケースもあるため注意が必要です。
契約前に「保管手数料の年額」「内容変更の費用」「更新のルール」を明確にしておきましょう。
相続発生時の執行費用
遺言信託で最も費用が発生するのは、実際に相続が開始されるタイミングです。
特に「遺言執行報酬」は、遺産総額に応じて計算されることが多く、報酬額は相続財産の1〜1.5%が目安とされています。
たとえば、3,000万円の財産であれば、30万円〜45万円程度がかかる計算です。
遺言執行報酬では、金融機関の解約や不動産の名義変更、相続人への分配手続き、各種書類の作成・提出など、専門知識を要する一連の業務が含まれています。
ただし、信託機関ごとに報酬基準は異なるため、契約前の比較検討は不可欠です。
遺言信託の相談先選び|銀行・弁護士・司法書士の特徴

遺言信託を検討する際は「どこに相談すればいいのか分からない」と感じる方も多いでしょう。
信託銀行、弁護士、司法書士など、相談先によって対応範囲や費用が異なるため、安易に決めるとスムーズに進まない可能性も否定できません。
ここでは初心者でも安心して相談できる窓口の特徴とそれぞれの違いをわかりやすく解説していきます。
主要銀行のサービス比較
遺言信託について相談できる主な窓口は「信託銀行」「弁護士」「司法書士」の3つです。
信託銀行は、遺言の作成から保管、執行までをワンストップで対応してくれるだけでなく、料金体系も明確で、無料相談を実施しています。
一方、複雑な家族構成や相続トラブルが予想される場合は、弁護士への相談が有効です。
法律全般の知識を持つため、紛争リスクのある遺産分割や相続人調査にも柔軟に対応できます。
司法書士は登記業務に強く、不動産の相続などに特化した相談が可能です。
それぞれ得意分野が異なるため「自分のケースでは何が課題か」を明確にした上で、最適な相談先を選ぶことが失敗を防ぐポイントといえるでしょう。
相談から契約までの流れ
遺言信託の相談から契約までは、一般的に4つのステップで進みます。
①無料相談の予約を取り、基本的な仕組みや費用について説明を受ける段階です。
この時点で家族構成や資産状況を大まかに伝え、遺言信託が適しているかどうかを判断してもらいます。
②具体的な遺言内容を決める段階です。
専門家が詳細なヒアリングを行い、財産の分割方法や相続人への配慮事項などを整理していきますが、契約費用の見積もりも提示されます。
③公正証書遺言の作成に向けた準備です。
必要書類の収集や財産目録の作成など、専門家のサポートを受けながら進めるため、公証役場での手続き代行など、複雑な手続きも気にする必要はありません。
④遺言書の保管契約を結び、定期的な内容確認や変更手続きのルールを確認して完了となります。
契約後も継続的なサポートが受けられるため、安心して長期間利用できるでしょう。
まとめ
遺言信託は、遺言書の作成から保管、相続発生後の手続きまでを専門機関が一括でサポートしてくれるサービスです。
特に認知症の進行が心配な方や、家族に負担をかけたくない方にとって、非常に有効な選択肢となります。
法律の専門家による作成サポートにより無効になるリスクを防げる点、厳重な保管体制、そして相続発生後の円滑な手続き代行が大きなメリットです。
一方で、初期費用や継続的な保管料、相続時の執行費用など、相応のコストがかかることも理解しておく必要があります。
費用面では、契約時に10万円〜30万円程度、年間保管料2,000円〜5,000円程度、相続発生時は遺産総額の1〜1.5%が目安です。
これらの費用を考慮しても、家族の負担軽減や確実な遺言執行を考えれば、十分に検討する価値があるサービスといえます。
まずは信託銀行の無料相談を活用し、あなたの状況に最適な解決策を見つけることから始めたうえで、早めに対策することが将来の安心につながるでしょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!