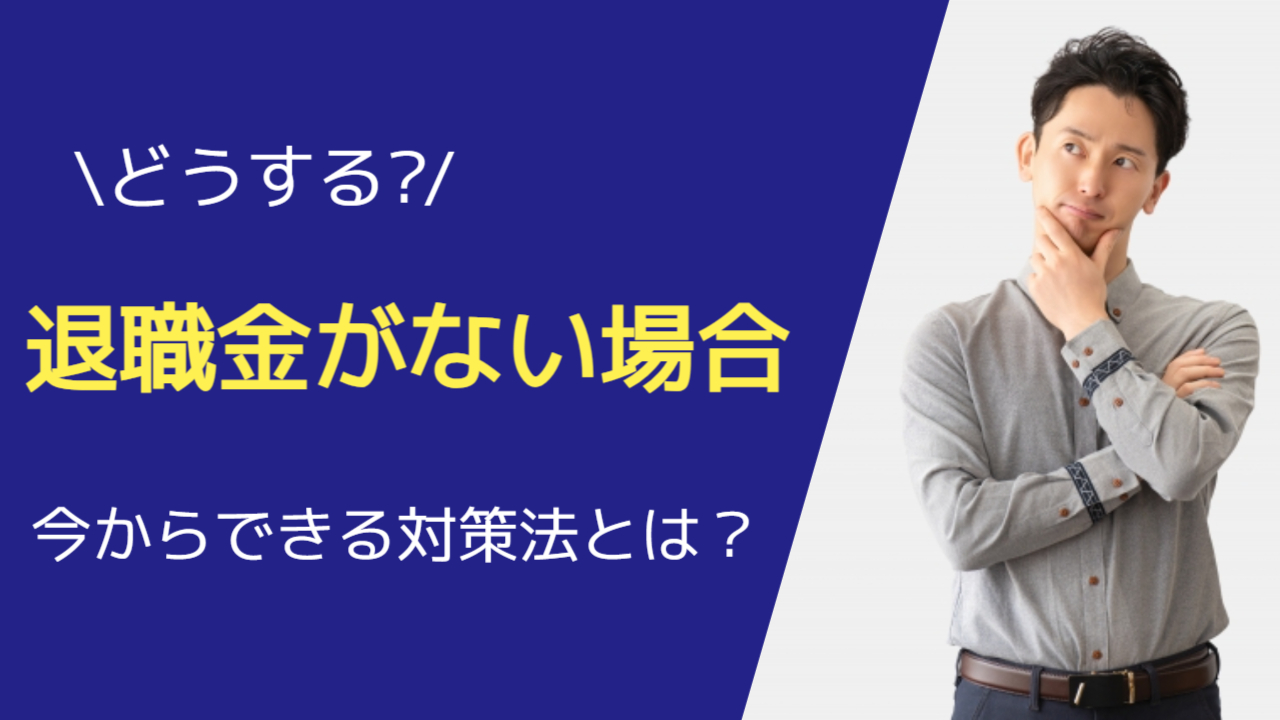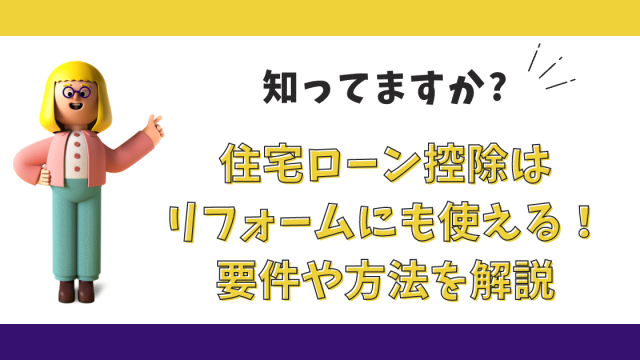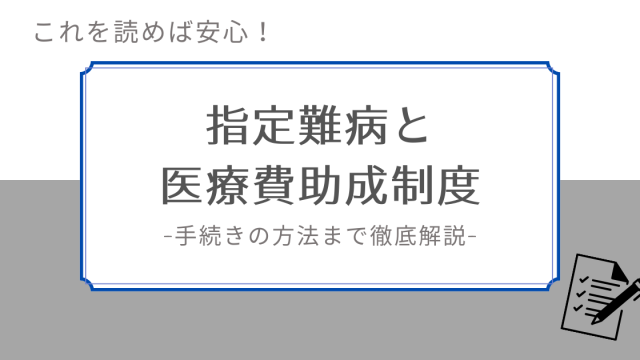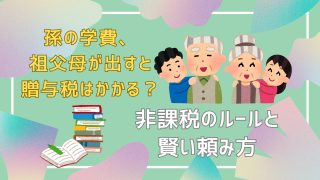「定年まで勤めれば退職金をもらえるのは当たり前」そのように考えている人はまだ多いかもしれません。
しかし現実には、退職金制度がない企業や、制度があっても金額が大幅に減少している企業も増えています。
また、非正規雇用やフリーランスなど働き方が多様化した現代では、退職金がゼロのまま定年を迎える人も少なくありません。
この記事では、退職金がない人・少ない人が老後に向けて今からできる対策を解説します。
退職金制度の現状

かつての日本では、終身雇用と退職金制度がセットで当たり前とされてきましたが、今や状況は大きく変わっています。
退職金制度を導入してる企業の割合は?
厚生労働省が令和5年におこなった調査によると、退職金制度を設けている企業は全体の74.9%でした。
従業員数1,000人を超える大企業では9割以上が退職金制度を導入していますが、小規模な企業では退職金制度を導入していないケースも多く見られます。
企業のコスト削減による理由以外にも、終身雇用制度の見直しや雇用形態の多様化、転職の一般化など、さまざまな要因が考えられます。
退職金制度の種類
退職金にはさまざまな制度がありますが、大きく分けて「退職一時金」と「企業年金」の2つの種類があります。
まずはその違いと種類についてみてみましょう。
退職一時金
一般的に「退職金」といってイメージするのがこの退職一時金ですね。
退職一時金は、企業が独自に積み立てた金額を、退職時に一括で受け取る制度です。
内容は企業ごとに異なりますが、勤続年数や退職時の賃金などによって計算され支給されます。
企業年金
企業年金は退職時に一括で受け取る方法と退職後に一定期間または終身で年金として分割受給する方法があります。
公的年金にプラスして受け取れるため、老後の安定的な生活資金を支える大きな柱になります。
【企業年金の主な種類】
- 企業型確定拠出年金(DC)
- 確定給付型企業年金(DB)
- 中小企業退職金共済制度
- 厚生年金基金(※現在は事実上廃止)
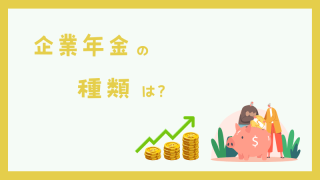
退職金が出ない働き方(非正規・フリーランスなど)
パートやアルバイト、契約社員といった非正規雇用では、そもそも退職金制度が用意されていない場合がほとんどです。
また、フリーランスや個人事業主にも退職金制度がないため、自分で計画的に備える必要があります。
退職金がない場合の老後生活への影響

退職金がない、または少ない場合、老後にどのような影響があるのでしょうか。
それは「老後の生活費が足りなくなるリスクが高まる」という点です。
退職金は、定年後の生活資金として使われる大切な蓄えです。
すでに十分な資産があれば問題ありませんが、そうでない場合は年金を頼りに生活を成り立たせなければならず、現役時代と同じ生活水準を保つのは難しくなります。
「退職金がないから、年金や預貯金だけでは足りないかも」と不安を感じたら、早めに対策を考え、行動を始めましょう。
老後の生活費はいくら必要?
「老後の生活費」と一口に言っても、必要な金額は人それぞれです。
なぜなら、どんな暮らしをしたいかによって支出の総額が大きく変わるからです。
総務省が令和6年におこなった「家計調査報告」によると、65歳以上夫婦のみの無職世帯の平均的な生活費は月およそ26万円でした。
しかし、これはあくまで平均値です。
趣味や旅行を楽しみたいのか、最低限の生活でよいのか、持ち家か賃貸か、介護費用はどの程度見込むか。
こうしたライフスタイルの違いによって、老後の必要資金は大きく異なります。
「退職金がない」とわかったときは、まずは自分がどんな老後を送りたいのかを具体的に思い描き、そのためにいくら必要なのかを試算してみましょう。
目安がわかれば、今後の資金準備の計画も立てやすくなります。

退職金がない場合の老後資金対策

では退職金がない場合、どう備えれば安心して老後を迎えられるのでしょうか。
ここでは、現役世代が実践できる2つの方法「iDeCo」と「NISA」について解説します。
個人型確定拠出年金(iDeCo)で積み立てる
iDeCo(イデコ)は、自分で年金を積み立てて運用できる私的年金制度です。
掛金は全額所得控除の対象となり、所得税・住民税の負担を軽減できるため、節税しながら老後資金を積み立てられる点が大きなメリットです。
掛金の上限は職業によって異なり、自営業者の場合は月額68,000円、会社員で企業年金がない場合は月額23,000円など、働き方に応じた範囲で積み立てられます。
(掛金の上限額は今後さらに引き上げられる予定です)
また、運用益も非課税で再投資されるため、長期的に複利の効果を活かして資産を増やせます。
ただし、原則60歳まで引き出せないため、緊急資金とは分けて積み立てることが重要です。
NISAで長期・分散投資を始める
2024年から新しく始まった「新NISA」は、従来のNISAよりも非課税投資枠が拡充され、誰でも長期的な資産形成がしやすくなった制度です。
新NISAは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがあり、年間最大360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)まで投資でき、非課税保有限度額は生涯1,800万円までとなっています。
NISAは運用益が非課税となるため、預貯金だけでは増えにくいお金を効率よく育てられる強力な手段です。
またNISAの場合、資金が必要になったタイミングでいつでも引き出すことが出来るなど、自由度が高いのも特徴です。
まずは必要資金を把握しよう
まずは「老後にいくら必要なのか」「公的年金でどのくらい賄えるのか」を知ることが第一歩です。
足りない分がわかれば、iDeCoやNISAをどのくらい活用すべきなど具体的な目安が立てられます。
とはいえ「いったい何から始めればいいのだろう?」「NISAではどんな商品を選べばいい?」そのような疑問を持たれる方も多いかもしれません。
そんなときはぜひFPオフィスあしたばにご相談ください。
経験豊富なファイナンシャルプランナーが老後資金のお悩みについてアドバイスさせていただきます。
まとめ
退職金がないと聞くと、不安を感じるのは当然です。
しかし、iDeCoやNISAを活用すれば、自分で退職金代わりの資産を積み立てることができます。
大切なのは「いつかやる」ではなく、「すぐに始める」こと。
税制優遇を賢く活かし、時間を味方につけて、コツコツと資産を育てていきましょう。
未来の自分の安心のために、今日からできる一歩を踏み出してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【あしたばライター:藤元 綾子】
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!
↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓