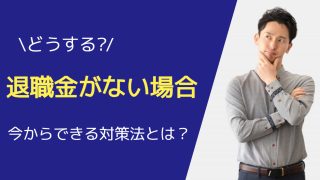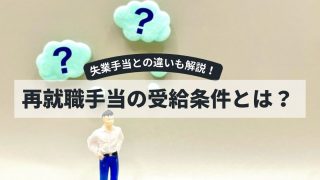毎年の確定申告になると「税金が高くて手取りが少ない」「個人事業主のままでいいか不安」「法人化が難しそうで手が出せない」と感じていませんか。
こうした悩みや負担を減らす方法の1つに「マイクロ法人」という選択肢があります。
マイクロ法人とは、従業員を雇わずに代表者1人で運営する小規模な法人です。
節税や社会保険料の削減効果が期待できるため、状況に合わせて正しく設立することで手取りを最大化できる選択肢になります。
この記事では、基本的な仕組みから設立すべきかどうかの判断基準、さらには法人の作り方まで網羅的に解説しているため、最後まで確認していきましょう。
マイクロ法人とは?個人事業主や一般法人との違い
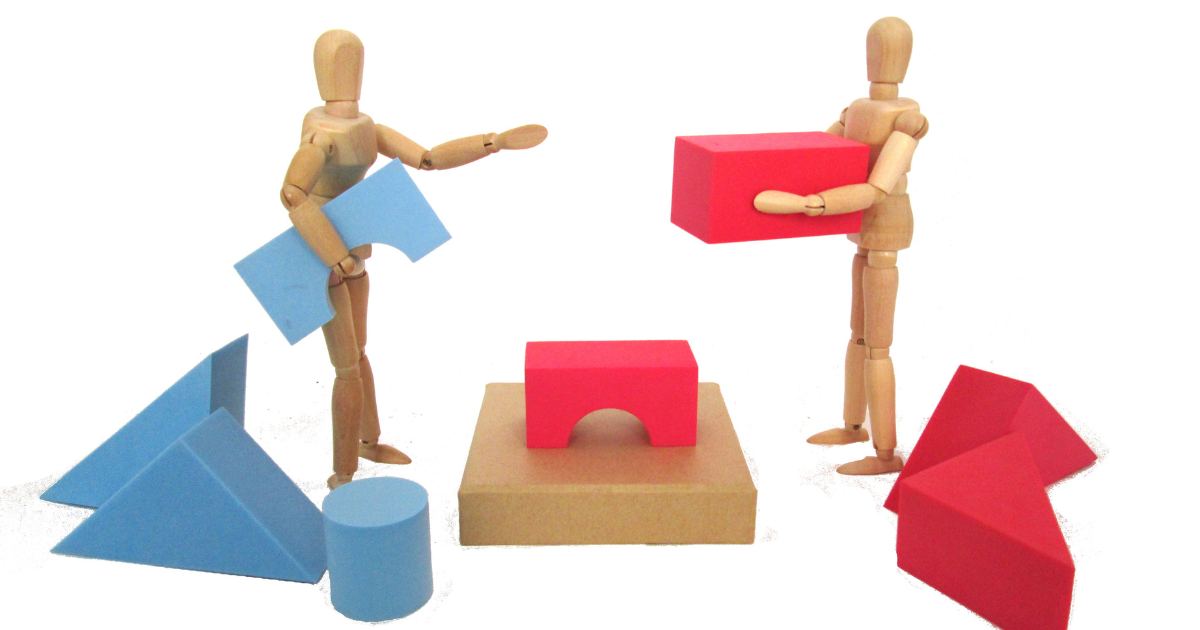
事業を行う際の形態として大きく分けると「個人事業主」「一般的な法人」「マイクロ法人」の3つに分けられます。
税金の仕組み、設立手続き、事業運営の方法などが異なるため、自分の事業規模や目的に合った形態を選ぶことが重要です。
マイクロ法人は、個人事業主と一般的な法人の中間的な位置づけにあり、小規模事業者にとって税務上のメリットを得やすい選択肢として注目されています。
まずはそれぞれの基本的な特徴と違いを理解しておきましょう。
マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、法律で定められた正式な会社形態ではなく「社長一人」または「家族のみ」で事業を行う小規模な会社を指す俗称です。
設立する際は会社法に基づき、株式会社か合同会社のどちらかを選択しなければなりません。
マイクロ法人では、一般的な法人のように事業規模の拡大を目指すのではなく、役員個人の手取り額を最大化することを重視する特徴があります。
個人事業主との違い
個人事業主とマイクロ法人の最も大きな違いは「税金」と「社会保険」の仕組みです。
個人事業主の場合、事業で得た所得全体に対して所得税や住民税、国民健康保険料が計算されます。
一方、マイクロ法人では、会社の「役員」となることから、会社から支給されるのは「役員報酬」です。
役員報酬には、税金を計算する上で有利な「給与所得控除」が適用されます。
社会保険も国民健康保険から切り替わり、役員報酬の金額を基準に保険料が決まるため、報酬額を調整することで社会保険料の負担をコントロールしやすくなるでしょう。
この点が、法人化による最大のポイントです。
一般的な法人との違い
マイクロ法人と株式会社や合同会社など一般的な法人は、法律上の区分は同じであるものの、設立の「目的」が大きく異なります。
一般的な法人は、株主や投資家のために利益を最大化し、従業員を雇用して事業規模を拡大するなど、会社の成長を優先するのが基本です。
一方、マイクロ法人の主な目的は、事業拡大よりも「役員である個人の手取り額の最大化」にあります。
会社を成長させるよりも、社会保険料の最適化や税制上のメリットを活用し、個人の資産形成を効率化することに重きを置くのが特徴です。
マイクロ法人設立のメリット

マイクロ法人を設立することで得られるメリットは主に5つです。
最も大きなメリットは税務面での優遇で、個人事業主と比べて所得税・住民税の節税効果や社会保険料の削減が期待できます。
また、法人格を持つことで社会的信用が向上し、経費として認められる範囲も広がります。
さらに所得分散による節税効果も活用でき、総合的な手取り収入の増加につながる可能性もあるため、これらの詳細を見ていきましょう。
社会保険料の節約
マイクロ法人設立における最大のメリットが、社会保険料の負担を大きく軽減できる点です。
個人事業主が加入する国民健康保険の保険料は前年の所得に応じて決まるため、所得が高いほど負担も増えます。
一方、法人の役員として加入する健康保険・厚生年金などの社会保険料は、会社から受け取る役員報酬の金額に基づいて算出されます。
この仕組みを利用して、役員報酬をあえて低く設定すれば、保険料の算定基準額そのものを低く抑えることが可能です。
事業全体の利益が高くても、個人の社会保険料負担を最小限にコントロールできる点が、法人化を検討する上で最も大きな動機となるでしょう。
所得税・住民税の節税
法人化による節税の大きなポイントは、所得税・住民税の計算方法が変わることです。
個人事業主にはない「給与所得控除」が適用される点がメリットといえます。
個人事業主の場合、課税対象は「売上-経費」で算出される事業所得です。
一方、法人から受け取る役員報酬は「給与所得」扱いとなり、その収入額に応じて一定額を差し引ける「給与所得控除」が認められます。
給与所得控除額は多くの場合、青色申告特別控除(最大65万円)よりも大きくなる場合が多く、結果として課税される所得金額の圧縮が可能です。
そのため、所得税および住民税の負担が軽減されるという仕組みによって、節税が期待できます。
社会的信用の向上
法人格を持つということは、個人事業主と比較して社会的な信用が高まるというメリットがあります。
法人を設立すると、商号、本店所在地、資本金、役員などの情報が法務局に登記され、誰もが閲覧できるようになります。
情報の公開性も含め、取引先や金融機関からの信頼につながるといえるでしょう。
具体的には、金融機関からの融資審査で有利に働くことなどが挙げられます。
また、企業によっては与信管理の観点から個人事業主を避け、法人格を持つことを取引条件とするケースも少なくありません。
さらに、オフィスの賃貸契約など、各種契約がスムーズに進む場合もあります。
直接的な節税効果とは異なりますが、この社会的信用の向上は、事業の基盤を強化し、活動の幅を広げる上で大きなメリットです。
経費の範囲が広がる
法人になると、個人事業主のときよりも経費として認められる範囲が広がります。
具体的には、法人の利益を圧縮し、結果的に法人税の節税につなげることが可能となるからです。
最も代表的な例は、自分自身に支払う「役員報酬」といえるでしょう。
個人事業主では自分への給与は経費にできませんが、法人では最大の経費となります。
その他にも、自宅を法人が借り上げる「社宅」として家賃、退職金準備として役員退職金に対する損金算入、一定の条件を満たす生命保険料も経費にすることが可能です。
このような項目は、個人事業主では経費として認められないものも多いですが、法人にすることで範囲を拡大できます。
所得分散による節税
法人化は、家族に役員報酬を支払うことで世帯全体の所得を分散し、税負担を軽減できるでしょう。
日本の所得税は、所得が高いほど税率も高くなる「累進課税」です。
そのため、一人が高額な所得を得るよりも、複数人に所得を分散させた方がそれぞれに適用される税率が低くなり、結果として世帯全体の納税が低く抑えられます。
例えば、事業を手伝っている配偶者や親族を役員とし、働きに見合った役員報酬を支払うことで所得を分散することが可能です。
さらに、役員報酬を受け取る人それぞれに「給与所得控除」が適用されるため、課税対象となる所得をより効果的に圧縮させられます。
マイクロ法人設立のデメリットと注意点

マイクロ法人にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。
中でも、金銭的なコストと事務的な負担が増える点は、設立前に必ず理解しておくべきでしょう。
特に法人の経理業務は個人事業主よりも複雑で、税理士への依頼費用も発生する可能性があります。
設立を検討する際は、これらのデメリットとメリットを比較して、慎重に判断することが大切です。
設立費用・維持費がかかる
マイクロ法人を設立する際には、株式会社なら約20万〜30万円、合同会社であれば約10万円の設立費用が発生します。
主な設立費用の内訳は以下の通りです。
| 株式会社 | 合同会社 | |
| 登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
| 定款認証手数料 | 3~5万円 | 不要 |
| 収入印紙代 | 4万円(紙の定款の場合のみ) | 4万円(紙の定款の場合のみ) |
さらに、法人を維持するための年間費用も発生します。
法人住民税の均等割が最低7万円、決算申告を税理士に依頼する場合は年間15万〜30万円程度の費用です。
これらの費用を考慮すると、少なくとも年間のランニングコストが必要になるため、節税効果がこの金額を上回るかどうかが判断のポイントになります。
経理・申告業務が複雑
マイクロ法人を設立すると、個人事業主のときよりも経理業務や事務手続きに手間がかかります。
個人事業主は年に1回の確定申告で済みますが、法人の場合は個人事業主よりも複雑な決算申告を行わなければなりません。
たとえば、マイクロ法人を株式会社で設立する場合、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書などの書類作成・提出が必要です。
また、従業員がいないマイクロ法人でも、代表者への役員報酬について給与計算や年末調整などの手続きが必要となります。
書類作成には専門知識が求められるため、多くの場合は税理士に依頼することになるでしょう。
自分で対応できない場合は年間15万〜30万円程度の税理士費用が発生する点も考慮が必要です。
法人住民税の支払いが増える
法人を設立すると、たとえ利益が赤字でも「法人住民税の均等割」を支払わなければなりません。
均等割の金額は資本金等の金額に応じて決まり、たとえば資本金1,000万円以下のマイクロ法人の場合は、最低でも年間7万円を納める必要があります。
内訳は都道府県民税均等割2万円と市町村民税均等割5万円の合計です。
この7万円の均等割は事業の収益に関係なく、法人が存続している限り毎年支払う義務があります。
一方、個人事業主の住民税均等割は合計5,000円です。
つまり、赤字の個人事業主がマイクロ法人を設立すると、住民税の負担が年間約6万5千円増加するため、固定コストが経営の負担となる可能性があります。
マイクロ法人を設立した後の注意点
マイクロ法人設立で注意すべき最大のポイントは、事業実態のない「ペーパーカンパニー」と見なされ、脱税行為を疑われることです。
節税目的で法人を設立しても事業活動の実態が伴わなければ、税務署からは単なる所得隠しや架空経費計上のための手段と判断されかねません。
そうなると、マイクロ法人の設立行為は正当な節税ではなく、意図的な脱税と見なされてしまいます。
疑いを避けるためにも、事業の実態を客観的に証明することが不可欠です。
Webサイトでの事業内容の公開、取引先との契約書や請求書、事業用口座での入出金履歴など、第三者が見ても活動していることが分かるようにしておきましょう。
マイクロ法人の設立方法・手順
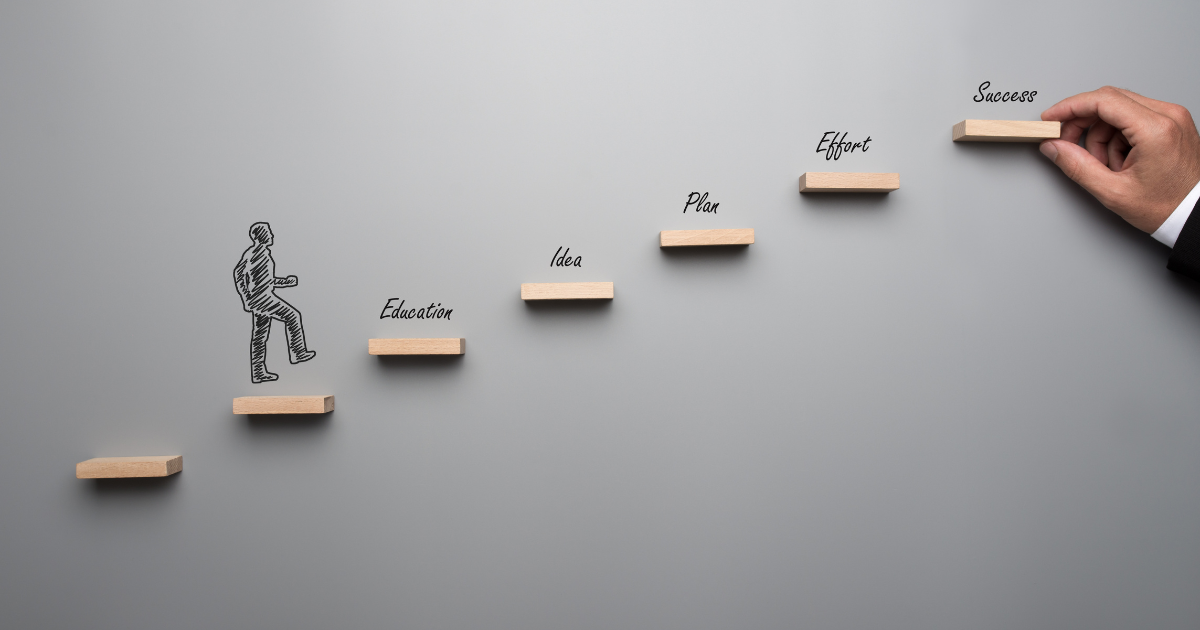
マイクロ法人を設立するには、株式会社や合同会社などの会社形態を選び、法務局で法人登記する必要があります。
設立は複数のステップに分かれており、適切な準備と手続きが重要です。
以下で設立に必要な手続きを詳しく見ていきましょう。
会社概要の決定
マイクロ法人の設立には、まず会社の概要を決める必要があります。
主な検討項目は以下の通りです。
- 目的:事業内容
- 商号(社名):法人名
- 本店所在地:自宅やレンタルオフィスなどの場所
- 形態:株式会社や合同会社などの法人の種類
- 資本金:1円以上
会社名を決める際は、他社が商標登録している名称と重複しないよう「特許情報プラットフォーム」などで事前にチェックしておきましょう。
また、会社の住所は自宅でも問題ありませんが、プライバシーを重視する場合はバーチャルオフィスの契約も可能です。
なお、上記の項目は定款に記載する必要がありますが、後から変更すると手続きや費用が別途かかるため、定款作成前に決めておくことをおすすめします。
実印の作成
会社の概要が決まったら、法人用の実印を作成しましょう。
実印は、法務局への登記申請や今後会社として交わす重要な契約書などで使用するため、会社の意思決定を証明する極めて大切なものです。
法人用の印鑑は「実印」「銀行印」「角印」の3種類を作成します。
なお、インターネットの印鑑作成サービスなどを利用すれば、数千円程度で数日で作成が可能です。
実印が完成したら、法務局へ「印鑑届書」を提出して登録を行い、登録が完了して初めて法人の印鑑として公的な効力を持つことになります。
なお、合わせて代表者個人の実印も必要になるため、同時に作成しておきましょう。
定款の作成と認証
会社の基本ルールを定めた「定款」の作成が必要です。
会社の憲法とも呼ばれる重要な書類で、法人登記に不可欠な重要書類といえます。
定款には、先に決めた商号、事業目的、本店所在地などを記載しなければなりません。
日本公証人連合会のウェブサイトにある雛形などを参考に作成できますが、専門的な知識も必要となります。
株式会社を設立する場合、作成した定款を公証役場に持ち込み、その内容が法的に正しいことを証明してもらう「認証」という手続きが必須です。
認証手続きには約5万円の手数料がかかります。
一方、合同会社の場合はこの定款認証が不要なため、設立費用と手間を抑えることも可能です。
資本金の払込み
定款の準備ができたら、次に資本金を払い込みましょう。
資本金は会社の元手となる資金で、1円以上の金額から設定可能です。
この時点ではまだ法人口座は作れないため、発起人と呼ばれる設立する人の個人口座に、発起人自身の名前で資本金額を振り込みます。
口座残高を資本金額に合わせるのではなく、この「振り込む」という行為が重要であるため注意が必要です。
例えば、資本金が100万円なら口座に100万円を振り込み、振り込みが完了したら通帳の表紙・1ページ目・該当の振込履歴が記載されたページをコピーします。
コピーした書類が資本金を払い込んだことの証明書となり、後の登記申請でも必要になるため、忘れずに準備しておきましょう。
登記申請書作成と申請手続き
必要な準備が整ったら、いよいよ法務局へ会社の設立を申請する「登記」の手続きに移ります。
登記申請書を作成し、準備した定款、資本金の払込証明書、役員の就任承諾書、印鑑届出書など、必要な書類一式を揃えましょう。
各書類の様式は法務局のウェブサイトからダウンロードが可能です。
必要書類が揃ったら、本店所在地を管轄する法務局へ提出します。
提出方法は、窓口への持参、郵送、オンライン申請のいずれかです。
書類に不備がなければ、提出から10日ほどで登記が完了し、会社が正式に成立します。
なお、手続きなどに不安があれば、司法書士に代行を依頼するのも一つの方法です。
登記簿謄本と印鑑証明書の受け取り
登記が完了したら、会社の存在を公的に証明する書類である「登記簿謄本(登記事項証明書)」と「印鑑証明書」を取得しましょう。
登記簿謄本は、法人の名称、所在地、役員などの登記情報が記載されたもので、法務局で取得できます。
印鑑証明書は、登録した法人実印が本物であることを証明するもので、こちらも印鑑カードを利用して法務局での取得が可能です。
書類は、法人口座の開設、融資の申し込み、事務所の賃貸契約、行政への届出など、会社として活動する上で様々な場面で提出を求められます。
登記が完了したら、すぐに何部か取得しておくと、その後の手続きがスムーズに進むでしょう。
各種行政への手続き
法務局での登記が完了したからといって、設立手続きが終わるわけではありません。
税務署や都道府県、市区町村など、各種行政機関への届出が必要です。
まず、税務署に「法人設立届出書」を提出します。
その際、青色申告の承認を受けたい場合は「青色申告の承認申請書」も一緒に提出しましょう。
給与を支払う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」も必要です。
さらに、都道府県税事務所と市区町村役場にも、それぞれ法人設立の届出を行います。
役員に報酬を支払い社会保険に加入する場合は、年金事務所で社会保険の加入手続きも必要です。
各種届出を終えて、ようやく会社運営のスタートラインに立てるといえるでしょう。
まとめ
マイクロ法人は、従業員を雇わずに代表者1人で運営する小規模な法人です。
個人事業主と比べて所得税・住民税の節税効果や社会保険料の削減が期待できる一方で、設立費用や維持費、経理業務の複雑化といったケースもあります。
そのため、年間の節税効果が設立・維持費用を上回るかどうかが判断の重要なポイントです。
なお、設立手順は複数のステップに分かれており、適切な準備と知識が必要であるため、不安な場合は専門家への相談も検討が必要となります。
マイクロ法人の設立は、将来の事業展開や家計全体を見据えた重要な判断であり、メリット・デメリットを十分に理解したうえで最適な選択をしましょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!