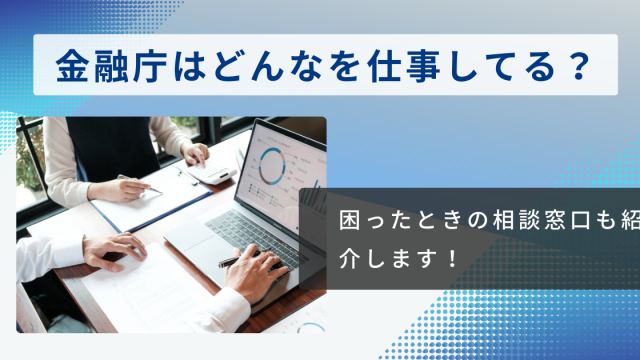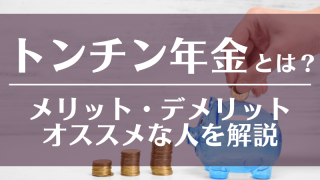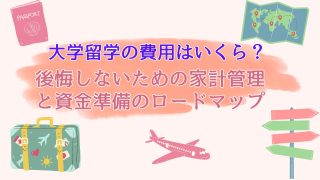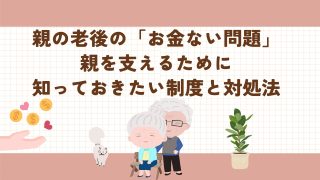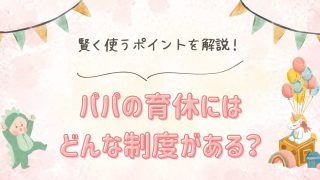国民年金への加入は、20歳以上のすべての国民に義務付けられています。しかし、収入の少ない大学生にとって、国民年金保険料の負担は大きく感じられるかもしれません。
本記事では、大学生が国民年金をどう扱うべきかについて、特例制度や親が払う場合のポイントを解説します。自分に合った納付方法を見つけて、将来のために年金についてしっかり考えてみましょう。
・国民年金の基本ルール
・大学生の国民年金保険料、どうする?
・大学生が利用できる国民年金の特例制度とは?
・親が代わりに払う場合のポイント
・大学生の年収の壁が103万円から150万円へ!
・まとめ:大学生の国民年金、特例制度や親のサポートを賢く活用しよう
国民年金の基本ルール

大学生の国民年金納付について
国民年金は、20歳以上のすべての国民に加入義務がある日本の公的年金制度です。これは学生であっても例外ではありません。
国民年金を納付することで、将来年金を受け取ることができるほか、万が一の遺族年金や障害年金を受給することも可能になります。
未納の場合のリスクとは?
国民年金保険料は、納付期限から2年以内に納めなければ未納扱いとなってしまいます。
国民年金を納付していないと、将来の受給額が減少するだけでなく、障害年金や、遺族年金が受給できない可能性もあります。
納付が難しい場合は「特例制度」を申請するなど、未納状態にならないように注意しましょう。「特例制度」については後ほど詳しく解説します。
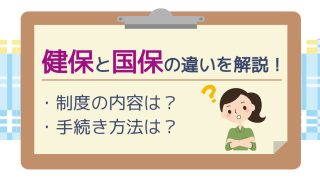
大学生の国民年金保険料、どうする?

保険料はいくら?負担の現実
国民年金保険料の金額は毎年見直しがおこなわれていますが、年収に関わらず負担額は一律です。
なお、令和6年度(令和6年4月~令和7年3月まで)は月額約16,980円、令和7年度(令和7年4月~令和8年3月まで)は月額17,510円となっています。
この金額は、アルバイト収入しかない学生にとっては大きな負担です。とくに自宅外で生活している学生や、学費を自分で支払っている学生にとっては、経済的な負担感が非常に大きいと考えられます。
支払いが厳しい場合の選択肢
収入が少なく保険料を負担することが難しい学生には、以下の選択肢があります。
- 「学生納付特例制度」を利用する
在学中の保険料支払いを猶予できる制度です。卒業後に追納することで、猶予期間中も保険料を支払ったとみなされるため、将来の受給額への影響を抑えられます。 - 親や家族に支払いをサポートしてもらう
親や家族が代わりに支払うことで、学生本人の経済的負担を軽減できます。さらに、親が支払った場合は、保険料の全額が控除を受けられるメリットもあります。
「学生納付特例制度」や「親が払う場合」については、次の章で詳しく解説していきます。
大学生が利用できる国民年金の特例制度とは?

学生納付特例制度の概要
学生納付特例制度は、大学生や専門学校生など、一定の条件を満たす学生が対象です。
この制度を利用することで、在学中の保険料支払いが猶予されます。
学生納付特例制度は、保険料の納付の猶予を受けていた期間は受給資格期間に含まれますが将来受け取る年金額には反映されません。
そのままでは将来受け取る年金が減ってしまいますが、後から追納することで年金額を満額に近づけることが可能になります。
対象者
- 大学(大学院)、短期大学、特別支援学校、専修学校及び各種学校など(※一部適用対象外の学校もあり)に在学していること
- 特例を受ける前年の所得が一定額以下であること(学生本人の所得)
※前年の所得の目安<128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等>
申請できる場所
- 住民票のある市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
- 年金事務所
- 在学中の学校など
申請に必要なもの
- 申請書
- 学生証
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書・年金手帳のコピーなど
学生納付特例制度を利用する際の注意点
猶予された保険料は将来的に追納することが可能です。
ただし追納は猶予期間から10年以内に行わなければなりません。
また、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されるので、その点には注意しておきましょう。
学生納付特例制度について詳しくはこちらをご参照ください。
参照:日本年金機構「国民健康保険の学生納付特例制度」
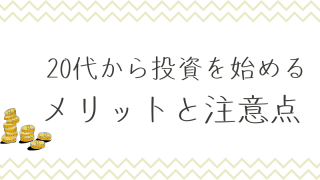
親が代わりに払う場合のポイント

そもそも親が支払うことは問題ないの?
親が、学生である子どもの国民年金を支払うことは可能です。
国民年金を親が代わりに支払ったとしても贈与税はかからないので問題ありません。
また、親が支払った保険料は「全額」社会保険料控除の対象になるため、親の節税としても有効な選択肢となるでしょう。
親が支払うケースのメリット
【学生本人の経済的負担を軽減できる】
学生自身で支払いをする場合、アルバイト収入の多くを保険料に充てなければならず、生活費や学費が圧迫されることがあります。親が代わりに支払うことで、学生の経済的負担を大幅に軽減でき、安心して学生生活を送ることができるでしょう。
【将来追納する必要がなくなる】
学生納付特例制度を利用すると支払いを猶予することができますが、将来の年金受け取り額を減らさないためには、猶予期間中の保険料はあとから追納しなければいけません。
親が代わりに支払うことで追納を避けることができ、将来の経済的な負担を軽減できます。
【親の節税効果が期待できる】
国民年金保険料を親が支払う場合、その「全額」が社会保険料控除の対象になります。
この控除により、親の税負担が軽減されるため、年末調整や確定申告の際には忘れずに申告しましょう。社会保険料控除が受けられるのは、国民年金保険料を支払った日が該当する年です。
親が支払うケースの注意点
子どもが就職したら保険料が重複する
国民年金保険料には、まとめて支払うことで、割引が受けられる「前納」の制度があり、子どもの保険料を代わって支払う場合にも、使うことができます。
もしこのように「前納」で保険料を支払っていた場合、子どもが就職して社会保険に加入した際に、国民年金保険料と厚生年金保険料が重複する可能性があります。
そのため、子どもが就職するタイミングで支払いを見直すことが重要です。
もしも重複して保険料を払ってしまった場合は、日本年金機構から「還付請求書」という書類が届きます。届いた書類に必要事項を記入して返送するだけで、重複分は返ってくるので、手続きを忘れないようにしましょう。
大学生の年収の壁が103万円から150万円へ!

最後に、学生のアルバイト収入に関する制度についても触れておきましょう。
大学生の中にはアルバイトで収入を得ている人も多いと思いますが、これまで親の扶養控除の対象になるのは「給与年収103万円以下」とされていました。
しかし2025年度税制改正大綱で「特定親族特別控除」が新設され、19歳から22歳までの扶養親族については、2025年以降「給与年収150万円以下」に引き上げられることになりました。
これにより今まで年間収入を103万円以内にするために勤務時間を減らしていた学生も、もっと働けるようになります。
学生ですから当然学業を優先するべきではありますが、この改正をメリットに感じる人も多くいるでしょう。
なお、年収150万円を越えた場合でもすぐに扶養控除の額がゼロになるのではなく、控除額が段階的に減少する仕組みとなっています。
今回の改正で103万円の壁については解消されますが、親の健康保険の被扶養者となれる要件の年収はこれまでと変わらず「130万円以下」のままなので注意しましょう。
まとめ:大学生の国民年金、特例制度や親のサポートを賢く活用しよう

大学生にとって国民年金は負担に感じられるかもしれませんが、特例制度や親のサポートを活用することで、その負担を軽減できます。
将来のために年金について考えることは重要です。自分に合った支払い方法や制度を利用し、安心できる老後を目指しましょう。また、学生時代に年金について知識を深めることが、社会人としての第一歩となるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【あしたばライター:藤元綾子】
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!
↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓