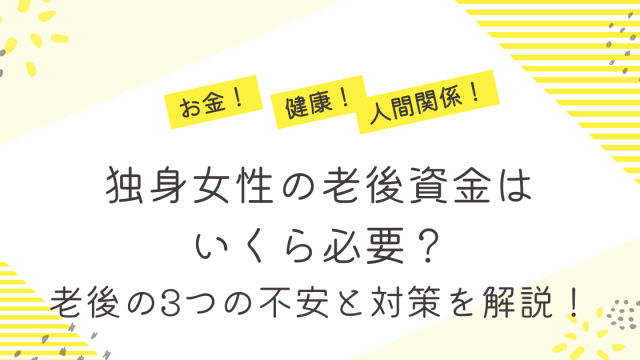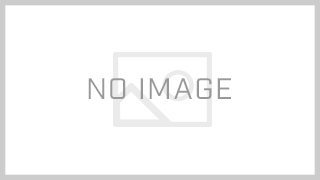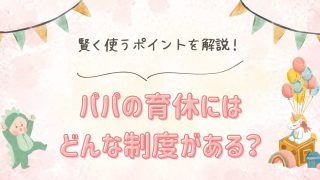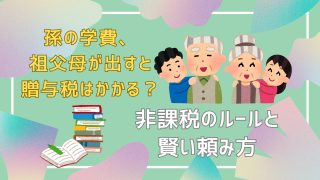近年メディアなどで取り上げられることも多く、広く知られるようになった「終活」という言葉。
ではいったい「終活」とはどのような活動のことをいうのでしょうか?
この記事では、終活の基本的な意味や目的の解説、また「いつ始めればいいのか」「何から手をつければいいのか」などの疑問を解決する具体的な方法5つをご紹介します。
終活の第一歩を踏み出したい方、家族のために備えたい方はぜひ参考にしてください。
終活とは?その目的と必要性を知ろう

終活とは何をすること?
終活とは、「人生の終わりに向けた活動」の略語で、自分の意思を整理し、家族への負担を減らすことを目的とした準備全般を指します。具体的には、エンディングノートの作成、財産の整理、介護・医療に関する希望の明確化、葬儀やお墓の準備、遺言書の作成などが含まれます。
終活は決してネガティブなものではなく、これからの人生をよりよく生きるための前向きな活動なのです。
なぜ終活の準備が必要なのか
終活の目的は、大きく分けて以下の3つです。
家族に迷惑をかけないため
人生の最期は誰にでも訪れるものですが、その時が突然やってくることも少なくありません。もし準備ができていなければ、家族は戸惑い、大きなストレスや負担を抱えることになるでしょう。
例えば、遺言書がないことで相続の手続きが複雑になったり、葬儀の形式や支払いについて揉めたりするケースもあります。
そういった事態を避けるためにも、自分の意思や財産、必要な連絡先などを整理し、残される家族が安心して対応できる状態にしておくことが大切です。
自分の意志を正確に伝えるため
高齢になると、医療や介護の選択肢が増える一方で、判断力や意思の伝達が難しくなる可能性もあります。
そのため、延命治療を望むかどうか、施設介護か在宅介護か、さらにはペットの世話や自宅の処分方法に至るまで、自分の意志を事前に明確にしておくことが必要です。
これにより、家族が迷うことなくあなたの希望に沿った判断をすることができ、後悔やトラブルを避けることができます。
安心してこれからの人生を送るため
終活を通じて「自分がどう生き、どう終わりを迎えたいか」を見つめ直すことは、人生の質を高める大きなきっかけになります。
不安をひとつひとつ取り除くことで、日々の生活に余裕が生まれ、より前向きに、充実した人生を送ることができるでしょう。
さらに、持ち物や人間関係を整理することによって、第二の人生を新たな視点でスタートさせる準備が整います。
- 家族の精神的・経済的負担の軽減
- 自分の希望がしっかりと反映される
- 予期せぬトラブル(相続争いなど)を防げる
- 今後の人生設計がしやすくなる
終活の準備はいつから始めるのがベスト?

年代別に見る「終活を始めるタイミング」
「終活は高齢者がするもの」というイメージが強いですが、終活を始めるのに明確な時期はありません。実際には50代から60代で始める人も増えています。
ここからは、やるべき終活の内容を年代別に分けてみてみましょう。
50代
50代はまだ早いと思われるかもしれませんが、健康で体力のあるうちから始めることで、老後の心配が減り、充実したセカンドライフを送れるメリットがあります。
老後の生活資金や健康面への備えを考慮しながら、断捨離や持ち物の整理を始めたり、エンディングノートの基本構成を把握するなど、出来ることから少しづつ始めましょう。
また、この時期は子どもが独立するなど生活に変化があるケースもあります。保険の見直しをおこなうことも、将来に備えるうえで重要な一歩です。
60代
定年退職など人生の転機を迎えるこの時期は、終活をより具体的に進めるタイミングです。
エンディングノートの記入を始めたり、遺言書の作成について専門家に相談するのもよいでしょう。
また、葬儀の形式やお墓の準備、介護が必要になった場合の希望(在宅介護か施設かなど)についても明らかにしておくと安心です。家族との対話を通じて、自分の意思を共有することも忘れずにおこないましょう。
70代以降
70代は体力や判断力が少しずつ低下してくる可能性があるため、まだ始めていない方は早めに始めることをおすすめします。
すでに始めていた方も、エンディングノートの内容が古くなっていないかなど、これまで進めてきた終活の準備を見直してみてください。
また、デジタル資産の整理やペットの世話のことなど、まだ手を付けていない部分があればできる限り早めに取り組むことが重要です。
終活を始めるきっかけ・タイミング例
終活を始めるきっかけは人それぞれですが、一般的に終活を始めようと思うきっかけは以下のような出来事が多いです。
- 定年退職を迎えたとき
- 体調に不安を感じ始めたとき
- 親の介護や相続を経験したとき
- 子どもが独立したとき
- 終活セミナーやテレビ番組などで興味を持ったとき
体が元気で頭もはっきりしているうちこそ、終活のベストタイミングです。
認知症や急な入院などで意思が伝えられなくなってからでは、家族に大きな負担をかけてしまいます。早めに始めることで、万が一の時にも備えられます。
次からは、具体的な終活の準備を5つのステップに分けてご紹介します。
まずは簡単に始められるところから始めてみましょう。
今すぐできる!終活の準備5つとは?

① エンディングノートの作成
終活の第一歩として最も手軽に始められるのが、エンディングノートの作成です。エンディングノートには以下のような内容を記載します。
- 自分のプロフィール
- 家族へのメッセージ
- 医療・介護の希望
- 財産の一覧(預金口座・保険・不動産など)
- 葬儀・お墓の希望
- SNSやスマホのパスワード管理
これらの内容を明記しておくことで、残された家族が手続きをスムーズにおこなうことができます。
エンディングノートは法的効力がないものの、自分の意志を明確に伝える手段として非常に有効です。
相続に関する内容などを記しておきたい場合は、法的効力のある「遺言書」を作成しておく必要があります。エンディングノートは内容を自由に書くことができますが、遺言書は決められた形式で書かなければいけません。
② 財産・保険・口座の整理
自分の持っている資産を把握しておくことは、終活において重要です。とくに複数の銀行口座や証券口座がある場合、相続人が把握できないことも多いため、明らかにしておきましょう。
- 銀行・証券口座の一覧化
- 不動産の登記情報確認
- 加入している保険内容の整理
- 借金やローンの有無
いざというときに家族が「加入している保険がわからない」「通帳や印鑑の場所がわからない」と困るケースも多いです。これらをリストアップしておくことで、相続手続きもスムーズになります。
③ 医療・介護・延命治療の意思表示
いざという時に備えて、延命治療の可否や介護の希望などを明記しておくことも重要です。エンディングノートや「事前指示書(リビングウィル)※」を使って、自分の意志を家族に伝えましょう。
- 延命措置は希望するか?
- どこで介護を受けたいか?(自宅・施設など)
- 認知症になった場合の対応方針
家族間で話しにくい内容こそ、文章に残しておくことが大切です。
※「事前指示書(リビングウィル)」とは、将来意思表示ができなくなったときに備えて、自身の医療やケアに関する希望(延命治療など)を事前に書面で表明する文書のことです。
④ 葬儀・お墓の希望をまとめる
葬儀の形式や規模、お墓の場所などについても、希望を残しておくと家族は安心して対応できます。
- 葬儀の費用、形式
- 訃報を知らせてほしい人
- 散骨や樹木葬などの希望
最近では、事前に葬儀社と相談する「生前契約」を活用する人も増えています。
⑤ デジタル遺品(SNS・スマホ)の整理
見落としがちなのが、SNSやメールアカウント、スマートフォン、パソコンに残ったデジタル情報の整理です。
- ログイン情報(ID・パスワード)の記録
- SNSやクラウドの削除希望の有無
- デジタル写真やファイルの整理
家族がアクセスできないと、重要な連絡や写真が失われる可能性もあるため、整理しておくことをおすすめします。

まとめ

終活は、最期の準備というだけでなく、自分らしく生きるための活動です。まずはすべてを一気に終わらせようとせずできることから少しずつ始めることが大切です。
終活は「自分のため」であり「家族のため」でもあります。残される家族の安心のためにも、今の元気な自分だからこそできる準備を、今日から始めてみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【あしたばライター:藤元綾子】
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!
↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓