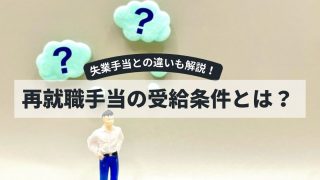不動産を相続したけど「何から手をつけるべきか」「期限や罰則って分からない」「自分でできるのか」といった悩みを抱えていませんか。
2024年4月1日から相続登記は義務化されたため、正当な理由なく放置すると罰則が科される可能性があります。
相続登記の義務化は法改正によって導入されましたが、多くの方にとっては突然の相続にすぐに対応できるものでもありません。
この記事では、不動産の相続登記(名義変更)に対する期限と罰則の基本や放置するリスク、具体的な手続き方法まで分かりやすく解説します。
最後まで読めば相続登記の全体像がわかり、何をすべきか見えてくるため是非最後まで確認してください。
【まず確認】相続登記の義務化|期限と罰則の基本
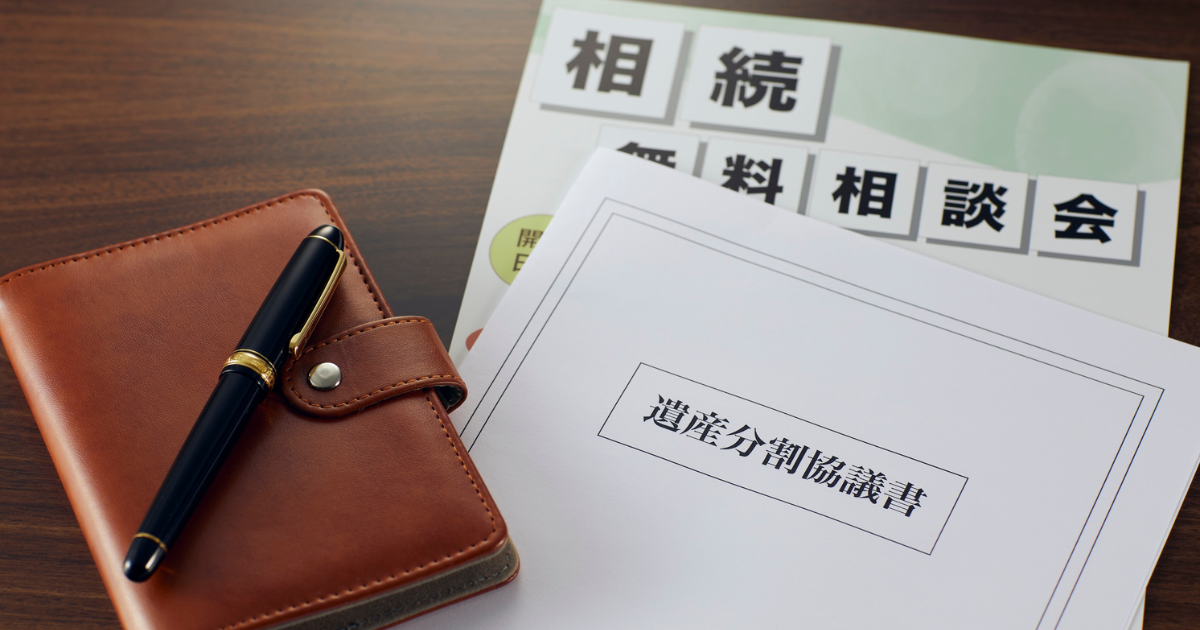
2024年4月1日から相続登記が義務化されたことで、相続を知った日から3年以内に手続きを行わなければ10万円以下の過料が科される場合があります。
義務化された不動産は過去の相続にも適用され、多くの方が今すぐ検討する必要が出てきました。
不動産を相続する全ての方が対象となる重要な制度変更であるため、自身のケースに当てはめながら基本をしっかり押さえていきましょう。
相続登記の期限は「相続を知った日から3年以内」
2024年4月1日、相続登記の申請を「不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に行う必要があると義務化されました。
「3年以内」という期限は所有者が不明な土地問題を解消することが目的で、改正不動産登記法によって定められています。
具体的な期限は以下の通りです。
| 条件 | 期限 |
| 不動産を相続した場合 | 所有権取得を知った日から3年以内 |
| 遺産分割が成立した場合 | 遺産分割が成立した日から3年以内 |
なお、2024年4月1日より前に相続が発生した場合は2027年3月31日までです。
ただし、不動産の取得を知った日または遺産分割成立日が2024年4月1日以降の場合、その日から3年以内のどちらか遅い方までというルールもあります。
期限のルールを間違えないよう相続発生日と遺産分割の状況を整理し、不明な点がある場合は司法書士など専門家に相談しましょう。
期限を過ぎた場合の罰則(10万円以下の過料)とは
相続登記では、正当な理由なく期限が過ぎれば「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
この取り決めは、相続登記の義務化を実効性のあるものにするための罰則規定です。
ただし、やむを得ない事情がある場合のみ過料が免除されます。
免除される可能性があるパターンは以下の通りです。
- 相続人が多数存在し、必要な資料の収集や相続人の把握に時間がかかる場合
- 遺言の有効性や遺産範囲について争いがある場合
- 相続登記申請義務者が重病などの事情を抱えている場合
- DV被害者等で生命・心身の危害が及ぶおそれがある場合
- 経済的困窮により登記申請費用を負担できない場合
実際、過料が科される前には法務局から手続きを行うよう催告があるため、催告に従えば問題ありませんが、正当な理由にあたるかの判断は個別で行われます。
期限内に手続きを終えるのが難しい場合は、放置せず法務局や専門家へ相談することが重要です。
過去の相続も対象?義務化で今すぐ確認すべきこと
相続登記の義務化は、施行された2024年4月1日以降の相続だけが対象ではありません。
法律が施行される以前に発生した相続、且つ登記が済んでいない不動産も義務化の対象に含まれます。
何十年も前に相続した実家などの不動産であっても、名義変更が済んでいなければ今回の義務化からは逃れられないでしょう。
なお、過去の相続についても猶予期間は3年間となります。
具体的な期限は「義務化の施行日(2024年4月1日)」または「自身が相続人であることを知った日」のいずれか遅い日から3年以内です。
つまり、ほとんどのケースで2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があり、期限を過ぎると同様に10万円以下の過料の対象となります。
放置は危険!相続登記をしない場合の6大リスク

相続登記の義務化によって過料という罰則がありますが、本当に気をつけなければならないリスクは他にもあります。
登記を放置することは自身の資産価値を損なうだけでなく、家族にまで影響を及ぼす多くのリスクを抱え込むことになるなど、大変な事態に陥るケースもあるでしょう。
単なる手続きの遅れと軽視せず、将来のトラブルを避けるためにしっかりと内容を理解しておくことが大切です。
リスク1:不動産が売却できない
相続した不動産は、登記しなければ売却できません。
法律上、不動産の所有者を証明する「所有権」は相続と同時に相続人へ移りますが、名義が亡くなった方のままだと法的に証明することができないからです。
不動産取引では、買主は登記簿を見て誰が所有者かを確認しますが、所有権の変更登記をしていないと、登記簿上の所有者と実際の売主が異なるため契約できません。
不動産を適切に処分・活用するためには、名義変更を行うための相続登記が絶対的な前提条件となります。
リスク2:担保にできない
相続した不動産を担保に融資を受けようとしても、相続登記が完了していなければ金融機関は対応してくれないでしょう。
金融機関から融資を受ける場合、基本的には不動産に「抵当権」を設定して融資を受けますが、抵当権設定登記は不動産の所有者でなければ申請できません。
登記簿上の名義が亡くなった方のままでは相続人が法的な所有者として認められないため、抵当権を設定できずに結果として融資は受けられないという事態に陥ります。
仮に、相続した実家をリフォームするためにローンを組みたいという計画があったとしても、相続登記が未了では計画自体が頓挫するでしょう。
不動産を単に所有するだけでなく資産として活用するためにも、速やかに名義変更しておくことが必要です。
リスク3:権利関係が複雑化して子や孫の代に負担を残す
相続登記を放置すると、時間の経過とともに相続人の数が増え続けるため、権利関係が複雑になります。
数次相続や代襲相続により、当初は少数だった相続人が増加することによって、合意形成が極めて困難になるからです。
不動産の相続権は消滅することがなく、相続登記をしないまま相続人が亡くなると、子や孫にも相続権が引き継がれることを「数次相続」や「代襲相続」と呼びます。
たとえば、父親が亡くなり長男・次男が相続したものの、登記しないケースを考えてみましょう。
父親の相続から10年後に長男が亡くなり、長男の配偶者と子2人が相続権を取得します。
さらに10年後に長男の配偶者が亡くなり、配偶者の兄弟2人も関係者となるケースでは関係者が拡大してしまいます。
こうなると、相続人同士の面識もなく、遠方居住や連絡先不明などの問題が重複するため、手続きは極めて困難です。
リスク4:他の相続人に勝手に持分を売却されてしまう
相続財産をまとめるための「遺産分割協議」の内容が決定する前に、他の相続人が自分の法定相続分(持分)だけを第三者に売却してしまう可能性があります。
遺産分割前の不動産は相続人全員が共有している状態となるため、各相続人は自身の持分を自由に処分できる状態です。
仮に、持分が専門の買取業者などに売却されると、全く面識のない他人と不動産を共有することになります。
たとえば、共有者となった業者が持分を買い取るよう要求してくる可能性も否定できません。
防止策として、相続人全員で速やかに遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するのかを明確に定めましょう。
その上で内容に沿った相続登記を完了させることが最も有効な対策となります。
リスク5:相続人の借金で不動産が差し押さえられる
相続人の中に借金を抱えている方がいる場合のリスクは、相続不動産が差し押さえられることです。
相続登記が未了の不動産は、法定相続分に応じて各相続人が権利を持っていると見なされるため、借金を返済しないと差し押さえられるリスクがあります。
債権者は借金の返済が滞ると貸したお金を回収するためであれば、相続登記が未了の不動産に対して裁判所に申し立てた上で財産を強制的に差し押さえることが可能です。
これを「債権者による代位登記」と呼びます。
遺産分割協議で「長男が不動産を相続する」と決めていても、登記を完了させていなければ差し押さえを防げません。
他の相続人の借金トラブルから大切な不動産を守るためにも、遺産分割協議が成立したら一日も早く相続登記の申請が必要です。
リスク6:必要書類が入手困難になる
相続登記を先延ばしにすると、手続きをしようとした時に必要な公的書類が取得できなくなる可能性があります。
役所が保管する書類には保存期間が定められており、期間が過ぎると廃棄されてしまうからです。
たとえば、登記簿上の住所と亡くなった方の最後の住所が異なる場合、その繋がりを証明するために「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要となります。
書類の保存期間は法改正により150年に延長されましたが、改正前である2019年以前はわずか5年と短く、古い相続の場合はすでに書類が廃棄されていて入手できないケースがあります。
書類が取得できないと、代わりに権利証を用意したり、相続人全員から「他に相続人はいない」旨を証明する書類に実印をもらったりするなど手続きが煩雑です。
確実かつスムーズに手続きを終えるためにも、書類が確実に揃う間に行動しましょう。
相続登記の費用はいくら?自分でする場合と司法書士へ依頼した場合の比較

相続登記の手続きを進める上で、多くの方が気になるのが「費用」です。
相続登記にかかる費用は「必ずかかる実費」と「専門家に依頼する場合の報酬」の2種類があります。
「自分で手続きする場合」「司法書士に依頼する場合」それぞれの費用を詳しく理解し、どちらを選ぶべきか判断材料として活用してください。
自分でする場合の費用内訳(登録免許税・書類取得費)
自分で相続登記を手続きする場合、費用は「登録免許税」と「必要書類の取得費」の2種類しか掛かりません。
- 登録免許税
法務局へ登記を申請する際に納める税金です。
| 不動産評価額 | 登録免許税 | 実際の登録免許税 |
| 1,000万円 | 1,000万円×0.4% | 40,000円 |
| 2,000万円 | 2,000万円×0.4% | 80,000円 |
| 3,000万円 | 3,000万円×0.4% | 120,000円 |
| 5,000万円 | 5,000万円×0.4% | 200,000円 |
- 必要書類の取得費
必要書類の詳細費用は以下の通りとなります。
| 書類名 | 手数料 |
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 750円 |
| 住民票・住民票の除票 | 300円 |
| 印鑑証明書 | 300円 |
| 固定資産評価証明書 | 300円 |
※手数料は市区町村によって異なる場合があります。
なお、書類については相続の複雑さにより枚数が変動するため、余裕を持って取得するようにしておきましょう。
司法書士に依頼する場合の費用相場と内訳
相続登記を司法書士に依頼する場合、費用は自分でやる場合の実費(登録免許税・書類取得費)に加えて「司法書士への報酬」が必要となります。
報酬額は事務所や案件の複雑さによって変動しますが、まずは一般的な相場を知っておくことで比較検討できるようにしておきましょう。
| ケース分類 | 基本報酬相場 | 特徴 |
| シンプルなケース (相続人1人、不動産1件) | 5~8万円 | 最も基本的な料金 |
| 一般的な相続登記 | 8~12万円 | 標準的な料金設定 |
| 複雑なケース | 15~25万円 | 数次相続等が含まれる |
報酬には、通常、登記申請書の作成や法務局への申請代行といった基本的な手続きが含まれます。
ただし、戸籍謄本など必要書類の収集を一任する場合や遺産分割協議書の作成を依頼する場合、相続人や不動産の数が複数ある複雑な案件などは報酬が高くなりがちです。
なお、司法書士によっては書類の取得のみでも報酬が必要な司法書士もいます。
少しでも費用を抑えるために、複数の事務所に見積もりを依頼し、サービス内容と費用を比較検討しておきましょう。
司法書士に依頼するメリット
相続登記を司法書士に依頼すると費用はかかりますが、費用を支払う以上に大きなメリットがあります。
中でも最大のメリットは、複雑で手間のかかる手続きをすべて任せられる点です。
| 項目 | 自分で行う場合 | 司法書士に依頼する場合 |
| 法務局への訪問回数 | 平日に3~4回 | 1~2回(相談・完了報告) |
| 手続き完了期間 | 数週間~数か月 | 1~2か月 |
| 不備による再提出リスク | あり(追加時間・費用) | ほぼなし |
| 平日の時間確保 | 必須 | - |
戸籍謄本の収集から遺産分割協議書や登記申請書の作成、法務局とのやり取りまで、専門的な知識が必要な作業を正確かつ迅速に進めてもらえます。
一方、自身で対応する場合はスムーズに進まないことも多く、そのため時間的・精神的な負担が増えるケースも多いでしょう。
なお、司法書士は不動産登記の専門家であるため、複雑な案件にもスムーズに対応できる点も強みです。
相続人の中に行方不明者がいる、前の代の相続登記が未了といった、専門知識のない方では対応が難しいケースでも解決してくれます。
手続きのミスを防ぎ、確実かつ安心して相続登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼を検討する価値はあるといえるでしょう。
4ステップで解説!相続登記(名義変更)手続きの流れと必要書類

相続登記を専門家に依頼する場合でも、全体像を把握しておくことでスムーズに進められます。
主な手続きは大きく分けて「協議書作成」「書類収集」「申請書作成」「法務局への申請」という4つのステップです。
各ステップで何を行うのか、どのような書類が必要になるのかを把握することで、自身で手続きを進める際の参考にもなります。
遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合は「誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するのか」を相続人全員で話し合って決める必要があり、この話し合いが「遺産分割協議」です。
法定相続分とは異なる割合で不動産を相続する場合や、特定の相続人が単独で不動産を相続する場合には、遺産分割協議が欠かせません。
協議で合意した内容は「遺産分割協議書」にまとめておくことで、後の相続登記申請において「なぜその名義変更が行われるのか」を証明する重要な証拠となります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名や実印の押印が必要で、仮に一人でも合意しない相続人がいると協議は成立しないため書面も無効です。
仮に、協議がまとまらないケースでは家庭裁判所での遺産分割調停や審判による解決となりますが、時間と費用がかかるため話し合いでの解決をおすすめします。
必要書類の収集
相続登記に必要な書類は相続した方法によって異なりますが、基本的には被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、不動産関係書類が必要です。
遠方の市区町村からも郵送で取得でき、計画的に進めれば2〜4週間で収集することも可能ですが、相続関係が複雑な場合はより多くの書類と時間が必要になります。
参考として、必要書類の目安を以下の表にまとめました。
| 書類分類 | 必要書類 | 取得場所 | 通数目安 |
| 被相続人関係 | 出生~死亡の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 各本籍地の市区町村 | 5~8通 |
| 住民票の除票または戸籍の附票 | 最終住所地または本籍地 | 1通 | |
| 相続人関係 | 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村 | 人数分 |
| 不動産取得者の住民票 | 住所地の市区町村 | 1通 | |
| 印鑑証明書(遺産分割の場合) | 印鑑登録地の市区町村 | 人数分 | |
| 不動産関係 | 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 | 1通 |
| 登記事項証明書 | 管轄法務局 | 1通(確認用) |
まずは、遺産分割協議書によって相続人を確定させたうえで必要書類の通数を把握することが必要です。
なお、自身で対応する場合は役所などへ足を運んで進めますが、なかなかスムーズに進まないことも多いでしょう。
そのため、自信のない方、複雑な相続関係がある方は、司法書士に書類取得を代行してもらうことも賢明な選択です。
登記申請書の作成
必要書類が一通り揃ったら、次は法務局へ提出するための「登記申請書」を作成します。
登記申請書では、誰がどの不動産をどのように取得したのかを明確にしておくため、正式に申請するためには必要な書類です。
- 不動産の詳細情報(所在、地番、家屋番号など)
- 登記の目的(所有権移転)
- 原因(年月日 相続)
- 相続人の情報など
記載すべき内容は法律で厳格に定められているため、一字一句間違いのないように作成しましょう。
申請書の様式(ひな形)は、法務局のウェブサイトで入手可能ですが、原因によって使用する様式が異なるため注意が必要です。
| 相続パターン | 申請書様式 | 登記の原因 | 主な添付書類 |
| 遺産分割協議 | 所有権移転登記申請書(相続・遺産分割) | 年月日相続、年月日遺産分割 | 遺産分割協議書、印鑑証明書 |
| 法定相続 | 所有権移転登記申請書(相続・法定相続) | 年月日相続 | 戸籍謄本等のみ |
| 遺言 | 所有権移転登記申請書(相続・遺言) | 年月日相続 | 遺言書、検認調書等 |
記載内容に不安がある場合は、法務局の窓口で事前相談を受けることをおすすめします。
法務局への登記申請
作成した登記申請書と収集した全ての必要書類が揃ったら、いよいよ法務局への登記申請です。
申請先の法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局と決まっているため、事前にインターネットなどで管轄を確認しておきましょう。
申請方法は、主に以下の3つです。
| 申請方法 | メリット | デメリット | 適している人 |
| 窓口持参 | その場で不備チェック、即座に修正可能 | 平日日中に法務局まで出向く必要 | 初回申請で不安な方 |
| 郵送申請 | 自宅から申請可能、時間を選ばない | 不備があった場合の修正に時間がかかる | 平日に時間を作れない方 |
| オンライン申請 | 24時間申請可能、手数料減額あり | マイナンバーカード等が必要、完全オンライン完結でない | オンライン取引に慣れている方 |
申請後、書類に不備がなければ1〜2週間程度で登記が完了します。
完了すると、従来の権利証にあたる「登記識別情報通知書」と「登記完了証」が交付されるため、全ての手続きは終了です。
まとめ
2024年4月1日から施行された相続登記の義務化は、相続を知った日から3年以内の手続きが必要となりました。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があるなど、非常に厳しいペナルティもあります。
また、過去の相続についても2027年3月31日までに対応しなければならず、該当する方は早急な対応が必要です。
さらに、放置によるリスクによっては、相続した不動産の売却ができない、借金による差し押さえが発生するケースもあります。
基本的に手続きは煩雑であるため、費用はかかるものの専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。
相続登記は早期の対応が何より重要であり、放置すればするほど問題は深刻化しやすいため、すぐにでも必要な手続きを進めましょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!