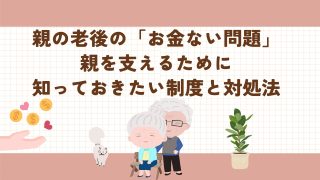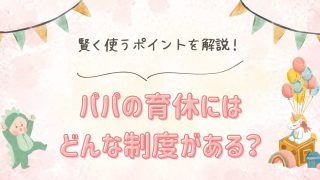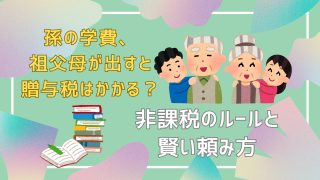学費を教育資金贈与として支援したいけれど、使いきれない分には「贈与税」がかかると聞いて、不安を感じていませんか?
制度を非課税で活用できるとはいえ、30歳時点の状況や贈与者の相続財産、税金に関わる条件が複雑であるため、正しい情報を押さえておくことが大切です。
この記事では、非課税枠1,500万円の基本的な仕組みから令和5年度以降の重要な改正点、使い切れずに残ってしまうことを防ぐための実践的な対策まで解説します。
最後まで読むことで、制度への漠然とした不安が解消されるとともに、ご自身の状況に合わせて活用ができるでしょう。
教育資金贈与の非課税制度とは?仕組みと最新の改正ポイント
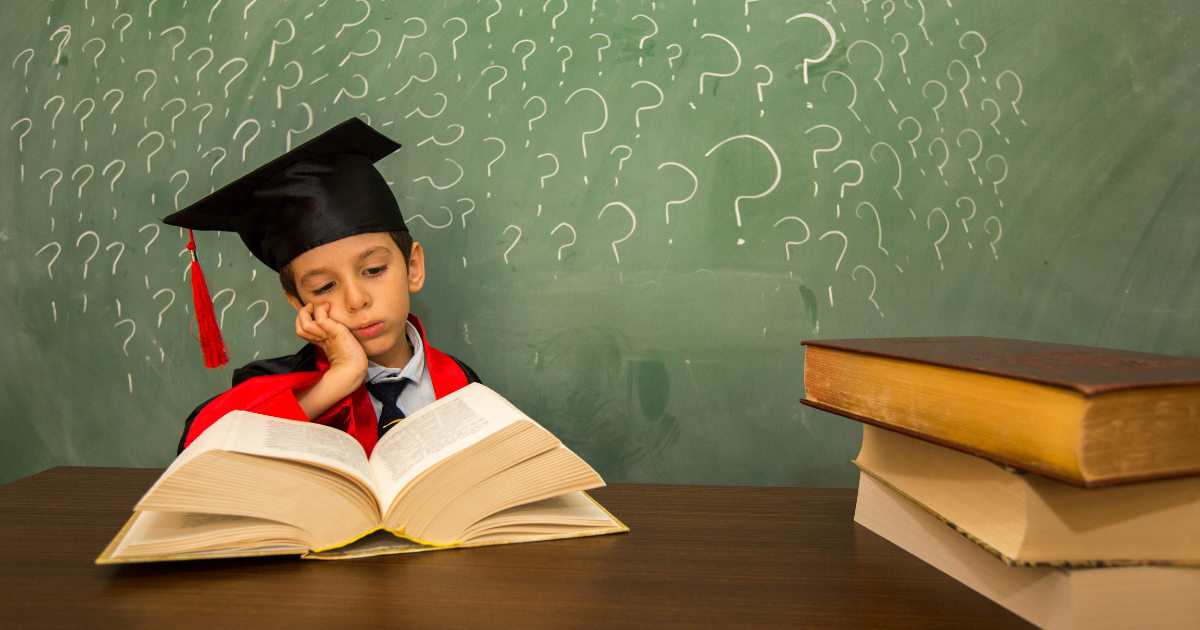
教育資金贈与とは、父母もしくは祖父母が子や孫へ教育費を早期、かつ非課税で支援する制度です。
令和5年度の税制改正によって令和8年3月末まで延長されましたが、一部では残額が相続税の対象となるなどの要件が増えました。
また、契約後は用途外の資金を自由に戻せないなど、最新ルールを理解しておかないと、課税リスクを回避できません。
さらに、税制改正による変更点もあるため、改正内容を踏まえた最新の制度概要を把握しておく必要があります。
1,500万円までの非課税枠と基本的な仕組み
教育資金贈与では、父母や祖父母が30歳未満の子や孫に対する教育資金を贈与する場合、受贈者一人あたり最大1,500万円まで非課税としています。
また、学習塾や習い事など学校等以外の教育サービスでは、最大500万円までが非課税です。
ただし、受贈者が30歳に達した時点で在学していない場合は契約が終了するだけでなく、残高に対して一般贈与と同様の課税が掛かります。
利用するには、信託銀行などの金融機関で専用口座を開設し、教育資金非課税申告書を提出するなどの手続きが必要です。
令和5年度(2023年度)税制改正で変わった重要ポイント
令和5年度(2023年度)税制改正では、主に2つの重要な変更点がありました。
1つ目は、贈与者が死亡した場合の課税です。
従来は、贈与者の死亡時に受贈者が23歳未満であるなどの条件を満たすことで、口座に残額があった場合も相続税はかかりませんでした。
しかし、富裕層の相続税対策としての利用を抑制するため、贈与者の相続税課税価格が5億円を超えると、教育資金の残額は相続税の対象となります。
2つ目は、契約終了時の残額に対する贈与税率の変更です。
従前、契約が終了すると、税率の低い「特例税率」が適用されるケースもありました。
しかし、改正後は残額に対して一律「一般税率」が適用されるため、使い切れない場合の贈与税負担は増加する可能性があります。
教育資金を使い切れないと贈与税がかかる!具体的なケースと税額計算

教育資金贈与では、メリットが大きい制度である反面、使い切れない場合の資金に対して思わぬ税金が課される場合もあります。
例えば、30歳を迎えた時点で学校を卒業している場合、贈与者の生存中に残高がある場合などが対象です。
制度を利用することにより非課税で支援したとしても、最終的に多額の贈与税がかかってしまっては意味がありません。
具体的にどのような場合に贈与税がかかるのか、条件と実際に課税された場合の税額や計算方法について解説していきます。
贈与税がかかる具体的なケース
使いきれない残額に贈与税が課税されるケースは、非課税措置の適用が終了し、一定の条件が揃った場合です。
具体的には、以下の4つの条件がすべて満たされたときに、残額から贈与税の基礎控除額110万円を引いた額に対して贈与税がかかります。
- 受贈者が学校などを卒業した
- 受贈者が満期である30歳になったため教育資金口座契約が終了した
- 受贈者が30歳に達した時点で贈与者が存命である
- 使い切れなかった教育贈与資金が贈与の基礎控除である110万円以上の場合
それぞれのケースに当てはまるかどうかを事前に確認し、後日の課税リスクを回避できるようにしておきましょう。
税金がかかる場合の具体的な計算例
教育資金贈与の残額に贈与税がかかる場合、通常の贈与税と同じ税額がかかります。
契約終了時の口座残額から贈与税の基礎控除額である110万円を差し引き課税価格を計算
↓
課税価格に贈与税の税率を掛けて税額を計算
具体的には、以下の通り計算しましょう。
契約終了時に口座残額が600万円あった場合、基礎控除110万円を引いた課税価格は490万円
↓
一般税率の速算表に基づき、490万円に対する税率と控除額を確認して計算すると、贈与税は82万円
(課税価格490万円×税率30%-控除額65万円 = 82万円)
仮に、残額が110万円以下であれば、課税価格は0円となり贈与税はかかりません。
残額によっては税負担が非常に大きくなるため、一括で贈与する場合には注意が必要です。
※実際の税率・控除額は国税庁の速算表をご確認ください。
| 基礎控除後の課税価格 (贈与額から110万円を差し引いた金額) | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ー |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
これで安心!知っておきたい教育資金贈与で税金がかからないケースとは?

教育資金贈与の残額に対し、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。
贈与税が掛からない、もしくは課税が猶予されるいくつか例外的なケースがあります。
例えば、一定の年齢になっても引き続き教育を受けている、贈与者・受贈者の状況が変化した際に規定が設けられているなどです。
税金が掛からないケースを理解しておくことで制度をより安心して活用できるため、それぞれのパターンをしっかりと確認しておきましょう。
30歳時点で学校在籍中のケース
本来、受贈者が30歳に達した年の年末に教育資金贈与は終了します。
しかし、30歳時点で大学や大学院、専門学校などに在学、もしくは教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている際は、40歳まで延長が可能です。
延長手続きは、受贈者が30歳になるまでに金融機関へ「教育資金管理契約継続届出書」や「在学証明書」などの必要書類を提出する必要があります。
手続きが承認されると、30歳以降も授業料や研究費などの費用は非課税です。
ただし、自動で延長されるわけではないため、必ず自身で手続きをしておきましょう。
万が一、手続きを失念すると在学中であっても30歳で契約が終了し、残額に贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。
40歳までに学校などを卒業したケース
30歳時点で在学中の場合に契約期間を延長したとしても、最長40歳を迎える前には口座内の資金を教育目的で使い切る必要があります。
ただし、延長期間中に学校等を卒業、または教育訓練を修了し、卒業・修了時点で口座残高が無くなっていれば、贈与税はかかりません。
延長後の契約期間が途中であっても、残高がなくなった時点で非課税のまま契約は実質的に終了し、贈与税を支払わなくて済みます。
とはいえ、延長した場合でも、40歳に達した時点で残高があればその残額には贈与税が課税されるため、資金を使い切る計画を立てることが重要です。
23歳以降もしくは学校卒業後の贈与者死亡によるケース
教育資金贈与の契約期間中に贈与者が亡くなった場合、受贈者が23歳以上、且つ学校を卒業している場合、残額は相続税の課税対象へ切り替わります。
ただし、贈与者が亡くなった時点で以下に当てはまる場合は、引き続き教育資金として利用することが可能です。
- 23歳未満であること
- 学校等に在学中であること
- 教育訓練を受けていること
なお、令和5年度の税制改正により例外の条件を満たしていても、亡くなった贈与者の相続税課税価格が5億円を超える場合は例外の適用がありません。
教育資金贈与で失敗しないための対策

教育資金を使い切れないことで税負担が増える可能性がある場合、契約時の必要額は適正に見極めたうえで支援することが大切です。
また、途中解約が難しく、祖父母の医療費や介護費用に回せないため、資金計画を綿密に立てておいた方が良いでしょう。
さらに、他の贈与制度や都度贈与を併用して負担を分散させる方法も効果的です。
ここでは、教育資金贈与で使い切れない場合に失敗しないための具体的な対策について解説します。
適切な贈与額の設定方法
教育資金贈与を「使いきれない」リスクを避けるための基本的な対策は、贈与額を適切に決めておくことです。
非課税枠が最大1,500万円あるからといって、必ずしも満額を贈与する必要はありません。
むしろ、実際に必要とする教育費を慎重に見積もり、過不足のない範囲で贈与額を決めることが重要です。
例えば、小学校から高校までは公立、大学は私立文系のように具体的なイメージを想定し、入学金、授業料、施設費、教材費などを計算します。
なお、適正な金額を計算するためにも、文部科学省の学習費調査や日本政策金融公庫の調査データなどを参考にした上で計算しておきましょう。
教育資金として認められる具体的な使途
贈与した資金の課税リスクを避けるためには「教育資金として認められる資金使途」を正確に理解しておくことが重要です。
対象範囲を間違えると、使えるはずの費用が使えずに資金が余るだけでなく、対象外の使途に支払うことで贈与税がかかることもあり得ます。
具体的に教育資金の対象となる範囲は以下の通りです。
1.学校等に対して支払う費用(非課税枠:1,500万円まで)
授業料 入学金
保育料 施設設備費
入学検定料 在学証明書代
卒業証明書代 給食費
スクールバス代 遠足費
修学旅行費 部活動費
寮費 PTA会費
生徒会・学級会費 大学入試センター試験受験料
通学定期券代 留学のための渡航費 etc
学校等とは、幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校などが含まれます。
2.学校等以外に支払う費用(非課税枠:500万円まで)
学習塾、そろばん、英会話などの習い事の受講料
スポーツや文化芸術活動の指導料
習い事や塾で使用する物品の購入費
ただし、23歳以上の受贈者は、学校等以外への支払い(習い事・塾等)は非課税の対象外です。
3.認められない使途の例
医療機関に支払う病児・病後児保育費
書店で購入した教科書以外の書籍代
下宿代や同窓会費
学校等が認めていない任意の支出
なお、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管するため、資金を支払った際には後から領収書等の提出が必要です。
また、支払いから1年以内、もしくは支払った年の翌年3月15日までに領収書等を提出する必要があるなど、一定のルールを理解しておきましょう。
契約後に後戻りができない
教育資金贈与信託の口座へ入金すると、原則として解約や資金の転用が認められません。
また、口座内の資金を定められた教育目的以外に使用することも禁止されているなど、ルールは厳格です。
例えば、贈与者が「急に資金が必要になった」と考えても、基本的に元に戻せず、途中で資金を引き出してしまうと非課税措置の適用から外れます。
特に、祖父母が高齢の場合、介護施設への入所や医療費の急な出費も考えられるため、後からまとまった資金が必要になる可能性も考えておきましょう。
いずれにせよ、資金が長期間にわたって拘束され、流動性が著しく低くなるという点は、この制度のデメリットと言えます。
利用を決定する前に、基本的には「後戻りできない」という特性を十分に理解し、あくまでも余裕資金の範囲内で、無理のない金額を設定することが大切です。
他の贈与制度との効果的な組み合わせ
教育費を支援する方法は、教育資金贈与の非課税制度だけではありません。
他の贈与を検討したり、組み合わせたりする方が有利な場合もあります。
例えば「暦年贈与」と「都度贈与」の活用です。
暦年贈与は、年間110万円までであれば非課税となるだけでなく、特別な手続きも不要、かつ使い道も問われません。
都度贈与は、入学金や授業料など、教育費が必要になったタイミングで、都度、必要な額を支払う方法です。
教育資金贈与の一括非課税は大きな魅力である一方、暦年贈与や都度贈与のメリット・デメリットと比較した上で、最も合った方法を選びましょう。
まとめ
教育資金贈与は、多額の資金を支援できる一方、使いきれない場合の贈与税リスクを理解しておかないと後から課税される可能性があります。
最大1,500万円まで非課税となるメリットなどが多いものの、使い切れない場合の贈与税や贈与者の死亡時の相続税、利用後には元に戻せないリスクも理解しておかなければなりません。
重要な対策は、教育資金として認められる範囲の正確な把握や必要な金額の慎重な見積もり、暦年贈与や都度贈与など他の方法とも比較検討することです。
ただし、判断に迷う、税金の計算や手続きに不安が残る場合は、専門家への相談をおすすめします。
専門家への相談は、不安解消につながる具体的なアドバイスを受けられるため、積極的に活用していきましょう。
弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。
収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!